安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
史跡
史跡とは、昔の人が食べた貝を捨てた「貝づか」、偉い人のお墓である「古墳」、戦争のときに味方を守るために作られた「お城」、人の住んだ家の跡である「住居跡」などのことです。昔の人々の政治、経済、生活、宗教などあらゆる活動によって作られ、現在も地面に残されている跡なのです。古いものでは何万年も前の旧石器時代の生活跡から、新しいものでは戦争の砲台跡まで実にいろいろなものがありますが、なんといっても昔の人々が使用していたそのままの場所ですから、昔の姿を簡単に思い起こすことができる貴重な地面です。しかし、史跡の場合、地面ばかりで、地面の上に建っていた建物は残っていません。そこで、県や市町村では建物を復元してわかりやすく見せるための整備をしています。このように、多くは広い敷地で保存され、公園や博物館などとして見学できるよう整備されたものが多いのでぜひ見に行ってみて下さい。
ちょっと寄り道 小杉丸山遺跡(こすぎまるやまいせき)編

小杉町・大門町流通センター内の一角にある、飛鳥時代後期(7世紀後半)の瓦、須惠器を焼いた窯や、粘土の採掘穴、工人たちの住居など当時の瓦や土器作りのようすが全貌できる遺跡です。
- 園内には、ガイダンス施設「飛鳥工人の館」があります。瓦や土器作りのようすを紹介したり、出土した瓦、土器などが展示されています。勉強してみよう。
- 野外には復元された登り窯や休憩小屋などがあり、秋には復元された窯を使って実際に土器焼きを行う「窯焼フェスティバル」が開催されています。ぜひ参加してみてはいかがですか。
クイズ 見に行ってチェック
復元された登り窯の長さは、どれくらいだろう。また、土器を焼くために必要な温度は何度だろう。
ちょっと寄り道 安田城跡(やすだじょうせき)編

婦中町井田川沿いにあり、発掘調査したところ、三つの曲輪とそれをとりまく堀、土橋などが発見されました。
- この安田城は1585年豊臣秀吉が越中の国(現在の富山県)の佐々成政を攻めるため、呉羽丘陵の山頂の白鳥城に陣を構えた際の支城といわれています。白鳥城を見上げてみよう。
- 資料館があるので、安田城が果たした役割をビデオを見たり、発掘調査で出土した土器などを観察してみよう。戦の雰囲気を感じることができるかな。
クイズ 見に行ってチェック
この戦いで勝ったのはだれでしょうか。
ちょっと寄り道 柳田布尾山古墳(やないだぬのおやまこふん)編
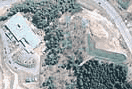
氷見市で発見された、日本海側で最大、全国でも十指に入る大型の前方後方墳です。発掘調査により、全長107.5m、古墳時代前期前半(今から約1700年前)に造られたことがわかりました。
- この古墳は、日本海の海上交通を押さえ、周辺には絶大なる力をふるった首長の墓と考えられています。だから海を一望できるこの場所に古墳があるのですね。海を眺めてみよう。
- お墓のあった主体部は残念ながら盗掘にあったようで、現在は大きな穴が空いています。なぜ盗掘をしたのだろうか、その理由を考えてみよう。
クイズ 見に行ってチェック
前方後方墳といいますが、どちらが前で、どちらが後ろでしょうか。

ちょっと寄り道 北代遺跡(きただいいせき)編

富山平野の中央部にある呉羽丘陵には、数多くの遺跡が確認されています。中でも丘陵の北側にある北代遺跡は、縄文時代中期後半(約4000年前)ごろの大集落遺跡です。
- 北代遺跡では竪穴住居と高床式倉庫が復原されています。倉庫を中心に環状に竪穴住居が配置されているのがわかりますか。真ん中は広場になっていたのでしょうか。
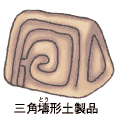 北代遺跡からは三角形をした珍しい土製品が発見されました。何に使ったのかはまだよくわかっていません。ガイダンス施設で展示しているので見て考えてみよう。
北代遺跡からは三角形をした珍しい土製品が発見されました。何に使ったのかはまだよくわかっていません。ガイダンス施設で展示しているので見て考えてみよう。
クイズ 見に行ってチェック
復元された竪穴住居の屋根は何で覆われているのでしょうか。
mini(ミニ)チェック
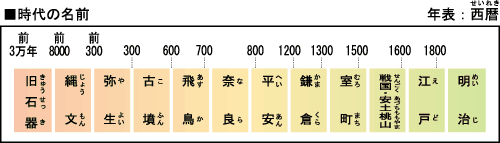
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください