安全・安心情報
トップページ > 県政の情報 > 知事室へようこそ > 知事記者会見 > 知事記者会見[令和6年度] > 知事記者会見(令和7年度当初予算案、組織案等)[令和7年2月18日(火曜日)]
更新日:2025年2月18日
ここから本文です。
知事記者会見(令和7年度当初予算案、組織案等)[令和7年2月18日(火曜日)]
- 日時:令和7年2月18日(火曜日)13時30分~
- 場所:議会大会議室
1.知事からの説明事項・質疑応答
(※)配布資料は「関連ファイル」からご確認ください
| 内容 | 動画 |
|
<発表項目>
|
【令和7年2月18日(火曜日)13時30分〜】知事記者会見(令和7年度当初予算案、組織案等)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
|
<質疑応答>
|
2.記者会見録
( )内は、発言内容を分かりやすくするため補足した部分です。(※)は、発言内容を訂正した部分です。
1.知事からの説明事項
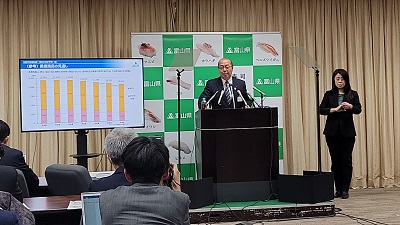
1.令和7年度当初予算案について
令和7年度の富山県の一般会計当初予算案、それから県庁活性化方針、この2本のことについて、今日まず私から話させていただきます。
まず、当初予算案ですが、2月25日開会の2月定例会に提案することになっております概要を説明します。
一般会計の予算案額は6,006億6,399万円です。令和6年度当初予算からは約120億円の減少となります。これは、コロナ禍で拡大した中小企業制度融資、ゼロゼロ融資やビヨンドコロナ応援資金など、これらの融資残高が返済によって減っていることによる預託金の減少が主な要因となっています。
また、国の経済対策に呼応し、11月議会に追加提案しました令和6年度11月補正予算と当初予算と一体に編成し、2月議会の冒頭に提案する予定の2月補正予算案を含めた16か月予算ベースでは6,411億1,282万円となりまして、能登半島地震からの復旧関係経費の減少などにより、前年度の同じく16か月予算から約276億円減少をしております。
それでは、令和7年度当初予算案のポイントをご説明します。
まず、重点分野の1点目、能登半島地震に係る復旧・復興ロードマップへの対応です。
11月議会の追加提案分、2月補正予算案、当初予算案を合わせまして、復旧・復興ロードマップへの対応経費として約54億円を計上しています。
地震の発生から1年余りが経過しました。これまでロードマップに基づき、スピード感を持って復旧・復興に取り組むとともに、災害対応検証会議において議論を進め、昨年末には検証報告書を取りまとめました。この報告書を踏まえて、新年度の取組みのポイントとして、特に地域防災力の向上に重点的に取り組みたいと考えています。
具体的には、災害時における国や市町村、民間団体との連携体制を強化するため、ワンチーム防災会議を開催するとともに、防災士の養成を強化してまいります。また、避難所の生活環境を抜本的に改善するため、トイレ、キッチン、ベッド、シャワー、いわゆるTKBSの設備を整備するとともに、県立学校などの体育館への空調設備の整備にも取り組みます。
次に、重点分野の2点目は、人口未来構想と「人口未来戦略」提言の推進です。
人口未来構想本部や成長戦略会議での議論を踏まえて、人口減少を抑制する対策、人口減少下においても社会を維持していく対策、そして、関係人口の創出・拡大に向けた施策などを推進するための重点経費として計38億円を計上しました。
人口減少の抑制と適応、関係人口の創出・拡大がポイントになります。
まず、共働き・共育てを応援するため、男性のより長期の育休取得に向けて育休の取得期間に応じて段階的に設定した助成金を交付するとともに、企業の福利厚生として従業員の家事支援サービス導入を普及するセミナーを開催します。また、結婚、子育て、仕事と家庭の両立など将来の人生設計となるライフデザイン形成を支援してまいります。
また、人口減少下においても活力ある社会を維持するためには、多様な人材が活躍できる環境づくりが重要であることから、本県としては初めて地域おこし協力隊を5名委嘱し、移住者の視点から移住促進や観光振興などの分野で活躍いただくこととします。
このほか、外国人材の活躍・多文化共生のための環境づくりも進めます。
また、大阪・関西万博の機会を十分に生かし、本県の魅力をアピールするほか、寿司のブランディング戦略や、スポーツコミッションの設立・運営、本県の強みを生かしたヘルスケアベンチャー誘致などを通じて、関係人口の拡大に取り組みます。
なお、「寿司といえば、富山」の展開の一環として、民間のすし職人養成学校の設立を支援することとします。
新たな総合計画の策定ですが、令和7年内をめどに策定することとし、県議会はもとより、市町村や関係団体など幅広く県民の皆さんの声をお聞きし、県民と共につくり、共に実現する計画を策定してまいります。
重点分野の3点目は、「未来に向けた人づくり」と「新しい社会経済システム」の構築です。
県民の皆様に選挙の際にお約束しました2つの八策、そして、その下に100の具体策、これらの実現に向けて、こどもまんなか社会の実現に向けた子育て支援や教育改革、また、新産業戦略などに取り組むための重点経費として計76億円を計上しました。
ポイントは、まず、こどもまんなか社会の実現に向けた施策展開として、こどもの権利に関する条例の制定に向けて検討を進めてまいります。また、「ワンチームとやま」連携推進本部会議の合意を踏まえ、こども医療費助成の対象年齢を小学生まで拡充します。
さらに私立高校の授業料については、現在国でも無償化に向けた議論が交わされていますが、国の決定を待つことなく、年収910万円未満世帯の私立高校の授業料を令和8年度新入生から段階的に実質無償化することとします。経済的理由によって子どもたちの自由な進路選択が妨げられることのないよう支援していきます。
次に、教育改革の推進、人材育成として、4月からの県立高校1人1台端末の保護者負担への移行に伴い、経済的な事情により負担が困難な家庭を対象として、端末の貸与や購入補助を行います。また、端末を授業の中でより有効に活用できるよう全ての県立学校のWi-Fi環境を強化します。さらにスクールソーシャルワーカーの配置を拡充します。
次に、本県の強みを生かした新産業戦略の展開としては、県内の中小企業の積極的な取組みを応援するため、地元金融機関と連携・協力した「中小企業成長応援ファンド」の造成を目指します。運用益を活用できる令和8年度から中小企業の新技術、新商品の開発や販路開拓などについて支援したいと考えます。また、サーキュラーエコノミーの推進に向けた異業種連携や新商品開発を支援します。
次に、インバウンド誘客促進として、さらなる増加が見込める欧米豪などの新規市場や高付加価値旅行者を中心に戦略的なプロモーションに取り組みます。先般、ニューヨークタイムズ「2025年に行くべき52か所」に富山市が選定されたところであり、これを追い風として北米市場については、私が自らニューヨークに赴き、トップセールスを実施しようと考えております。
また、高い波及効果が見込める高付加価値旅行者向けの宿泊施設整備の補助制度を創設し、誘致に積極的に取り組みます。
このほか、農林水産物の海外展開について、市町村や近隣県、全国知事会との連携を強化して、さらなる輸出拡大を図ってまいります。
次に、既存事業の見直し・再構築です。
本県の行財政を取り巻く環境は依然として厳しく、予断を許さない状況にあることから、限られた経営資源、マンパワーや財源ですけれども、限られた経営資源を効果的に活用するため、既存事業の抜本的見直し・再構築の徹底をより一層進めてまいりました。
このため、長年にわたり継続している事業は一旦立ち止まり、廃止または停止ができないか検討したほか、スクラップ・アンド・ビルドを一層徹底しました。その際には、部局ごとに事業費の見直し目標額を設定し、既存事業本数の2割削減を目指して、見直しを進めてきました。
この結果、見直し対象の2,553事業のうち、約4割に当たる1,046事業を見直し、そのうち602事業、見直し対象事業の23.6%になります。その602事業は廃止または停止としました。これによる見直し効果額は、事業費ベースで約33億円となります。
主な見直し事例は、記載のとおりです。ご覧ください。効果的な見直しを行うことができたと考えています。
次に、参考までにですが、中期的な財政見通しと県債残高の概要を説明します。
中期的な財政見通しは、昨年11月の予算編成方針の発表時には、令和7年度に50億円の要調整額、つまり財源不足を見込んでいました。このため、予算編成過程において事業の見直しや重点化・効率化を図るとともに、知事会などを通じた国への働きかけを含め、税収をはじめとする一般財源の確保に努めてまいりました。
今年度の税収は、堅調な企業業績などにより昨年度を上回る規模となる見込みであることから、新年度についても昨年11月にお示しした推計値を上回り、当初予算ベースで実質税収を過去最大と見込んでいます。地方交付税などを含む一般財源も、前年度より増額を見込むことができました。また、国の経済対策や新たな交付金の積極的な活用、既存事業の抜本的見直し、再構築などに取り組み、要調整額を解消することができました。
一方で、今後の事業見込みを踏まえ、令和8年度以降を試算してみますと、経済情勢にも左右されますが、引き続き一定の要調整額、令和8年度においては49億円、令和9年度において86億円が見込まれ、予断を許さない状況にあると認識しています。
今後も歳入歳出の両面から不断の見直し、改善を進め、持続可能な財政運営に努めてまいります。
なお、県債残高は、防災・減災・国土強靭化関係の事業などで増加するものの、臨時財政対策債の償還が進むため、減少傾向が続きます。令和7年度末には、県債残高が1兆626億円となる見込みです。
令和7年度当初予算案の規模やポイントについては、以上です。
重点政策別の主な事業をご説明いたします。
今のはポイントを説明しましたが、引き続きより中身に突っ込んだ話です。
まず初めに、能登半島地震に係る復旧・復興ロードマップへの対応です。
災害対応検証を踏まえて地域防災力向上ため、県や市町村、関係機関の連携を強化するワンチーム、災害対応力向上の人づくり、災害対応を迅速化・効率化するDX、避難所環境を改善する高品質、民間や県民参加を促す官民連携、この5つの項目を改善の柱として取り組んでまいります。
具体的に申しあげますと、まず、ワンチームの柱、行政や民間団体との協議の場の創設や、リエゾンが派遣先の市町村で円滑な活動ができるよう資機材の整備を行います。
次の人づくり、市町村や北陸三県との合同研修を実施するほか、今年度補正予算で実施回数を追加した防災士養成研修について、新年度は当初から拡充した量で実施をいたします。
また、DXでは、対策本部の通信手段の多様化・多重化のため、次世代衛星通信サービス「スターリンク」を導入するほか、効率的な情報収集・共有体制のため国と県の防災情報システムを連携します。
次の柱、高品質については、避難所の生活環境を抜本的に改善するため、トイレ、キッチン、ベッド、シャワーのいわゆるTKBS確保のための設備を整備します。また、県立学校などの体育館への空調設備導入にも着手します。
次の柱、官民連携ですが、県民の皆さんとの対話を行うほか、アプリ活用などによる災害救援ボランティアの連携体制の構築支援を行います。さらに四季防災館のリニューアルを行い、県民の震災経験の伝承と防災意識の向上に努めます。これらにより、起こり得るであろう次の災害に備えた対策を進めてまいります。
復旧・復興事業については、これまで数次にわたる補正予算を編成し進めてきているところですが、令和7年度当初予算においても所要額を計上しました。
まず、くらし・生活の再建のため、宅地の液状化対策を引き続き進めてまいります。
また、木造住宅の耐震化促進のため補助額を引き上げるとともに、新たに耐震シェルターの設置を支援の対象とします。さらに総合福祉会館の復旧工事や国指定文化財の復旧支援、水産資源の影響調査にも引き続き取り組みます。
地域産業の再生に向けては、11月補正予算で措置済みではありますが、なりわい再建支援事業により、中小企業などの施設の復旧を引き続き支援するほか、大変残念ですが、来年以降に延期となりました黒部宇奈月キャニオンルートの一般開放に向けた機運醸成や黒部峡谷鉄道の旅行商品造成などに取り組みます。
また、災害発生時に中小企業の資金繰りなどを速やかに支援できるように、制度融資に災害対応資金を常設にします。これを常設で置きたいと思います。
さらに北陸全体の復興に向け、関西圏情報発信拠点HOKURIKU+で魅力発信するなど、三県連携の取組みを進めます。復旧・復興はいまだ道半ばであり、引き続き被災者の皆様に寄り添ったきめ細やかな支援に最優先で取り組んでまいります。
以上が震災への復旧・復興ロードマップへの対応です。
次に、重点分野の2つ目は、人口未来構想と「人口未来戦略」提言の推進です。
まず、自分の生き方を主体的に選択できるとやまの実現のため、ライフデザイン形成を支援するセミナーを開催するほか、人口の自然減を抑制するため、県内企業などが福利厚生で活用できるマッチングアプリの構築、婚活イベントなど出会いを後押しする取組みをさらに拡充してまいります。
また、男性の長期の育休取得促進のための助成金、家事支援サービス普及など、共に働き、共に育てる機運の醸成に努めます。
県民が誇りと愛着をもち、県外の人から選ばれるとやまの実現により、社会増への転換を図るため、創業と組み合わせた移住支援や広域連携プロモーション、移住体験プログラムを行うマッチングツアーなどを行います。
また、首都圏で働く若者を対象に、「富山で働こう」キャンペーンを実施するほか、戦略的な企業誘致も推進します。
次に、人口減少への適応として、多様な人材が活躍して成長できるとやまを実現するため、UIJターン就職をさらに促進することとし、県内での就職活動で必要な交通費支援額の拡充を図ります。
また、増加する外国人住民の皆さんが県内で活躍でき、また多文化が共生する環境づくりに向けて多文化共生プランの改訂、また条例の制定に向けた検討を進めるとともに、企業などでの外国人材の活用と県内定着を促進します。
さらに農業の担い手確保のため、若い世代の就農支援に加えて、セカンドキャリアとして経営継承し、就農する50代の方を支援するほか、建設や公共交通の人材確保、活躍支援にも取り組みます。
地域の総合力を高め、安心して快適に過ごせるとやまを実現するため、ネットワークカメラを活用した見守り体制を強化するほか、中山間地域の活性化に向けて地域課題解決などに積極的にチャレンジする活動を後押ししていきます。
また、県民お一人お一人のウェルビーイング向上のため、自分ごとの意識と行動を促す事業や指標データの民間活用などを推進します。さらに人口減少・少子高齢化が進む中でも、多様化する県民ニーズなどにお応えできるよう持続可能な行政サービスの在り方に関して検討を行います。
なお、人口問題に限らず持続可能な社会の実現に向け、新しい富山県の未来を描き、さらなる成長・発展を目指す県政運営の基本方針を示す新総合計画の策定も進めてまいります。
次に、関係人口の拡大・深化に向けて、6月に大阪・関西万博に出展するほか、「寿司といえば、富山」のブランディング戦略として、国内外への魅力発信や人材確保・養成などの取組みを強力に進めます。
さらにスポーツを核とした取組みとして、官民連携のスポーツコミッションを設立・運営するほか、県総合運動公園の観客席など設備を更新し、J2カターレ富山の観戦などに訪れる方々への満足度の向上を図ります。
このほか、県内外の県人会が一堂に会する世界大会を本県で初めて開催するほか、農村地域での暮らし体験などの都市農村交流などに取り組みます。
なお、人口未来構想と人口未来戦略提言の推進のための施策立案に当たっては、ウェルビーイング向上を意識した施策設計図を作成し、今、ご説明した事業のみならず、幅広く検討を進めました。その施策設計図は、参考資料としてお配りしているところです。ご覧いただければと思います。
また、人口未来構想本部や「ワンチームとやま」連携推進本部会議で議論のあった人手不足対策についてですが、これは施策設計図の「6地域交通サービス」、「12産業振興」、「13農林水産業の発展」、「14社会インフラ」、「18学校教員確保」など様々なテーマで検討を進めたところです。詳しくは、明日開催します人口未来構想本部会議の中でお示しをしたいと考えますので、あしたまでお待ちいただければと思います。
次に、重点分野の3つ目になりますが、未来に向けた人づくりと新しい社会経済システムの構築です。
まず、こどもまんなか社会の実現に向けて、引き続きこどもの権利に関する条例の検討を進めるとともに、機運醸成のため国や民間企業などと連携したシンポジウムを開催します。
また、遠方の分娩施設で出産する場合でも安心いただけるよう交通費などの支援に取り組むほか、「ワンチームとやま」連携推進本部会議での議論を踏まえ、こども医療費助成制度の対象を小学生まで拡充します。このほか、子育て支援ポイントについて引き続き取り組んでまいります。
なお、私立高等学校の授業料を令和8年度の新入生から段階的に実質無償化することとしています。
次に、困難を抱える子どもへの支援として、4月にこども総合サポートプラザを開設し、いじめや不登校など様々な相談に対応します。
富山児童相談所と児童心理治療施設、学びの場、3つの機能を集約した施設は、今、仮称でこども安心センターという名前をつけておりますが、この整備も着実に進めます。また、児童相談所の法的な対応を強化するほか、子どもの居場所づくり支援にも引き続き取り組んでまいります。
さらに低所得のひとり親家庭の方に対し、食料品などの購入に利用できる1万円分の電子ポイントを交付するほか、困難な問題を抱える女性と子どもへの支援の実態やニーズを調査します。
次に、学校教育の充実と教育改革の推進です。
県立高校での1人1台端末の保護者負担への移行に伴う支援、活用環境の整備に取り組みます。また、小中学校でのスクールソーシャルワーカーの配置を拡充するほか、不登校の未然防止のため、市町村の校内教育支援センターの整備を後押しします。
さらに小学校の新規採用教員の負担軽減、県立高校の職業科での外部人材の活用にも取り組むほか、魅力と活力のある県立高校づくり向けて引き続き丁寧な議論に努めてまいります。
次に、多様な人材の育成です。
一昨年開催されたG7富山・金沢教育大臣会合では、サイドイベントとして、富山・金沢こどもサミットを実施しました。その際に参加した中学生、高校生の皆さんがまとめた宣言書に基づく取組みについて発信し広めるために、新たに「とやまこどもサミット」を開催します。
また、児童生徒のグローバル意識の醸成のため、国際バカロレア等に取り組むインターナショナルスクールのサマースクールの開催を支援するほか、中高生のキャリアプランに理工系分野の職種を選択肢として入れていただけるよう企業見学や交流会を開催します。
さらに県立大学において、情報工学部の新棟整備やインドのアンドラ大学との学術交流などに取り組みます。このほか、公立夜間中学の設置に向けて準備を進めてまいります。
次は、共生社会の実現です。
女性が働きやすい職場づくりを推進するため、官民連携の会議を新たに設立し、優れた取組みを横展開するほか、県外に進学した本県出身の女子学生の就職やキャリア形成に関する意識の変容過程などを探る調査を行います。
また、アンコンシャスバイアスへの気づきと解消を図るため、新たにアンバサダーによる普及啓発に取り組むほか、外国人の住民の皆さんが地域社会の一員として安心して暮らすことができるよう日本語教育環境の充実を図ります。
さらに認知症施策推進計画を策定し、認知症の方ご自身に大使となっていただき、普及啓発を行うほか、農福連携による食品などの販売や障害者アートの展示イベントなどを開催します。
次に、スタートアップへの支援などです。
本県が強みを持つ医療、バイオなどのヘルスケア分野でのスタートアップ企業の誘致やイントレプレナー、社内起業家のことをこう言いますが、イントレプレナーの育成のほか、中小企業成長応援ファンドの造成に取り組んでまいります。
また、県立大学に寄附講座を設置し、バイオ医薬品製造等に関する人材育成の取組を推進するほか、農林分野では省力化・効率化技術の導入による有機農業への転換の促進や、スマート林業の普及に取り組んでまいります。
次に、健康・福祉の充実です。
介護現場の生産性向上のため、ロボットやICTなどの導入を引き続き支援するほか、成果連動型民間委託(PFS)を活用した特定保健指導の実施率向上に努めます。また、悩みを抱える若者などの居場所づくりや摂食障害、高次脳機能障害の方への支援体制を充実します。
さらに長時間労働の多い医療機関に対し、労働時間短縮や医療体制確保のため医師を派遣する医療機関を支援するほか、社会福祉施設などを含め職場環境改善を推進します。
なお、今年は戦後80年の節目となります。悲惨な戦争の体験と記憶を風化させず、平和の尊さを次世代へ語り継いでいくことが私たちの重要な使命だと考えています。このため、「戦時下の暮らし展」を規模を拡大して開催するほか、映像制作・発信など若い世代の方々への周知啓発にもしっかり取り組んでまいります。
次に、文化・スポーツ・伝統分野の振興です。
美術館・博物館・文学館連携による企画展など、各文化施設での企画や情報発信に取り組みます。
また、スポーツ振興では、令和9年度中の開館に向けて武道館の整備を進めるほか、総合運動公園のさらなる魅力向上のため、民間活力の導入のための社会実験を行います。
加えて来年、ミラノ・コルティナ2026オリンピック冬季競技大会が開催されますが、その直後に予定されているスキーモーグルワールドカップの県内での初開催実現を後押ししたいと考えています。
さらに同じく来年、本県で開催されるプロ野球オールスターゲームを契機とした地域活性化の取組みを支援してまいります。
伝統分野については、伝統産業のプロデュース力の向上を図るための人材育成プログラムに取り組んでまいります。
未来に向けた人づくりの最後は、県庁改革の推進です。
県政の課題解決に当たり、若年層の意見を取り入れるため、オンラインコミュニティーを活用するほか、県民の皆さんに伝わる親しみやすい広報を目指して情報発信力の強化に努めます。
また、職員の人材育成やエンゲージメント向上のため、スキルや経験などの情報を一元的に管理するシステムを導入するとともに、引き続きチャレンジコンテストを行うほか、カスタマーハラスメント対策も進めてまいります。
次は、新しい社会経済システムの構築です。
インフラ・県土強靭化の推進については、河川や砂防、農地の防災・減災対策や橋梁やトンネルなどのインフラの老朽化対策、通学路の歩道整備など必要額を確保の上、着実に進めてまいります。
さらに県立高校の特別教室への空調整備や交通安全施設の改良、各種施設の維持修繕にも計画的に取り組みます。
安心で持続可能なまちづくりと公共交通について申しあげます。
県庁周辺エリアの「ありたい姿」の実現に向け、基本構想の策定を進めます。また、安全で安心なまちづくりのため、砺波エリアにおける新警察署の整備や水橋交番の移転新築工事を進めるほか、性暴力被害ワンストップ支援センターの相談体制を拡充します。ツキノワグマやニホンザルによる被害防止にも取り組みます。
公共交通については、城端線・氷見線の再構築事業を支援するほか、富山地方鉄道による鉄道の安全性や快適性の向上を促進するため、沿線市町村と連携して支援をします。さらに富山空港におけるコンセッション事業の開始に向けた準備など、空港活性化への取組みを進めてまいります。
次は、新産業戦略の推進です。
まず、新たな成長産業をつくり出すため、サーキュラーエコノミーやバイオの分野での取組みを進めます。また、産学官や企業間の連携による新たな付加価値の創出を目指し、アルミや医薬品の研究開発、人材育成に取り組むほか、伝統工芸産業と異業種とのコラボレーションも推進します。さらに、ものづくり総合見本市の開催、インドとの経済交流の促進など、県内企業の海外展開を促進します。
中小企業トランスフォーメーション補助金は、既に11月補正で措置しており、引き続き事業者の生産性向上を支援します。適切な価格転嫁のための支援体制も構築し、伴走支援を行っていきます。このほか高岡テクノドームの別館整備を進めるほか、県内企業の人材確保の取組みも後押しします。
エネルギー価格や物価高騰への対応については、国の経済対策の効果をいち早く県内に波及させるため、昨年の11月議会で追加提案し、既に各種取組を進めています。これらに加え、プレミアム商品券の発行に対する支援や省エネ家電・機器の買い換え促進などについて、当初予算案、そして、それと同時提案する2月補正予算案に盛り込んでいます。
次は、DXによる変革の推進です。
中小企業のデジタル化の状況に応じて段階的な支援を行うほか、商店街でのキャッシュレス決済の導入、農業機械の自動走行などのための環境整備、建設業のバックオフィス業務効率化など、DXの取組みを進めてまいります。
また、県へ手数料や使用料等を納付いただく際のキャッシュレス対応にも取り組んでまいります。
次に、カーボンニュートラルなどGXの推進です。
まず、住宅でのカーボンニュートラル実現やウェルビーイング向上のため、県独自の基準を満たす高性能住宅への支援に取り組みます。また、電気自動車や太陽光発電設備など再生可能エネルギー設備等の導入を引き続き支援します。
このほか県営の3発電所について、リプレースを進めるほか、魚津地域におけるバイナリー方式での地熱発電の導入に向けた検討を進めてまいります。
次は、観光振興による誘客促進です。
インバウンド誘客の促進のため、特に消費の旺盛なハイエンド層の誘致を強化するとともに、欧米豪をターゲットとした観光プロモーションも拡充して取り組みます。
また、富山と高山の周遊を促進するほか、高付加価値旅行者向け宿泊施設の整備支援制度を創設し、市町村とも連携し誘致に取り組みます。さらに北陸への観光誘客のため、北陸三県などで連携するなど、効果的な魅力発信に取り組みます。
次は、農林水産業の振興です。
担い手不足や高齢化、環境変化などの状況も踏まえ、持続可能な農林水産業の構築に取り組みます。輸出の拡大に向け、とやま輸出ジャンプアップ計画に基づき、北米などの新市場や近隣県と連携した欧州等でのプロモーションを実施するほか、「富富富」の生産振興に引き続き努めます。
また、担い手の確保・育成のため、集落営農の広域連携組織のモデルづくりや新規就農者の受入れ体制の整備への支援、女性が働きやすい環境整備や、とやま農業未来カレッジの研修体制強化などを進めます。さらに中山間地域での農業生産や棚田保全活動、農村RMOの形成を支援するほか、森林資源の循環利用を進めます。
このほか、震災による水産資源の影響調査や老朽化した立山丸の代船、代わりの船の建造を進めてまいります。
最後に、市町村との連携促進です。
引き続き「ワンチームとやま」連携推進本部会議を開催するとともに、地域の特色を生かした市町村などのまちづくりへの支援に取り組んでまいります。また、県や市町村、民間事業者が提供する生活に役立つアプリやサービスなどを連携するプラットフォームの利活用を促進します。
さらに地域おこし協力隊の受入れ促進に向けて、県において新たにサポーターを設置し、活躍する隊員の姿を情報発信するほか、持続可能な魅力ある田園地域の創出に市町村や地域の皆さんと協力して進めてまいります。
重点政策別の主な事業の説明は以上となります。
なお、成長戦略の推進に向けた令和7年度の主な取組みは、本日県のホームページで公表しています。詳細は、戦略企画課にお問合せください。
また、令和6年度当初予算において作成した施策設計図は、その後の事業進捗や状況変化を踏まえて更新し、同様に県のホームページに掲載しています。こちらのほうの詳細は、ウェルビーイング推進課にお問合せください。
令和7年度当初予算の説明は以上となります。
2.令和7年度の県庁活性化の取組みについて
引き続き、令和7年度の県庁活性化の取組みについて申しあげます。
昨年11月に策定した県庁活性化方針に基づき、県民のウェルビーイング向上に資する持続可能な県政推進体制の構築を図るために、組織の見直し、業務等の見直しを2つの柱として、具体的に取り組む内容についてご説明をいたします。
まず、組織の見直しです。
主なポイントとして、新総合計画の策定と企画部門の集約・強化、危機管理体制の強化、外国人共生社会の推進体制の構築、さらに観光推進体制の強化、職員のエンゲージメント・ウェルビーイング向上に向けた体制の強化、成長産業の振興・人材活躍の推進などの見直しを行います。
部局ごとでは、まず、知事政策局に「総合政策課」、「政策推進室」及び「企画室」を新しくつくり、企画部門を集約・強化します。企画室には、新たに「総合計画課」を設置し、成長戦略のビジョンや施策の方向性を継承する新たな総合計画を策定をします。
危機管理局では、防災・危機管理課を「危機管理課」及び「防災課」に改組し、指揮系統の強化を図り、迅速かつ効率的な業務執行体制を構築します。また、知事政策局から復旧・復興担当をこちらに移管し、災害対応検証会議を踏まえた復興・災害対策を実施していきます。国との連携を強化するため、県庁に在籍しながら内閣府防災担当の業務に従事する非在庁型研修員を防災課に配置します。
地方創生局に、「多文化共生推進室」を新設します。多文化共生推進室には、生活環境文化部から国際課を移管した上で、新たに「外国人共生社会推進課」を設置し、多文化共生施策の司令塔として条例の制定やプランの改訂に取り組みます。また、県人会世界大会の開催に向けて、部局の枠を越えプロジェクトチームを設置して取り組みます。
インバウンド需要の獲得や県内観光資源の強化に向けた体制構築のため、地方創生局から独立し、新たに「観光推進局」を設置します。新たな局をつくります。
経営管理部に「人事企画室」を新設し、職員のエンゲージメントやウェルビーイング向上に向けた体制を強化します。人事企画室には、新たに「人材戦略課」を設置し、昨年度策定した人材育成・確保基本方針に基づいた職員の育成や人材確保対策を推進します。また、持続可能な行政サービス提供のため、プロジェクトチームを設置し、戦略的な職員確保策を検討します。
商工労働部に「成長産業推進室」と「多様な人材活躍推進室」を新設します。成長産業推進室には、知事政策局からカーボンニュートラル推進担当の一部を移管して、新たに「エネルギー政策課」を設置し、再生可能エネルギー導入に向けた取組みを推進します。多様な人材活躍推進室には、新たに「人材確保推進課」を設置し、若者、高齢者、障害者、外国人など多様な人材が活躍できる社会の実現に向けた取組みを推進します。
次に、(2)として、定員の管理です。
一般行政、教員、警察官等を含めた全部門では事務の見直しによる減員を行う一方、病院の診療体制の充実、児童相談所の体制強化などについては増員を行い、差し引きで前年度より29人少なくなる見込みです。これにより、令和7年4月の職員数は1万5,220人となる見込みです。
一般行政部門については、令和4年4月の定員を基準とし、段階的な定年引上げに伴い、正規職員の増加が見込まれることなどから、3年間で32人を増員する計画としておりました。新たな行政需要などに対し必要な人員を配置してきましたが、60歳退職者が想定より多く、定年引上げによる増員が抑制されたため、21人の増となっております。
次に、組織の活性化と多様な人材の活用です。
まず、職員のチャレンジを応援する仕組みでは、職員が地域貢献活動へ積極的に参加できるよう特別休暇を創設し、地域活動の担い手不足の一助となる現場力を育成します。また、職員行動指針に沿った取組みを表彰する新たな職員表彰制度を創設し、職員のチャレンジを応援する機運を醸成します。
庁内複業制度やジョブチャレンジ制度は継続し、職員に事業提案を募るチャレンジコンテストについては、次年度は本採択に至らなかった事業を応援するステップアップ枠を新設するなど、職員の挑戦をさらに後押ししていきます。
次は、多様な人材の活用ですが、本県で初めて地域おこし協力隊の隊員を採用いたします。県外での在住や民間での経験を生かした地域おこしに取り組んでいただきます。高度専門人材や地域課題を解決する熱意とスキルを持つ外部人材も引き続き積極的に活用を進めてまいります。
次に、職員の育成・確保ですが、能登半島地震の検証を踏まえた危機管理体制の整備では、大規模災害発生時に迅速に対応するため、平時から全庁的に職員を動員できる体制を構築します。北陸三県知事懇談会で本県から提案した北陸三県合同災害対応研修ですが、受援・応援体制や広域避難などについての研修を夏頃までに開催いたします。
また、リエゾン業務や避難所運営、罹災証明発行業務などについて、市町村と合同で研修を行います。
県職員採用試験の見直しですが、職務経験者試験において、社会人経験枠の新設や基礎能力検査の実施、年齢要件の引上げを行います。上級試験の先行実施枠や初級試験の試験区分の拡大などの見直しを行います。既存のインターンシップに加えて、日替わりで民間企業と公務職場を体験できる合同インターンシップに参加いたします。
職員キャリア開発支援、研修体系見直しでは、職員のキャリア開発を支援するため、自治体初のセルフキャリアドックを導入します。
次は、職員のチャレンジ力・コミュニケーション力を強化するため、民間から学ぶチャレンジ講座の開催など、研修体系の見直しを行います。
続いて、2つ目の柱の業務などの見直しについてご説明します。
ここまでは組織などの見直しでした。
業務などの見直し、まず、県民目線での政策形成・執行、県民参画による行政の推進です。
県民のウェルビーイング向上を目指した政策形成・執行では、新年度予算編成において、未来構想、人口未来戦略提言を推進するため、ウェルビーイング指標の活用により、分野横断的に新たな事業の企画立案を行いました。
県民参画による行政の推進では、オンラインコミュニティーを活用し、県政の課題解決を図るための意見を広く求める取組を新たに始めます。
令和6年度の官民協働事業レビューでは、9事業について必要な見直しを行った上で当初予算案に反映したところです。来年度は事業選定に当たり、特定テーマの設定や県民評価者による現地視察など、県民参加の要素を強化して実施します。
わかりやすい広報・オープンデータの推進では、職員向けのSNS活用などに関する広報マニュアルの作成や県民(大学生等)との協働により、県政の情報発信力の強化に努めます。オープンデータについては、目的のデータに円滑にたどり着くよう現在、富山県オープンデータポータルサイトで提供しているデータを順次「富山データ連携基盤」に移行・集約するとともに、県民が利用しやすいファイル形式で提供してまいります。
次に、DX・働き方改革です。
まず、スマート県庁の推進では、昨年1月から稼働した新グループウェアのさらなる普及・展開に取り組み、県庁の働き方改革や組織文化の改革を推進していきます。汎用的な生成AIに加えて、グラフや図といった画像を処理できる高機能生成AIを新たに導入し、職員の業務効率化をさらに進めます。
また、県民が利便性の高い行政サービスが受けられるよう、行政手続の電子化をさらに推進します。収入証紙制度については、令和7年度9月末に販売を終了します。県内20か所にキャッシュレスなど多様な納付方法が可能な収納窓口を設置するなど、引き続き環境整備を進めてまいります。
実地監査、常駐・専任、書面掲示などのアナログ的な行為を求めるアナログ規制については、点検・見直しを進めており、今年度末までに全体の約90%の見直しを完了する予定です。
デジタルを活用した働き方改革では、各所属各部門から寄せられた業務改善の相談に対し、デジタル化推進室などがデジタル活用による業務改善に向けて伴走支援を行います。また、工事等事業管理システムを再構築し、様々なデータ管理・処理を一元化、電子決裁機能を付加して利便性を向上させるなど職員の事務負担を軽減します。
業務の効率化では、予算の説明でも触れましたが、スクラップ・アンド・ビルドを徹底し、対象の2,553事業のうち23.6%を廃止・停止するなど、既存事業の抜本的見直しを行いました。
児童虐待事案に迅速かつ的確に対応するため、富山県児童相談所情報管理システムの改修を行い、リアルタイムで児童の被虐待歴の有無等の情報共有が可能となるシステムを構築します。
県が施行する文書への知事印などの公印の押印を、法令の定めにより必要な場合などを除き、原則として不要とします。
また、公文書の保存基準などについては、文書保管コストの軽減や歴史的に価値ある公文書として保管すべき公文書選定の方策を検討してまいります。
ウェルビーイング経営の推進では、本館4階のモデルオフィスで複数の所属に体験勤務してもらい、意見や要望などを今後の県庁の働きやすく魅力的な職場環境づくりに反映していきます。食堂の一部を活用して、職員のコミュニケーションスペースを設置し、風通しがよく柔軟な発想が生まれる職場づくりに取り組んでまいります。
また、カスタマーハラスメント対応指針や職員向けマニュアルの策定、本庁などの電話設備に電話録音機能を導入するなど、ソフト・ハード両面から職員が安心して働ける職場環境づくりを進めてまいります。
次に、官民連携・民間活力の活用です。
県庁前公園の花壇について、令和8年度の改修を目指し、富山大学芸術文化学部学生らと協働して、新しい花壇の形をデザインします。
Park-PFIを活用した県立都市公園の整備については、県では太閤山ランド、五福公園、常願寺川公園の3つの都市公園において、民間事業者と連携しPark-PFIを進めてきました。
太閤山ランドでは、北陸エリアとしては初となる池越えジップラインなどのアドベンチャー施設を新設します。また、県で整備中のふわふわドームも併せ、資料では4月中旬オープンとなっていますが、日付が入りまして、4月13日のオープンを予定しています。
五福公園では、子どもからお年寄りまで快適な憩いの場を提供するため、飲食店を新設します。4月下旬のオープンを予定しています。
常願寺川公園では、ファミリーやグループが手ぶらで気軽にバーベキューを楽しめるエリアを新設します。夏頃のオープンを予定しています。
県総合運動公園へ民間事業者の参入や投資を呼び込むことを目的に社会実験を実施し、民間活力の導入に向けた市場性や採算性を調査します。
また、県と包括連携協定を締結している企業は現在25社まで増えましたが、この企業との連携をより一層強化してまいります。
次に、公共施設マネジメントの推進です。
人口減少や少子高齢化、多様化する県民ニーズなどに対応するため、持続可能な行政サービスの在り方について検討するとともに、公共施設などの保有総量の適正化と最適配置を推進してまいります。
また、県庁周辺の県有地については、県民や民間事業者からの意見の反映に努め、基本構想を策定するとともに、NHK跡地の暫定利用を推進します。県庁舎については、県庁周辺エリアマネジメントとの整合を図りながら、また、県民の皆さんの意見をお聞きしつつ、将来を見据え中長期的に検討してまいります。
カーボンニュートラル戦略における県の率先行動目標の達成に向け、令和7年度より、本庁舎及び県議会議事堂の電力は、企業局の県営水力発電所で発電した再生可能エネルギーを活用することで、県本庁舎などの電気使用に伴うCO2排出量はゼロとなります。また、令和7年度は、衛生研究所ほか5施設に太陽光パネルを設置いたします。
次に、外郭団体及び公の施設に関する検討・見直しです。
まず、外郭団体の見直しでは、今年度に行われました包括外部監査を踏まえ、既に実施されている外郭団体の経営状況などの指導・監督に加え、事業計画の策定やその達成状況などに対する県の点検・評価体制などを検討してまいります。
また、公益財団法人伏木富山港・海王丸財団が所有する帆船海王丸は、建造から既に94年が経過しており、令和9年度に船舶安全法に基づく定期検査を受ける必要があります。前回平成24年度同様、大規模な修繕が見込まれることから、来年度新たに設置する海王丸保存活用検討委員会において、その実施方針を検討いただくこととしています。
公の施設に関する検討では、平成3年の供用開始から33年余りが経過した富山県ゴルフ練習場について、施設の老朽化などから現在の指定管理期間が満了する令和7年度末をもって廃止いたします。廃止後の土地・建物については、民間事業者の知恵を借りながら新たな利活用案を検討するため、令和7年度に公募型プロポーザルを実施したいと考えております。
また、ネーミングライツは自主財源の確保や施設運営の安定化のほか、官民協働の推進にもつながることから、今後県有施設への導入を進めてまいりますが、まずは新川こども施設と四季防災館において導入に向けた検討を先行して進めてまいります。
令和7年度県庁活性化の取組みについては、以上です。
私からの冒頭の説明は以上となります。
2.質疑応答

【記者】
まず、予算の中身、子ども関連の施策のことなんですけれども、7年度予算も非常に多く盛り込まれていると思うんですけれども、子ども施策に関する予算額、令和6年度の場合は407億円で過去最高額ということだったんですけれども、7年度の予算では子ども関連の額、総額でいくらになるかということと、また、そこに込めた知事の思いですとか、狙いなども併せてお願いします。
【知事】
やはりこどもまんなか社会、これを進めるということをかねてより標榜しておりますので、前年度も大変多くの予算を配分しましたが、令和7年度でもさらに大幅に増やしております。子育て環境の充実などに重点を置いています。
教育費も含めてですが、子ども政策費では、令和6年度の当初予算に比べまして、プラス31億7,000万円、令和6年は今おっしゃったように、406億9,000万円でしたが、令和7年度当初予算案では438億5,000万円と増やしています。
主な増える要因ですが、富山児童相談所のこども安心センターの移転新築整備に加えまして、こども医療費の拡充、県立学校の学習用ネットワーク環境の整備、県立高校1人1台端末の保護者負担移行に伴う低所得世帯などへの支援、義務教育課程における1人1台端末更新に係る市町村支援などによるものです。これらが増える要因です。
このほかにも、こどもの権利に関する条例の検討の経費、さらに、こどもまんなか社会機運醸成のためのシンポジウムの開催、スクールソーシャルワーカーの配置の拡充、また安心して妊娠・出産を行うための支援体制の構築、子どもの居場所づくりのためのフリースクールなどの運営実態の調査など、「ワンチームとやま」連携推進本部会議での議論を踏まえた新規・拡充事業を数多く計上しました。
こどもまんなか社会の早期実現に向けて、あらゆる施策を総動員して取り組んでまいります。昨年の選挙での公約の2本の柱、未来に向けた人づくりが片方ですけれども、その特に中心は、やっぱりこどもまんなか社会をつくっていく。未来を担っていくであろう子どもたちの子育ての支援、また望まれる方の出会い、妊娠や出産を応援する。このようなことに438億5,000万円を盛り込んだということで、こどもまんなか社会をしっかりと進めていきたいと考えております。
【記者】
続きまして、事業の本数の削減について、既存事業の23.6%に当たる602事業を廃止して当初の目標をクリアした形になりましたけれども、この数字をどう評価されるのかということと、今後の方針も含めてお願いします。
【知事】
昨年の予算編成方針の段階で約50億円の要調整額があるということは、そのときに申しあげました。結果的にはそれを、要調整額をクリアすることはできましたけれども、その1つが、この既存事業の見直しによって資金を捻出するということであります。それを様々な目標を設けて予算(編成)に当たってもらったわけであります。
長年続けてきた事業もあります。部局長にとっても、また担当の皆さんにとっても、身を切るような思いであられると思いますが、でもそこをあえて判断をしてもらいまして、目標どおり、全ての事業が対象ではなくて、そのうちの対象にしたのは、そういういわゆる義務的経費とかそういったものはどうしても動かせないものがあるので、対象の事業が2,553事業になりました。このうちの602事業を身を切る改革、選択と集中ということで602事業を廃止・停止したということ。本数での2割削減を目標としておりましたが、23.6%となり、これを達成することができました。
また、あわせて、この見直し額は昨年度を大きく上回りました。昨年度は17億7,000万円でしたが、本年度この23.6%削減で、見直しで約33億円を捻出することができました。予算編成方針の思いを職員の皆さんが酌み取ってくれて、厳しい中で少しでも資金を捻出しようということで取り組んでくれた成果を私は大変にありがたく思っております。
ただ、これで到達点ではないので、これからもやっぱり不断の身を切る改革というものは行っていかなければならないと考えておりますが、今のところは、とにかく職員の皆さんにはご苦労さま、ありがとうと申しあげたいと思います。
【記者】
続きまして、マニフェストについて関連ということで、100の具体策のうち、この予算案に盛り込まれているのが、予算計上が不要なものも含めて82項目と聞いていますけれども、入っていない18項目というのはどのようなものがあるのか。また、入っていない理由ですとか、それらの項目を今後どういうふうに進めていかれるかをお尋ねします。
【知事】
今回の当初予算案、それからまた令和6年度の補正予算、11月補正と2月補正ですが、2月補正はこれから県議会に併せて提案するものですけれども、これのうち、私の昨年の選挙公約である「未来に向けた人づくり」、そして「新しい社会経済システム」、この2本の柱、2本の八策の下に100の具体策を入れてあります。
その中で、今回直接対応する事業を予算計上できたのが79項目です。それから、直接対応する取組みを実施しますが、予算の計上が不要なものもありました、3項目。合わせて82項目、これについて、今回当初予算で盛り込むことができたということであります。
直接的にはまだ対応できていないもの、こういうものでも関連事業は予算を立てていますが、直接的には対応できていないということで、こういうものが18項目となります。どういうものがその18項目かというと、今回速やかに予算措置できるものは盛り込みました、フルに。だけれども、市町村、あるいはほかの主体などと調整の必要な項目もあります。主にこの18項目は、そんなものです。
例えば市町村と連携し、ゼロ~2歳の第2子の保育料無償化を目指すということ、あるいは県庁の女性職員の管理職への登用目標である25%の達成を目指すとかですね、それから、県内医薬品メーカーの弁護士派遣制度、インハウスローヤーの導入などを支援する。県営の電気事業への民間活力を導入し、一層の収益の確保を図るなど、そのようなもの等々18項目が今回は取り上げていないということです。ほかとの調整を待って、また予算の必要なものは予算措置をしていきたいと考えています。
2期目最初の予算編成ですが、そういう意味では100分の82というのは、悪くない割合かなというふうに考えております。
【記者】
今回の予算にキャッチフレーズをつけるとすれば、どういう形になりますでしょうか。
【知事】
これいつも聞かれることで、積極的に言っているわけじゃなくて聞かれるから言っているということでご理解いただきたいと思いますが、令和7年度の予算を一言で表すとしましたら、「地域防災力を高め、富山県を前へ。」このように申しあげたいと思います。
引き続きロードマップに基づいて震災からの復旧・復興に努めてまいりますが、まだ道半ばです。でも、この震災から教訓を得ています、いろいろと。それを有識者を交えた検証会議を経て、昨年末に検証の報告書を作りました。それに基づいて5本の柱、先ほども説明しましたが、これに基づいて新年度予算では地域防災力を高めてまいります。
そのような意味で、やっぱり地震を忘れないという意味も込めて、地域防災力を高めていくということ。そして、それは何のためかというと、やはりもちろん傷んだ家屋や傷んだ企業、傷んだインフラを直していくということはもちろんですけれども、その先にはやっぱり富山県をさらに前に進めていく。そのような目標を持ってつくった予算であるということを表したいと思います。
【記者】
最後に、今後の財政運営の方針についてお聞きしたいんですけれども、県債残高が見込みでは僅かに7年度は減っているということで、財政調整基金も一番低かった昨年の6月から3,300万円ほど、結果まあ持ち直しましたけれども、それらを踏まえて今後の財政運営のビジョンですとか、方針などをお願いします。
【知事】
先ほども申しあげたように、昨年秋に予算編成方針の中で示した要調整額、これは何とか様々なやりくりの結果、解消することができました。でも、これも先ほど申しあげましたが、8年度以降も数十億円単位の要調整額が出るものと見込んでいます。
今後の財政運営も決して楽なことではないというふうに考えております。やはりこれは個人の生活でもそうだと思いますが、借金というのはやはりできるだけ身軽にしておくことが必要だというふうに思っております。なので、引き続き歳入を増やすように努力をする一方で、先ほどの事業の選択と集中などを不断で行うことによって、歳出を極力切り詰めていく。そのようなことで県債残高もできるだけ減らしていきたいと考えております。
これは、もちろん積極的に財政を出動するというお考えもあろうかというふうに思います。ただ一方で将来の富山県民の負担というものも考えて、我々はそのバランスを取りながら、行政というものを運営していかなければなりません。
なので、そのために今やるべきことは、極力選択と集中を利かせていく。そして、できるだけ歳出を減らしていく。また、もちろん歳入を増やしていくという努力も新産業の育成など、そんな努力もすることによって、将来世代への負担をできるだけ伴わないように現在の富山県の活気を生み出していく。そんなことに努めていきたいと思います。
【記者】
先ほどの質問と重なる部分もあるんですけれども、事業の抜本的見直しに関連しまして、これまでですと財源の確保だけではなくて、人手不足、言わばマンパワー不足にも対応するというお話があったんですが、こうした事業の見直しで、これまでどういった課題が、人手不足に関してはこれまでどういった課題があって、この見直しでそれがどういうふうに解消されていくのか。それについて一言お願いします。
【知事】
トータルの人員については、先ほど申しあげたとおり微増であるということであります。結果的にはそういうことになっていますが、その人員、マンパワーについての予算編成方針のときに申しあげたことは、いつまた何どき昨年のような自然災害、あるいはほかの災害が起こるかも分からないと。そのときのために財源とマンパワーというものをある程度確保しておきたいということを申しあげました。今回の事業の抜本的な見直しは、そういった意味もあったということであります。
ただやっぱり県庁も日々動いて生きているので、その有事対応の人たちを別にプールしておくわけにはいきません。今それぞれの組織に各部門にちりばめてあるわけでありまして、いざとなった場合、特に災害時などについては、そういった経験者は全てリストアップしており、いざとなったらそういう人たちを招集といいますか、集めてそういった有事に対応するという、そんな体制をつくっていくということです。
【記者】
事業の中身の人口減少だとかに係る知事の考え方について、1点お伺いします。
人口減対策は出会いの支援だとか関係人口だとか外国人材だとか、非常に多角的な視点で取り組まれていくのかなと思うんですが、出会いのところ、今回、前回の別の会議でもご発言があったような、アプリの開発だとか、新たな出会いのサポート事業だとかという取組みがあって、先ほども出会いを後押しする取組みを拡充していくというようなご発言があったかと思います。
現状、マリッジサポートセンター「adoor」だとかということで、同じような出会いだとかの支援というのはされておられると思うんですけれども、こういう何か別のものを入れたということについて、これはどういった狙いでこういった事業を盛り込まれたのか、お考えを教えていただけますか。
【知事】
出会いをご希望される、あるいは結婚をご希望されるそのような方に向けて、入門編でTOYAMATCHというのがあります。それから、結婚も意識しての方々にはadoorがあります。これも今も運用しております。
たださらに強化をしようということで、新年度に盛り込んでいるのが、企業向けのマッチングアプリを開発して、それを企業にお使いいただこうということです。それは議論もあるところであり、庁内でも議論がありましたように、そこまでやるのかということですが、でも、そこまでやるということです。もちろん企業が望まれればということなんですが、ぜひ多くの企業にこのアプリを活用いただいて、言わばより安心できる登録者の中からマッチングをお互いにできるということなので、成果もより上がりやすくなるのではないかと考えております。開発した後は、より多くご活用いただけるようにプロモーションもしていければというふうに考えております。
何でそこまでやるんだということですが、やっぱりこれは人口減少、特に自然減を少しでも減らしていきたい、あるいは究極的には均衡させていきたい、そういうような目的であります。明日すぐにそうなることはありません。でも、こういった取組みをして積み重ねていくしか自然減の抑制というのはできないというふうに考えております。そのような思いです。
【記者】
関連で追加でなんですけれども、今回、福利厚生としてのサービスだとかということで、雇用とか働き方という面を改善することが少子化対策とかにもつながるという考え方はこれまでもいろんな計画で示されていたと思いますけれども、この企業を巻き込んでいくということの重要性について、どのように認識されているのか、この予算については、どのような考え方でその思いが入っているのかという、一言いただけますか。
【知事】
この少子化対策、あるいは子育て支援、女性活躍、社会減の抑制、さらに均衡、さらに社会増、これら全てのキーは、私たちがいろいろ考えた結果、企業の役割、なかんずく企業経営者の意識にあるというふうな結論であります。なので、企業に対する経営者に対する働きかけ、あるいは意識改革、あるいは啓発に重点を置いて取り組んできたところでございます。
今回の令和7年度の当初予算においても、このように企業向けの、企業をターゲット、ターゲットとは悪い意味ではなくて、企業がより動きやすいように、また経営者の皆さんがより経営の中にこういった人口への対策を盛り込みやすいような、そんな狙いで様々な施策を打っているということです。
【記者】
こどもまんなか社会の施策として、私立高校の無償化というものがあると思うんですけれども、段階的に取り組んでいきたいということだったんですけれども、先日も私立高校の関係者の方々から要望を受けたと思うんですが、どんな狙いで予算に入れていくかというのを改めて教えてください。
【知事】
かつてはですよ、私が高校生の頃は、よくこんな言い方をしました。やっぱり富山県は公立が皆さんお好きで、子どもたちも親も、そして私立は滑り止めなんて言った時代がありました。過去形ですよ、過去形。でも、今は違います。
公立高校、県立高校と私立高校が高校の教育においては、お互いが特色を出し合ってお互いが魅力を磨き、魅力を出し、そして切磋琢磨し合って高校教育を担っていく。両方ともメインプレイヤーだというふうに私は考えています。
ただ違いがあり、それはやはり学費のことです。Aの高校を選びたい、それが私立である。だけども、学費のことがハードルとなって選べないとしたら、これは不幸なことだと思います。それを解消するべく、昨年度、本年度と私立高校の授業料に対する支援を拡充してまいりました。そして、また令和8年度からも無償化に向けて段階的に進めていきたいと考えています。
ちょうど今、同じタイミングで国のほうでもいろいろな協議が行われることも承知をしています。それをにらみながらということになりますが、国がどうあれ、富山県としては、令和8年度から段階的に無償化を目指していくということになります。
それによって子どもたちが本当に自分の学びたい、あるいは部活動を選ぶ子もいると思います。自分の選びたい学校にお金の心配をないようにして選べるようにしたい。そういった思いで予算をつくっています。
【記者】
もう1点なんですけれども、知事の後ろにもおすしの写真があると思うんですが、「寿司といえば、富山」のブランディング推進として、すし職人の養成学校の設立に新たに予算を盛り込まれたということなんですけれども、改めて、「寿司といえば、富山」に対しての意気込みを教えてください。
【知事】
少しおさらいしますと、富山県というのは、皆さんも感じておられるように、こんなにいいところなのになかなか全国的に認知をされていないと。大体中ぐらいの認識しかないということ。これをやっぱり何とか突破しようということで、じゃ何が突破するツールとしていいのかということで、皆で成長戦略会議を中心に話し合った結果、おすしをぜひ掲げながら、1点突破していこうということで、「寿司といえば、富山」ブランディングが始まったわけであります。これまでも既に様々なことを行ってきました。3つのフェーズに分けて行っていきますが、人材育成ということも大きな柱になっています。
その上で、「寿司といえば、富山」といいながら、おすし店がどうも足元ではあまり増えていない、むしろ減っている市町村もあるという状況、これは特に人の問題です。後継者がいない、あるいは担い手がいないということで、閉店をせざるを得ないおすし屋さんもある。これでは残念なことですし、「寿司といえば、富山」ブランディングの根幹に関わることなので、すし職人の育成も行っていこうということ。
幸い民間でそのような機運が盛り上がってきたものですから、じゃ民間がやれることならば、別に役所が前に出ることもないので、民間の方を応援するという形の予算を今回令和7年度の予算に盛り込ませていただいております。
いろんなコースが、これはまたそれを説明することがあると、しかるべきときに説明があると思いますが、いろんなコースで職人さんを育成していきます。そして、一方でそういった人とお店とのマッチングなんかもできればというふうに思います。そんなことで、おすし屋さんを減らさない、増やしていく。そんなことにできればというふうに考えて取り組んでいるところです。
幸いこの前の総務省の統計で、世帯の外食のすしに対する支出が富山市さんが全国で一番になられたということ。こんなこともやっぱり富山市民の皆さんをはじめ、県民の皆さんが「寿司といえば、富山」をある意味じゃ、おいしく食べることによって応援をしていただいているのかなと思って、大変にありがたく思いますし、最終的には、全国で「寿司といえば」とお聞きをすると、「富山」と答える人が9割という大変に高い目標ですけれども、これへ向かって進めていければというふうに思っています。
【記者】
これまでの質問と重なっていて恐縮なんですけれども、理解のためにもう一度お聞きしたいことがあります。
人口減少に絡みまして、それでもやるのかという議論もあった。それでもやるんだという形で今回盛り込まれているものの、それでもやるのかというところの議論について、もう少しお聞きかせいただきたいんですけれども、例えばアプリなどを活用して職場で出会いを設けていくということは、性的少数者にとってみると、必ずしも過ごしやすい会社ではなくなる可能性もありますし、また、もともと社会の中に外国人の方に対するいろんな思いがあって、それでも共生していくんだと踏み込まれている点について、改めて知事のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。
【知事】
この出会いを応援する、あるいは結婚を応援する、あるいは妊娠を応援する。これは全て望まれる方に対してするということです。強制をするわけでは絶対にありません。そこはぜひご理解をいただきたいですし、様々なお考えの方がおられることは理解をしているつもりでございます。
そういった方々にもちろん強制はしないし、かつそういうことによって出会いや結婚や妊娠や出産を望まれる方々を応援すること、それはもちろんやっぱり我々としては、ぜひ制度をつくるなり、政策をつくったらお使いいただけるようにPRをしたいと思います。
それが必ずしもそういったお考えのない方にとって、もし、居づらさ生きづらさを考えることになってはいけないと思いますので、そのあたりはできるだけの配慮はしていきたいと考えております。
【記者】
あと、外国人材活用についても。
【知事】
そうですね。今、約2万2,000人ほどの外国人が富山県で働いておられます。ただ経営者の皆さんなんかとお話をしますと、あるいはいろんな福祉施設の方々ともお話をしますと、いずれも皆さん人手不足を憂いておられます。今かなり富山県の県民も、ご高齢の方でも元気な方は働いておられます。それから女性の有業率の高さは、これはもう富山県、かなり前より日本でも有数の高さであります。
なので、今後この中で人手不足をどう解消するかというと、一つは本当により長い時間、元気な限り働いていただこうということがまず一つ。それから、空いた隙間の時間をうまく、これはデジタルを使ってマッチングすることによって、そんな小っちゃな細切れの時間でも、ある程度まとまればそれなりの労働時間になるということ。そういったことをうまくマッチングして、足りないところを埋めていこうということも一つあります。
そういった努力もいろいろとしなければならないわけでありますけれども、でも、さらにということになると、やはりこれは外国人材の力を借りるということになると思います。外国人が近くおられることをあまり愉快に思われない方も、それはおられるんだと思いますが、私はいろんなこと、もし生活の習慣の違いがあるなら、それは話し合うことによって、日本ではこうだけども、ベトナムではこうなんだよね。フィリピンはこうなんだよね。それはやっぱり多様性を理解するということは私は可能だし、そうしていく時代だというふうに思っています。
もう今や、それこそ外国人がどんどん富山でも来られる時代ですから、そういった方々を毛嫌いしていては、あるいは不審に思っていたり、そういうことはやっぱりできない時代だと思います。お互いに理解をし合う、これが大切だというふうに思います。そのために多文化共生プランというものも今もありますし、これもリバイスしていきたいと思います。
さらにより着実に確実に外国人との共生を進めるための条例というもの、これも今後県議会と相談をして定めることによって、県民の皆様にも理解をしてもらいながら、外国人材が富山を選んでいただき、そして共に働き、共に暮らし、また共に子どもを育て、共にごみも捨てる。そんな隣人として受け入れていく、そんな富山県にしていく。やっぱり寛容で、そして多様性を認める富山県にしていくということ。
これは、未来を担う子どもたちにとっても、またグローバルな時代で生きていく子どもたちにとっても、あるいは世界に飛び出していく可能性のある子どもたちにとっても、こういったことを小さいうちに多様な国の人たちが富山にいるということ、そんな中で育つことは決してマイナスじゃない、むしろ大きなプラスになるということだと私は信じて、こういったことを進めていきたいと思います。
もちろん反対もあるでしょう、議論もあると思いますが、そこはやはりしっかりとお話し合いをして理解を深めていただきながら、やっていきたいと思います。
【記者】
観光の施策について何点かお聞かせいただきたいんですが、今回、観光推進局を新たに立ち上げるということで、まず新しい局を観光で立ち上げるということについての狙いと、知事の思いをお聞かせいただけますでしょうか。
【知事】
富山県にとって、もちろんアルミや医薬品製造などのものづくり産業というのは大切な産業の柱です。でも、日本全体にとっても、また富山県にとっても観光というものは、それと勝るとも劣らないインパクトを持つ産業に育ってきていると思うし、また今後ますます伸びていくんだというふうに考えています。
なので、これをしっかりと、そんな世界の、日本の観光に対する流れを、観光が活況を呈しているという流れを富山県でもしっかりと受け止めていくために、より観光に力を入れようということで、一つ独立した部局として分離独立するという、そんなことを組織上考えて、より強力に進めていく体制づくりをしたということでございます。
【記者】
具体的な施策についてなんですが、高付加価値宿泊施設の整備支援制度を新たに創設するということなんですが、以前からラグジュアリーホテルを誘致したいという議論もされてきた中での制度の導入、この狙いについてまずお聞かせいただけますでしょうか。
【知事】
もちろん多くのインバウンドが富山県を訪れてくださることはありがたいことなんですが、でも、それがともすれば京都やあるいは近い金沢でも、どうもそういう(オーバーツーリズムという)傾向になりつつある。オーバーツーリズムということになって、もともと富山県に住んでおられる、もともと住んでおられる富山県の住民の方々が住みづらく、生きづらくなるということは本末転倒だと思います。
じゃということで、一つの解決策が高付加価値なお客さん、1の消費を100人でしていただくよりも、100の消費を1人でしていただければ消費額としては一緒なわけでありますから、できるだけそういった方も交え、そういった方ばかりにはなかなか難しいとは思いますが、そういった高付加価値のインバウンドの方も迎えていくことが一つ方向性だというふうに考えています。観光庁なんかでもそういった考えによる補助金も頂いているところであります。
ただその場合に、富山県に少し今力不足なのは、宿泊場所であります。1回の旅行で100万、200万平気で使われるような方々がおられると。そういった方々が泊まるような宿泊施設を拡充する必要があると思い、これまでも様々なチャンネルで取り組んできたところなんですが、今のところなかなかまだ具体的な成果にはつながっていません。
なので、今回明示的にそういった制度をつくることによって、より多くの方が、要するに旗を上げることによって、その旗を見ていただいて富山県に投資してみようかという、そんな方をぜひ引き寄せていきたいというふうに考えています。
【記者】
もう一つ施策についてなんですが、今回はハイエンド層をターゲットとした商談会を開催するであるとか、あとはアメリカやフランスで観光PRイベントを現地で初めて開催するなど、欧米豪を意識された施策を幾つも展開されていると思います。先ほどのラグジュアリーホテルも含めまして、そういった方々に富山の魅力として何を売り込んでいきたいのかをお聞かせいただけますでしょうか。
【知事】
イギリスについては、これで3年連続でプロモーションを、これまでの例として、イギリスについては取り組んできました。そして、手応えを感じているのは、それが明らかに数字に表れているんですね。イギリスからのインバウンドの伸びはすごい高く出ています。やっぱりこれは1年、2年、3年と取り組んできた成果だというふうに思っています。
じゃ、やっぱりやれば効果が出るんだなということの手応えを得たので、新しくフランス、それからアメリカ、アメリカについては例のニューヨークタイムズの追い風もあり、それを受けながらやっていきたいということであります。そういうことですね。
【記者】
少し重なるんですけれども、人づくりの中での教育改革であったり、こどもまんなか社会の施策の中で、フリースクールへの助成というのは今年度からやられていて、自治体がフリースクールの民間に対して助成するというのは珍しいという話でしたが、新年度も継続と拡充という中で、またスクールソーシャルワーカーみたいなところについても拡充と。
ただこのあたりの知事の思いといいますか、先ほど今年度当初のお話でも聞かせていただきましたけれども、どんな富山の教育はどうあるべきかであったり、そのあたりの知事の思いをお聞かせください。
【知事】
教育については、もちろん教育委員会が責任を持って、数年に一度教育大綱というものを定めまして、これからの子どもたちにとってどういった教育が必要か、どんな力をつけて次の高等教育機関に、あるいは社会に送り出していくのかということを本当に議論を重ねて大綱とし、それに基づいて具体的な教育が行われているということです。
それの教育を享受できるのは、やっぱり学校においてなんですよね。でも、今ご存じのように不登校が増えています。不登校の子どもたちも決して取り残すわけにはいきません。まず居場所をつくり、そして、その居場所で学校以外でも学べる場所を極力確保していかなければならないということだと思います。
今のところ私どもの県庁では、不登校の子どもの教育場所を運営するノウハウは全くありません。なので、今は民間NPOが運営されるフリースクールというものを支援することが、今できる一番ベターなことではないかと思い、フリースクールの応援をしているところでございます。
本年度からは、利用料の支援、月額上限1万5,000円までというものも制度もつくりました。利用もされていますが、まだ不登校のお子さんの数、それからフリースクールを利用しておられる方の数から見ると、比較すると、この制度を使っている人はまだ十分行き渡っていないのかなというふうに思っていますので、これをさらに周知徹底してご利用いただけるようにしたいというふうに考えています。
もう一つ、フリースクールの現場から要望があるのは、今年始めたのはご家庭に対する保護者や本人に対する支援ですけれども、フリースクールの経常費などに対する支援も要望をいただいています。
これについては、ただ、今フリースクールも、いろんな規模もたくさんあって、1人のお子さんを受け持っておられる施設もあるし、20人以上受け持っておられる施設もあります。いろいろ幅広いので、ちょっと実態をしばらく時間をかけて調べてみたいということで、本年度そういった予算は、令和7年度に、そういったフリースクールの実態の調査という予算をつけて、その上でどのような支援をどのような規模ですればいいのかということを考えていきたいというふうに思っています。
【記者】
高校生のグローバル人材の育成なんかも、このポイントのところにあるんですけれども、割と幅広なメニューを何となく教育の施策の中で盛り込んでいるような印象なんですけれども、そこは非常に何か意識した点なのかどうかという、そのあたりの思いというのはいかがでしょうか。
【知事】
まあ幅広というか、やっぱりこどもまんなかで物事を考えていますので、様々な子どもたちが多様な価値観を育み、そして国際感覚を持ち、そして大切なのは独りきりじゃなくて、周りと力を合わせながら物事に取り組んでいく。そんな子どもたちを育むためにいろんな政策を打っていきたい、子ども関連の政策を打っていきたいということです。
それから、こどもまんなかではありますが、もう一つ、やっぱり教育の現場では教師の皆さんが大切だというふうに考えています。教師の皆さんが子どもたちを教え、子どもたちを育むことにフォーカスできるように、できるだけ教育のメインのこと以外のことの多忙化は解消したいということで、スクールソーシャルワーカーなどの今回大幅に拡充をしたということであります。
先生方が本来やりたい、やるべきことに集中していただくために、できるだけいわゆる校務というような事務作業については、極力外部人材を活用することによって、軽減をしていきたいというふうに考えています。
【記者】
こちらのほうの資料にある働き方改革、前段の資料にもあるんですが、業務の効率化の事業の見直しにつきまして、もう少しお伺いできればと思います。
知事は、11月、昨年の基本方針のところで見直しを打ち出されまして、その後、庁舎内で各部局ごとに、もしくは部局連携で見直しの議論をされておられたと思いますが、その間の、ちょっと中の話なのでお答えできる範囲で結構なんですけれども、一旦指示を出された後にその後の議論の経過ですとか、そのあたりは知事ご自身はどのような形で見ておられたのか。逐一報告が上がってきて、何か指示を出されたとか、そういった形での関与があるのかどうかというあたりをもうちょっとお聞かせ願えませんでしょうか。
事業の2割削減で、こちらのページでいうと28ページのところになります。業務の効率化で2割削減というのがありまして、スクラップ・アンド・ビルドで目標達成ということになったんですが、知事が最初に指示を出されたと思うんですけれども、その後、庁舎内の議論の推進をどのように見られたかというあたりをもう少し細かく聞きたいんですけれども。
【知事】
私の仕事は、最初にやっぱり大きな方針を出すことだと思い、部局長さんたちもとても経験を積まれた公務員でいらっしゃるので、というか私よりはるかに経験を積んだ公務員でいらっしゃるので、その予算編成方針なり私の大きな方針を受けて、あとそれをどう咀嚼して、そして現実解を導き出していくかということは、それはお任せをしているということであります。
結果、2割の削減ということをクリアしてくれたということであります。なので、先ほども申しあげたように、部局長はじめ職員の皆さんによく頑張っていただいたということを今は言いたいということですね。
【記者】
そうしますと、少し経過を見られて、知事のほうから追加の指示があったとか、そういうようなことは特になかったということなんでしょうか。
【知事】
そうですね。皆さんしっかりと受け止めてくれて、それを具体化して結果を出してくれたというふうに思っています。
【記者】
就任以来、1期目は特にそうだと思いますが、シーリングというような考え方を特にされない状況下で進められながらということなんですけれども、今回はマンパワーの確保も含めて必要だということで実施されました。
改めて知事がトップダウンという言い方かどうか分かりませんが、指示を出されたことで、こういったような結果が出たということについては、どのようにお感じでしょうか。
【知事】
まず、今回私はシーリングを復活させたとは思っていません。この世界で言うシーリングというのは、もう全てに対して1%マイナスとか、2%マイナスとか、言わば薄皮をむくように減らしていくことによってトータルである程度の削減をするというのがこの世界で言うところのシーリングだと私は理解しておりますが、そういった指示は全くしていません。
今回の2割というのも、あくまで事業の統合をしたり効率化したり、あるいは廃止したり、停止したり、そんなことで事業本数を減らそう。それによって資金も捻出しよう。マンパワーも捻出しようという、そんな思想でお願いをしたところでの23.6%ということなので、そういう趣旨でみんな受け止めてくれたというふうに思っています。
【記者】
もう1点は、来年度以降も、予算が足りていないことが想定されますので、引き続き、不断の見直しというものが必要だと。それがシーリングという形かどうかは置いておきますけれども、何かしらの見直しが必要だと思います。
深掘りの余地というのは、23.6%というのも結構大きな数字かなと思っているんですけれども、今後の余地がどれぐらいあるかというのは何となくお感じのものはありますでしょうか。
【知事】
はい。確かに23.6%というのは大きな数字だというふうに思っています。毎年これができるかというと、それはなかなか今ここで確約できることではないというふうに思います。
でも、引き続き官民協働事業レビュー、これも実施をしてまいります。もちろん我々も知恵を絞るんですが、さらに県民の皆様の違った視点からの切り込みなどもお貸しをいただいて、これからも選択と集中、それから改革と創造、これをさらに進めていければというふうに考えます。
【記者】
県庁のことといいますか全体的なことになってくるんですけれども、今回2期目がスタートしての初めての当初予算の編成だったと思うんですけれども、4年前、1期目に編成したときと何か心の変化といいますか、2期目が始まるに当たって何か思い入れとかそういったことはありますでしょうか。
【知事】
そうですね。最初の任期の最初の頃というのは、言うまでもなく、行政の公務員としては全くの新人だったので、またこの組織のトップとしても全くニューカマーだったので、本当に何といいますかね、模索をするような感じでしたね。
でも4年間こうやって、4年余り経験をしてみて、大きな組織ではありますけれども、どこを押せばどうなるかとか、どこを押すのがより効くのかとか、ちょっと職員も聞いているので、あんまり企業秘密、企業秘密ではないですけれども(笑)、そんなことも大分分かってきたと思います。言わば取説といいますかね。
なので、4年前に初めて令和3年度当初予算をやったときよりも、今回の令和7年度当初予算を編成するにおいては、いろいろとよくできているんじゃないかなというふうに思います。
3.関連ファイルのダウンロード
(※)関連ファイル(PDFファイル)をご覧になるには、Adobe社の「Adobe Reader」が必要です。Adobe Readerがパソコンにインストールされていない方は、下記のAdobe社のダウンロードページよりダウンロード(無償)してご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください