(従業者4人以上の事業所) |
本県工業の構造変化について、構成比が上位の業種の推移から見てみる。(1) 事業所数
1位を占めていたのは1980(S55)年までは食料品であったが1981(S51)年以降、金属製品となった。一般機械は概ね10%付近を推移し、電気機械は1990(H2)年から7%程度を占めている。
| 順位 | 1971
(S46) |
1975
(S50) |
1980
(S55) |
1985
(S60) |
1990
(H2) |
1995
(H7) |
2000
(H12) |
2002
(H14) |
| 1 | 食料品
15.5% |
食料品
14.0% |
食料品
13.9% |
金属製品
14.6% |
金属製品
15.1% |
金属製品
16.5% |
金属製品
16.4% |
金属製品
16.6% |
| 2 | 木材・木製品
10.9% |
金属製品
13.0% |
金属製品
13.1% |
食料品
12.0% |
食料品
12.0% |
食料品
11.9% |
一般機械
12.5% |
食料品
12.9% |
| 3 | 金属製品
10.4% |
一般機械
9.3% |
一般機械
9.7% |
一般機械
10.6% |
一般機械
11.3% |
一般機械
11.5% |
食料品
12.4% |
一般機械
12.8% |
| 4 | その他製造業
9.6% |
木材・木製品
9.0% |
その他製造業
9.2% |
繊維工業
8.0% |
繊維工業
7.3% |
衣服
7.4% |
電気機械
6.9% |
プラスチック
7.0% |
| 5 | 一般機械
10.6% |
その他製造業
8.9% |
繊維工業
8.5% |
木材・木製品
6.6% |
電気機械
7.2% |
電気機械
7.1% |
プラスチック
6.8% |
電気機械
6.8% |
※1985年にアルミ関連事業所の特殊格付け廃止による非鉄金属から金属製品への、1994年にニット製品の繊維工業から衣服への移し変えがあった。
2001年までの電気機械が2002年に電気機械、情報通信、電子部品に3分割されたが時系列比較上、分割前の括りによって2002年の構成比を出している。
(2)従業者数
繊維関連(1994年にニット関連産業が繊維工業から衣服へ移し変えられたことで構成比が逆転しているため2産業を合算して時系列比較をしている)が1位を占めていたが、海外への生産移転などにより2002(H14)年では6%を割り込んだ。他方、アルミ関連事業所の非鉄金属から金属製品への移し変えがあった(1985年と1984年以前における構成比の逆転はこの産業移動による)こともあるが、1985(S60)年以降、金属製品が1位を占めるようになった。また、電気機械は、1985(S60)年から上位に入り11から13%を、一般機械は11から12%、化学工業は7から8%を占めている(図27)。.
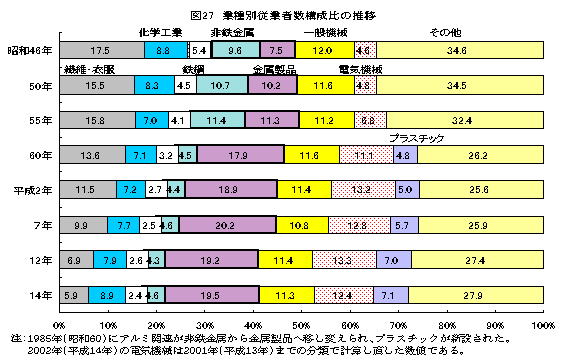
(3)製造品出荷額等
1971(S46)年には繊維工業や鉄鋼が10%程度を占めていたが、2002(H14)年では3%を下回った。他方、1975(S50)年以降、アルミ関連産業を中心とした金属製品、非鉄金属が上位を占めるようになった。電気機械は、繊維工業や鉄鋼に代わって1985(S60)年から上位に入り、部品関係を中心に伸びてきた。化学工業は10から14%、一般機械は概ね10%程度と、30年の間で上位を占めている(図28)。
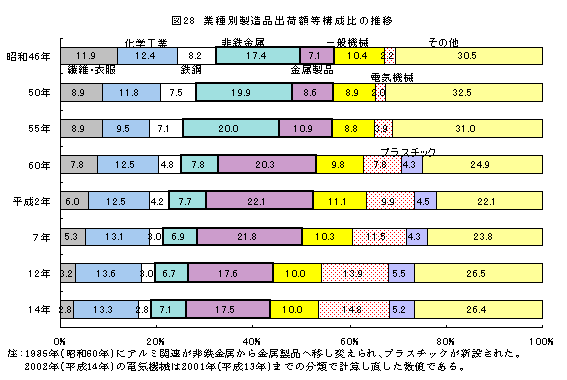
また、特化係数(1を超えていれば全国に比べ相対的に特化)をみると、アルミ関連産業が集中していることから金属製品が3.44(1985年4.20)、非鉄金属が3.40(同3.26)と極めて高くなっているほか、北陸3県に繊維産業が多かったことから繊維が1.85(同2.32)、衣服が1.16(同0.65)と高いものの、1985年に比べると金属製品、繊維の比重が低下している。また、電気関係産業のうち、電子部品が2.17(2002年からの新分類)と高くなっている(図29)。
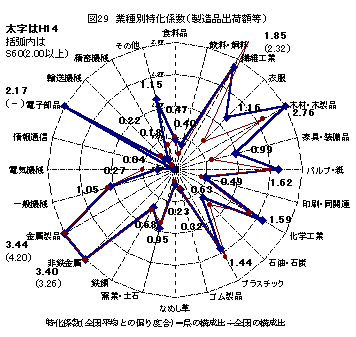
各項目へリンクします
1 概況 8 有形固定資産投資総額 2 事業所数 9 在庫額 3 従業者数 10 リース契約及び支払額 4 製造品出荷額等 11 1日当たり工業用水量 5 付加価値額 12 工業用地等 6 現金給与総額 13 地域別の動き 7 原材料使用額等 15 産業細分類及び品目別の状況