消費者物価指数の算出方法と
|
1.はじめに消費者物価指数(CPI:Consumer Price Index)はいろいろな指数の中でも、見聞きする機会の多い指数だと思います。CPIは「経済の体温計」とも呼ばれており、経済政策の重要指標となるほか、国民年金などの実質的な給付水準の改定でスライド率として利用される等、さまざまな分野で活用されています。最近では、デフレ脱却や日銀の利上げの判断材料として取り上げられるなど、金融政策の面からも重要視され、関心が高まっています。ここでは消費者物価指数の算出方法や留意点、富山市の消費者物価指数の特徴、18年度に行われた基準改定などについて述べたいと思います。 |
2.平成18年平均消費者物価指数の概要(1)消費者物価指数(富山市)平成18年平均の富山市の消費者物価指数(平成17年=100)は、総合指数で99.8となり、前年に比べ0.2%下落しました。これは、「光熱・水道」、「交通・通信」、「諸雑費」などが上昇したものの、「教養娯楽」、「家具・家事用品」、「保健医療」などが下落したためです。 なお、総合指数は、平成16年以来、2年ぶりの下落となりました。
(2)消費者物価指数(全国)平成18年平均の全国の消費者物価指数(平成17年=100)は、総合指数で100.3となり、前年に比べ0.3%上昇しました。これは、「教養娯楽」、「家具・家事用品」などが下落したものの、「光熱・水道」、「食料」、「諸雑費」などが上昇したためです。 なお、総合指数は、平成10年以来、8年ぶりの上昇となりました。 ※ 全国の消費者物価指数の詳細は総務省統計局のホームページをご覧ください。 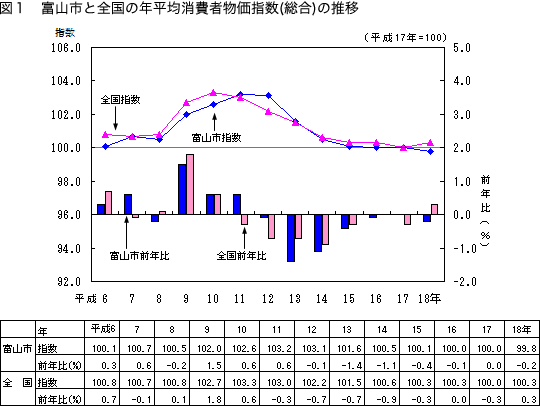
|
3.消費者物価指数の算出方法およびウェイトについてまず、CPIはどのように算出されるのかについて、大まかに説明したいと思います。 CPIは小売物価統計調査で得られた小売価格と、基準年(注1)の、家計調査の結果により作成されたウェイトを基に算出されます(注2)。 基本的な考え方は、以下のとおりです。
|
(1) 品目別価格指数の算出小売物価統計調査で調査された価格を基に、品目ごとの価格指数を算出します。価格指数は、ある品目の調査時価格と基準時価格により算出されます。基準時価格とは、その調査品目の、基準年(H17)1月から12月までの各月の価格を単純平均したものです。この価格を「Po」、調査月の価格を「Pt」とすると、調査月の価格を基準時価格で割ったもの(Pt/Po)が、調査月の品目別価格指数です。 分かりやすい例を下に挙げます。(あくまでも例なので、金額等は実際とは異なることをご了承下さい。)
つまり、平成17年の価格を100として、平成19年3月は112.5となります。 同様にして、他の品目についても品目ごとの価格指数を出していきます。もう一つ、食パンの例を挙げます。
|
(2)ウェイトの算出次に、ウェイトを作成します。ウェイトとは、家計の消費支出全体に占める、ある品目への支出金額の割合のことです。ウェイトは品目ごとに作成され、下位類(注4)のウェイトの和が上位類のウェイトとなります。
基本となる品目ごとのウェイトは、家計調査の品目別支出金額を消費者物価指数の品目に配分することで算出します。あんパンならあんパン、食パンなら食パンに使った金額がその品目のウェイトとなります。支出金額がウェイトとなりますので、最終的なウェイトの全国の値は全国の1か月間1世帯当たり消費支出金額にほぼ等しくなっています。また、参考として総合を1万とした1万分比ウェイトが作成されています。 下の[表1]をご覧下さい。消費支出の合計が15万円で、あんパンに150円、食パンに450円使った場合、総ウェイトは150,000、あんパンのウェイトは150、食パンのウェイトは450となります。また、1万分比ウェイトは、消費支出全体を1万とした場合の、その品目が占める割合ですから、あんパンでは 150÷150,000=0.001=10/10,000 1万分比ウェイトは10となります。 また、仮に「パン」という小分類が、あんパンと食パンの2品目から成るとすると、「パン」のウェイトは、あんパンのウェイトと食パンのウェイトの合計ですので、1万分比で10+30=40となります。(注5) ![[表1] 支出金額とウェイトの関係](_img/2-02.gif)
|
(3)物価指数の算出さて、ついに物価指数の計算です。先ほどの方法で出した価格指数を品目ごとのウェイトで加重平均し、物価指数を算出します。ここでは、先に出したあんパンと食パンの例を使い、この2品目のみで「パン」という小分類が構成されると仮定して説明します。あんパンの価格指数は112.5、食パンの価格指数は92.5で、ウェイトはあんパンが10、食パンが30だったとします。 「パン」の物価指数は以下の式で求められます。 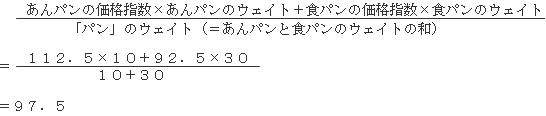 ここで、仮に、あんパンと食パンの価格指数が逆だった場合はどうなるでしょう。あんパンの価格指数が92.5、食パンの価格指数が112.5、ウェイトは上の例と同様に、あんパンが10、食パンが30だったとします。 この場合の「パン」の物価指数は 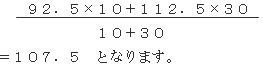 「パン」の物価指数は、食パンの価格指数に近くなっており、ウェイトの高い食パンの価格指数の影響を大きく受けていることがお分かりになると思います。 このようにウェイトを使って加重平均することで、あんパンよりも多くの金額が支出される食パンの価格の変動を、正確に物価指数に反映させるようにしているのです。 |
(4)価格と指数の関係についてここで1点、指数を見る上で気をつけなければならないことがあります。それは、指数はあくまでも時間の経過による価格の変化率を示すものであり、指数の大きいものの価格が指数の小さいものの価格よりも高いというわけではないということです。引き続き、あんパンと食パンの例を使って説明します。下の[表2]は富山市と東京都区部の比較表(例)です。(例なので、金額等は実際とは異なります。) 富山市のあんパンと食パンの価格を見比べてみてください。平成19年3月時点で、あんパンの価格は90円、食パンの価格は370円です。あんパンの価格指数が112.5で、食パンの価格指数が92.5でも、あんパンが食パンより高いとは言えないことがご理解いただけると思います。 次に、あんパンについて見ると、富山市の指数は112.5、東京都区部の指数は87.5となっています。この指数が示しているのは富山市では基準時と比べて12.5%上がり、東京都区部では12.5%下がったということです。価格については、富山市のほうが東京都区部よりも高いのか、指数を見ただけでは分かりません。[表2]のように東京都区部のほうが高い可能性も十分あります。 また、富山市と東京都区部で食パンの指数が92.5と同じですが、基準時価格が異なれば、当然、調査時点の価格は異なります。これは中分類指数や総合指数などについても同様です。 ![[表2] 価格と指数の関係(例)](_img/2-05.gif)
|
(5)消費者物価地域格差指数について地域間の物価水準の差を見る場合は、消費者物価地域差指数を利用します。 消費者物価地域差指数とは、全国平均を基準(=100)とした都道府県庁所在市などの年平均指数です。「通常のCPIは、ある地域における、時系列の物価の変動を見るもの」ですが、「地域差指数は、同一時点での、場所による物価の差を見るもの」です。通常のCPIが場所を固定しているのに対して、地域差指数は時間を固定します。地域差指数のウェイトは全国一律に、その年の家計調査の全国平均を利用します。 消費者物価地域差指数は、「総合(持家の帰属家賃を除く)」、「食料」及び「家賃を除く総合」の3系列について作成されます。また、東京都区部を基準(=100)とした指数も併せて作成されています。地域差指数を使えば、地域間の物価の比較が可能です。 [表3]は平成17年平均の都道府県庁所在市別の消費者物価地域差指数です。富山市は平成17年平均の「総合(持家の帰属家賃を除く)」で、全国平均を100として101.8、つまり全国平均よりも1.8%高く、47都道府県庁所在市中、19位となっています。1位は東京都区部で110.9、47位は那覇市で96.2です。 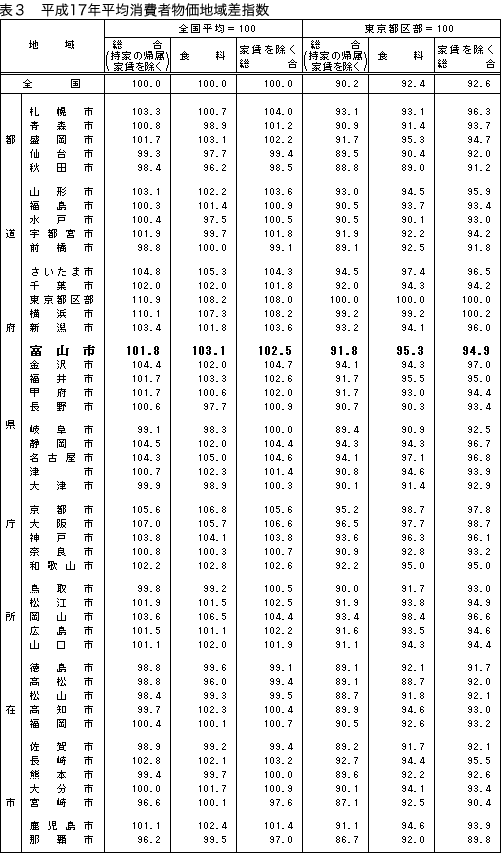
|
(3)18年平均の富山市消費者物価指数について平成18年平均の総合指数(平成17年=100)では、全国が100.3と前年比0.3%上昇しているのに対して、富山市は99.8と前年比0.2%下落しています。理由の一つとして、下落幅の大きい品目や類のウェイトが、全国よりも高いことが考えられます。 「3.消費者物価指数の算出方法およびウェイトについて」で説明したように、指数はウェイトの高いものの影響を大きく受けます。富山市のウェイトが全国と比べて大きい品目の指数が下落した場合、たとえその下落率が全国と同じでも、総合指数の押下げ効果はより大きくなります。 [表5]は平成18年平均消費者物価指数の全国と富山市の中分類指数の比較です。色を付けた「外食」、「家庭用耐久財」、「教養娯楽サービス」は、いずれもウェイトが富山市のほうが全国よりも高い中分類です。指数を見ると、「家庭用耐久財」では富山市は全国よりも大きく下落しています。「外食」と「教養娯楽サービス」では、全国は上昇し、富山市は下落しています。このように、ウェイトの高い分野で大きく下落したことが、総合指数の下落に影響していると考えられます。(ちなみに、平成17年の指数は、平成17年が基準年のため、全ての項目で100となっています。) なお、中分類の寄与度(指数の変化に与えた影響の度合い。平成18年平均の富山市のCPIは前年と比べて下落しているので、この場合、総合指数の下落にどれだけ影響を及ぼしたか)で見ると、寄与度の大きかったものから順に、「教養娯楽用耐久財」、「家庭用耐久財」、「通信」、「教養娯楽サービス」、「外食」、「保健医療用品・器具」、「医薬品・健康保持用摂取品」、「穀類」、「菓子類」、「飲料」となりました。 ※表をクリックすると大きく表示されます。
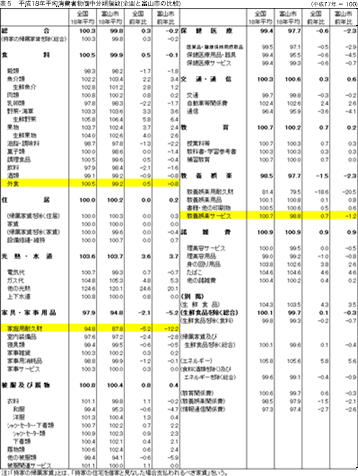 |
5.季節調整について消費者物価指数では、季節調整をしていません(注8)。そのため、季節によって価格が上下するものは指数も同様に上下します。例えば、「交通・通信」の中の「交通」は、航空運賃が上がる旅行シーズン(特に8月)に指数が上昇します。また、「被服及び履物」は、セールにより、毎年2月と8月に指数が下落します。 「被服及び履物」は平成17年4月以降、平成18年9月までは前年同月の指数を上回っていましたが、平成18年10月以降は前年同月の指数を下回りました。これは、17年の晩秋からの厳しい寒さで、冬物衣料の価格が高騰したこと、また、18年は逆に暖冬で、冬物衣料の価格が下落したことが影響しています。 ![[図2] 富山市の消費者物価指数の推移](_img/2-09.gif)
|
6.基準改定の内容について平成18年7月から、平成17年基準の消費者物価指数が公表されています。公表直後には「CPIショック(注9)」という言葉も聞かれた今回の基準改定では、具体的に何が改定されたのでしょうか。主なものは以下の5点です。 なお、平成17年基準指数と平成12年基準指数の差に関する解説は、総務省統計局のホームページに掲載されています。
(1) 指数の基準時の改定指数の基準時が平成12年から平成17年に改定されました。 (2) 品目の追加、整理統合家計での支出が増えている携帯電話、液晶テレビ、DVDレコーダーなど34品目が追加され、支出の減少しているビデオテープレコーダーなど48品目が整理統合されました。改定後の品目数は584品目になりました。価格の下落の激しい液晶テレビなどの品目が追加されたことが、指数の押し下げ要因となりました。 (3) ウェイトの改定これまでは家計調査の平成12年の品目別消費支出金額などにより作成したウェイトが用いられていましたが、上述のとおり、平成17年の結果等により作成したウェイトに改定されました。携帯電話料金などの品目は、値下げ競争により価格が下がっていること、また家計の中で支出金額が急激に伸び、ウェイトが高く改定されたことで、指数の押し下げ要因となりました。 (4) 指数の作成方法の改定例えば通信販売での利用が多いサプリメントについて店頭販売価格とホームページ等で確認した通信販売価格を合成した指数を作成するなど、現在の状況に合わせた方法に変更されました。 (5) 作成・公表する指数の拡充「情報通信関係費」、「エネルギー」などの指数が新たに作成されました。 参考までに、平成12年基準と平成17年基準の総合指数の前年同月比を比較してみます。(前年同月比を使ったのは「4.季節調整について」で述べたように、CPIは季節調整をしないため、季節要因に影響されない物価の動きを見るには、前月比よりも前年同月比が適しているからです。)全国、富山市ともに、平成12年基準では平成18年1月から7月にかけて、指数は前年比で上昇もしくは横ばいでしたが、平成17年基準では前年比で下落、または上昇した場合も上昇幅が減少していることが分かります。(棒グラフが一部表示されていないのは、前年同月比が0.0だったことを表しています。) 全国よりも富山市のほうが、平成12年基準と平成17年基準の差が全体的に大きくなっていますが、これは、教養娯楽用耐久財、家庭用耐久財、通信など、指数の押し下げ要因となったもののウェイトが、基準改定で全国よりも大きく増加したため、指数の下落圧力がより大きく働いたことが原因と考えられます。 ![[図3] 基準年による前年同月比の比較](_img/2-10.gif)
|
7.おわりに消費者物価指数の公表については、総務省では原則、毎月26日の属する週の金曜日に、前月の指数(東京都区部については当月の中旬速報値)を公表することとしています。県の公表スケジュールも同様です。例えば、5月は26日が土曜日ですので、その週の金曜日である5月25日に平成19年4月分(東京都区部は5月中旬速報値)が公表になります。総務省統計局のホームページのほか、とやま統計ワールドにも掲載していますので、ぜひご覧ください。 デフレ脱却や利上げなどのニュースの中で取り上げられる機会が増え、最近ますます注目を集めているCPIについて、本稿をきっかけに理解や興味を少しでも深めていただければ幸いです。 また、CPI作成の基礎となる小売物価統計調査及び家計調査に、皆様のご協力をお願いいたします。
|
![[表4] 平成17年基準 富山市と全国のウェイト比較](_img/2-07s.gif)