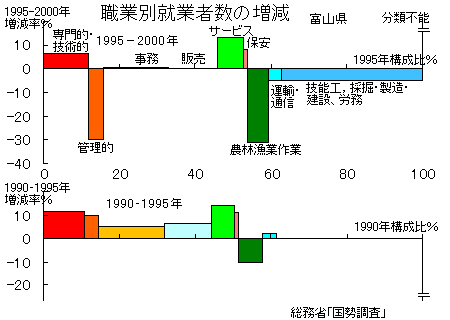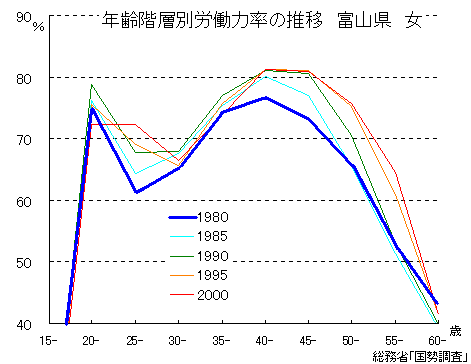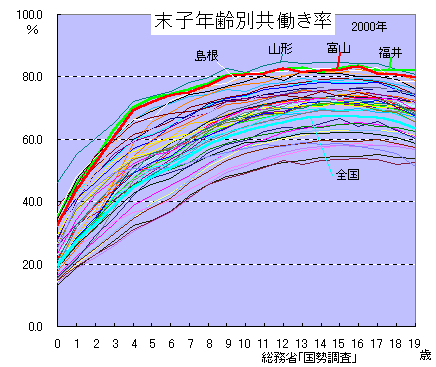|
職業別就業者数の変化
前回は、経済構造の変化を産業別就業者数の変化で見
た。しかし、企業組織が大きく変化するもとで、産業分類の意味が次第にあいまいなものとなりつつある。
これを補完するものとして、職業別就業者数の変化の検討がある。
下図は、1990年代前後半各5年間における職業別就業者数の変化を前回利用した寄与度グラフで表したものである。
1990年代後半には、一般に言われている、長期的な職業構造の変化の方向が明確になってきたと捉えられよう。
技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者の減少については、中国等との競合の中での製造業の厳しい状況や公共工事の抑制の結果である。産業分類で
は、製造業、建設業の就業者数の減少に対応している。
管理的職業の減少については、厳しい景気動向の中での企業の組織改革の結果であるが、同時に情報システムの普及により、管理的職業の必要性が乏しくなり
つつあることを反映しており、長期的動向に沿うものである。
農林漁業作業者の減少は、高齢者の退出が大きいにも拘わらず、若年者の新規就業が伴わないためである。
一方、専門的・技術的職業の増加は、今後の経済活動が知的創造に向かっていることを示している。
サービス職業については、介護保険の導入により、ホームヘルパー、介護職の増加が著しかったものと考えられ、今後とも増加していくであろう。
以上のような変化を別の角度から見ると、管理的職業は大部分を男が占めており、また技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者の太宗も男であるた
め、これまで主として男が担っていた職業が大きく減少している。これに対して、サービス職業は女がより多く占めており、この点では主として女が担ってきた
職業が増えていると言える。
また、専門的・技術的職業及びサービス職業のみの増加は、潜在的には、所得の両極化、格差の拡大が予想される変化である。
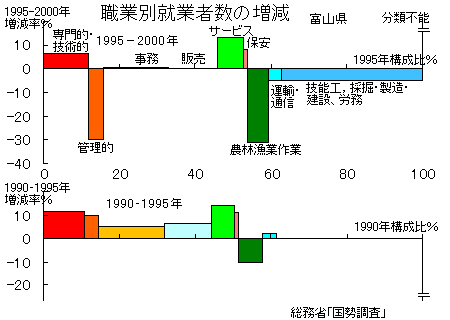
ところで、この職業別就業者数の統計は、本年6月末に富山県分が公表されたが、平成12年10月の調査から20ヶ月以上経過している。この状況に対処す
るため、約1年前に、国勢調査の調査票から1%の調査票を抽出して集計した結果が発表され、富山県の職業別就業者数も明らかにされていた。国勢調査は悉皆
調査であり、統計上の確率的誤差を懸念する必要はないのだが、この抽出調査では、配慮する必要がある。
実は、専門的技術的職業就業者数が5年前に比較して5.6%減少と全国で例のない結果がでていた。実際に増減がなくても、このような結果は確率的には
10%以上起こる可能性があり、悉皆集計の結果を待っていたところ、実際には、6.4%増となっていた。
この場合1%抽出の結果は、およそ400回に1回程度起こるまれな結果となるが、これをどう考えておけばいいのか。翻って考えてみれば、1%抽出集計の
結果を幾つも並べて検討しており、そのうちの一つに管理的職業従事者の減少があったと捉えればそれほど不思議な現象ではないとも言える。
国勢調査では本論ではないのだが、統計を扱う人には、このような確率の課題を常に念頭に置いていて欲しい。ここで実例として説明した確率については、高
校の数学にある初歩の確率論で計算式は求められる。しかし計算するのは大変な作業となり、実際に求める人はあ
まりいないようだ。ただし、今日のパソコンを使い、計算順序を工夫して途中で値が発散したり、消滅したりしないようにすれば、求めることができる。
女の年齢階層別就業率
富山県民の就業状況で、特徴としてあげられるのは、女の就業率が高いことである。
女の就業率は年齢階層によって大きく異なるが、この年齢階層別就業率は一般にM字カーブと呼ばれている。
ただし、このM字カーブも次第に変形しつつあり、富山県では、この中窪みが近いうちに消滅するようにも見られる。
下図は、このM字カーブの経年変化を一図に重ねて表したものである。
このグラフ自体の表現が成功しているかどうかは異論があるかもしれないが、このようなアニメーション・グラフもフリー・ソフトを使って容易に描けること
を知っておいて欲しい。
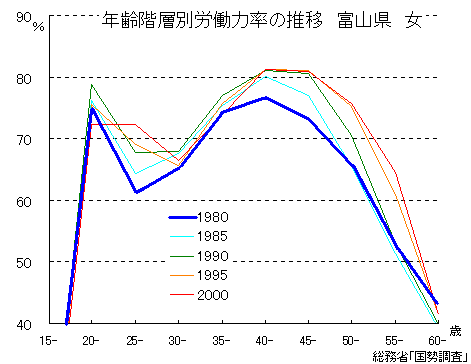
女の年齢別就業率がM字カーブを描くのは、出産・育児の過程で、一旦、職を離れるためであるが、実際に、末子の年齢別に夫婦の共働き率の推移を見ると、
この様子がよく分かる。
下図は、全国及び47都道府県の末子年齢別夫婦共働き率を描いたものである。
富山県のこのカーブの特徴として、末子が4歳までに急上昇し、そこで上昇が一段落し、カーブが明確に折れ曲がっている。これは、共働きを考えている夫婦
の多くは、末子が保育所なり幼稚園なりに通い始めると同時に、共働きを始めていることを意味している。
また、共働き率の高い県としては、富山とともに山形、福井、島根等が並ぶが、これらの県はいずれも拡大家族(非核家族)世帯の割合が高く世帯の規模が大
きい県である。これは、夫婦がその親から子育ての支援を受けていることが推測される。
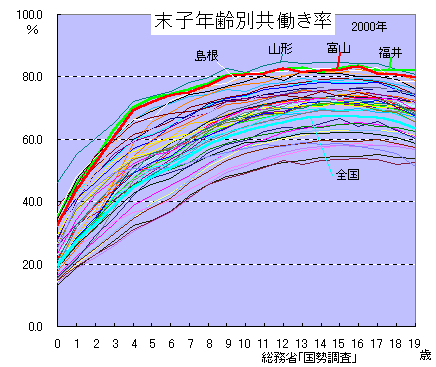
6回にわたって、「国勢調査からのメッセージ」と称し、平成12年国勢調査結果の興味深い内容を紹介するとともに、併せて、今日的な統計手法について解
説してきました。
二兎を追い、焦点が定まらず、分かり難いものとなってしまった面もありますが、読者諸賢の参考になれば幸いです。
|
![]()