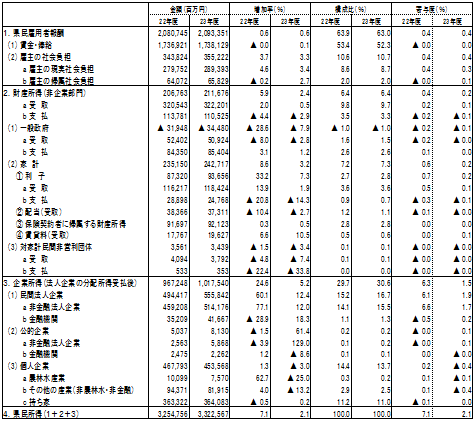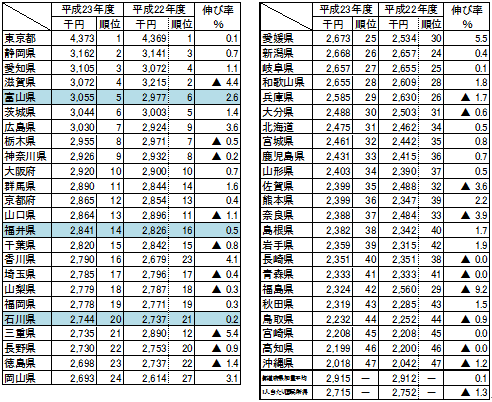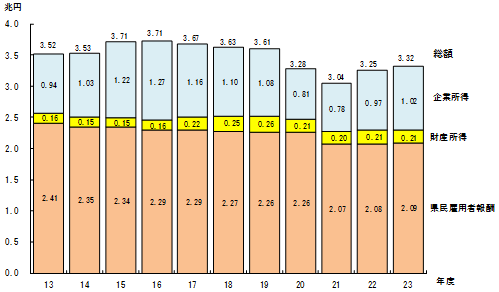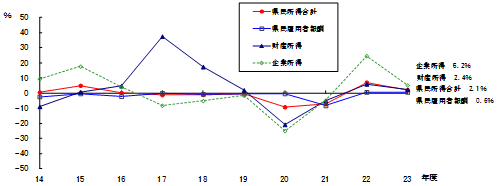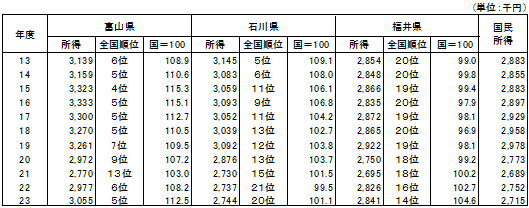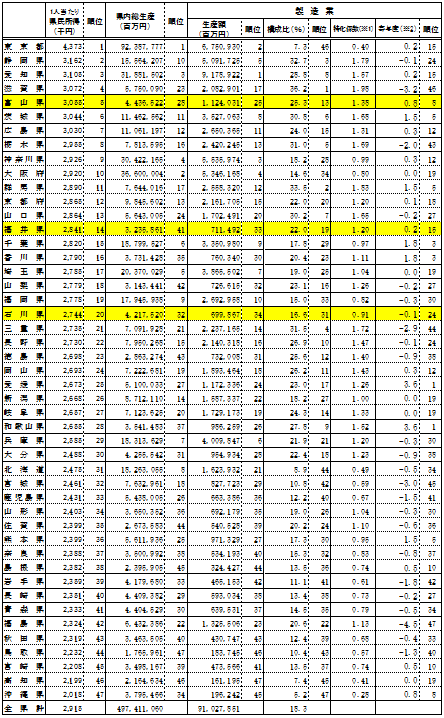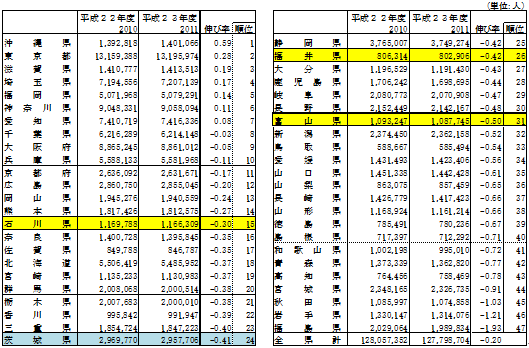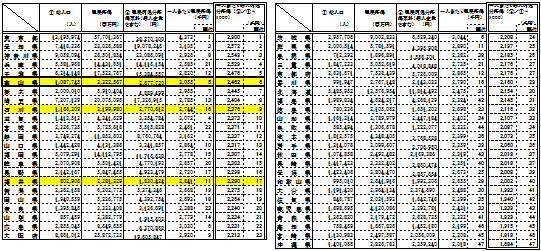平成23年度富山県民経済計算推計結果にみる「1人当たり県民所得」統計調査課 老田 靖男 |
|
|
1 はじめに富山県では、平成26年2月に平成23年度の富山県民経済計算の推計結果を公表しました。また、平成26年6月に各都道府県の推計結果をとりまとめた「平成23年度の県民経済計算について」が内閣府から公表され、新聞等で報道されましたが、その内容は概ね次のようなものでした。
平成23年度の富山県経済の概況については、平成26年5月に掲載した「平成23年度富山県民経済計算推計結果について」において既に紹介しておりますが(富山県の県内総生産は、名目4兆4,365億円、実質4兆7,712億円となり、対前年度経済成長率は、名目2.2%増、実質4.0%増と、名目・実質ともに2年連続でプラス成長となりました)、今回はその中でも特に「1人当たり県民所得」に注目し、その定義や意味について説明するとともに、平成23年度の富山県の県民所得の概要や、国・他県との比較、富山県の産業構造との関係なども併せてご紹介したいと思います。 |
2 「1人当たり県民所得」とは「1人当たり県民所得」は県民経済計算で推計されており、地域間の所得格差を計る代表的な指標とされ、都道府県間の所得水準を比較する際に用いられる場合が多いのですが、前記のような報道がなされるたび「富山県民の所得はなぜそんなに高いのか」、「富山県は所得が高いイメージがないのに、なぜ全国順位が5位〜10位といつも上位なのか」という問合せをよく受けます。 「1人当たり県民所得」という言葉は、新聞等のマスコミ報道でよく耳にされると思いますが、県民の皆さんは「県民所得」という名称から、これを「個人給与や個人所得の平均である」と誤解される場合が多いようです。 「1人当たり県民所得」は、県民所得を県の総人口で割って求めるものですが、この県民所得には、賃金・給与等の「県民雇用者報酬」だけではなく、金融資産からの利子・配当などの「財産所得」や「企業所得」も含まれており、「個人の給与(賃金)」や「所得水準」を示すものではありません。 また、総人口には、就業者だけでなく生産活動に従事していない高齢者や子供、失業者なども含まれていますので、単純に個人所得と比較しても意味がありません。 つまり、「1人当たり県民所得」とは、「個人の所得水準(家計の所得)」ではなく、「経済的な豊かさ(各都道府県の経済力)」を示すイメージに近いと思います。 計算の都合上、「1人当たり県民所得」は、県民所得が多く人口の少ない県(人口が減少傾向にある県)で大きくなり、県民所得が少なく人口の多い県(人口が増加傾向にある県)で小さくなります。また、「1人当たり県民所得」には、企業所得が含まれるため、全産業に占める製造業の比率が高いいわゆる「工業県」では「1人当たり県民所得」は大きくなる傾向があり、高齢者や子供の人口比率が大きく就業者の少ない都道府県では「1人当たり県民所得」は小さくなる傾向があることにも注意が必要です。 |
3 富山県の「県民所得」、「1人当たり県民所得」の概要それでは次に、平成23年度の富山県の「県民所得」と「1人当たり県民所得」の概要について説明したいと思います。
上位5県は、東京都、静岡県、愛知県、滋賀県、富山県の順となっており、この5県の「1人当たり県民所得」の平均額は3,353千円となっています。一方、下位5県の平均額は2,195千円となっており、上位5県とは1,158千円の格差がみられます。 1位の東京都の「1人当たり県(都)民所得」が4,373千円と突出して高いですが、これは東京都民の所得水準の高さのみを反映しているわけではありません。 東京都の「1人当たり県(都)民所得」が高い要因の1つには、東京都には企業が多数集中しており企業所得が大きいことや、周辺県から通勤している就業者が多いことがあげられると思います。この人たちが生み出した付加価値のうち企業内留保分は東京都の都民所得に計上されますが(属地主義)、雇用者報酬(賃金・給与)は、就業者が居住している周辺県の県民所得となります(属人主義)。 「1人当たり県(都)民所得」を計算する際の割り算の分母は東京都の人口なので、周辺県から通勤している就業者は計算から除外されることになります。つまり、企業が多く、多くの就業者が周辺県から集まり生産活動を行う東京都の場合は、必然的に「1人当たり県(都)民所得」が高くなるわけです。 また、東京都は地方と比べると物価が非常に高いことも考えると、東京都の「1人当たり県(都)民所得」は見かけほどは高くないと考えることもできます。 2位以下の静岡県、愛知県、滋賀県の場合は、いずれも工業出荷額規模の大きな地域(いわゆる工業県)であり、特に民間法人企業所得が高いことが、常に「1人当たり県民所得」が全国上位に位置している主な要因としてあげられるかと思います。 次に、今回5位となった富山県の「1人当たり県民所得」の概要について見てみたいと思います。富山県の県民所得金額と構成の推移(平成13年度以降)を表したものが図1、県民所得伸び率(名目)の推移(平成14年度以降)を表したものが図2です。 図1、図2を見ると、富山県は平成20年度、平成21年度と県民所得金額が企業所得で大きく落ち込んでいるのが分かります。これは、平成20年9月のリーマンショックが富山県の製造業(主に電気機械、化学、一般機械、金属製品など)に大きな影響を与えたことが主な要因と思われます。その後、富山県では平成22年度から23年度にかけて製造業を中心に経済状況が大幅に回復したため、企業所得は増加傾向にあるものの、県民所得の金額全体でみると、まだリーマンショック前(平成19年度)の水準までは回復していないことが分かります。 次に、北陸3県の「1人当たり県民所得」の推移(平成13年度以降)を見てみたいと思います。(表3参照) 富山県の場合は、リーマンショックの影響を受けた平成20年度の9位、平成21年度の13位を除くと、この10年間は概ね300万円前後で全国順位も4位〜7位と高水準で推移しており、国の水準を上回り北陸3県では最も高い順位となっています。なお、石川県、福井県は全国中位となっています。 それでは、富山県の場合はなぜ「1人当たり県民所得」の全国順位が上位に位置しているのでしょうか。その主な要因としては、富山県の産業構造と人口の減少があげられるのではないかと思います。 まず、産業構造についてですが、「1人当たり県民所得」が高い地域は、前記のとおり製造業の比率が高い「工業県」に多い傾向にあります。これは、製造業はサービス業などと比べると「労働生産性」が高い産業であり、就業者1人当たりの生産額が大きい産業だからです。「労働生産性」とは「就業者1人が産み出す付加価値」を意味し、その付加価値が大きい程、労働生産性は高いということになります。 つまり、製造業は生産技術や資本装備率が高く、設備投資を一度行えば、その後は少人数で大量生産することが可能であるのに対し、サービス業の場合はマンパワーによるところが大きく、1人当たりの生産量には限界があります。従って、製造業の方がサービス業よりも「労働生産性」が高い産業であるということが言えるかと思います。 それでは、富山県の全産業に占める製造業の割合はどのくらいなのか、平成23年度の値について他の都道府県と比較しながら見てみたいと思います。(表4参照)
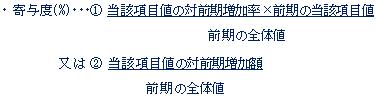
この表をみると、平成23年度の富山県の県内総生産に占める製造業の比率は25.3%と北陸3県では最も高く(石川県は16.6%、福井県は22.0%)、全国的にみても高い水準にあることが分かります。従って、富山県の場合も、労働生産性の高い製造業の比率が高い「ものづくり県」であることが「1人当たり県民所得」を引き上げ、全国上位に位置している主な要因であると言えるのではないかと思います。 しかし、県内総生産に占める製造業の比率の平成23年度の富山県の全国順位は13位であり、「1人当たり県民所得」が5位という結果は少し高すぎるような気もします。 富山県の製造業の比率は、30%を超えていた時期もあったのですが、近年は第3次産業の比率が6割強と高まってきており、製造業の比率は減少傾向にあります。 そこで、平成23年度県民経済計算の結果から、本県の主力産業である製造業のうち主な産業の状況(構成比・成長率等)について見てみたいと思います。(表5参照) 【表5 平成23年度県民経済計算結果における製造業の主な概要 】
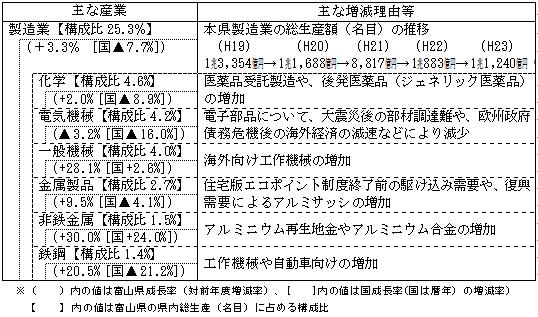 この表から、平成23年度の富山県の製造業は、電気機械は増加率がやや減少したものの、構成比の高い化学や一般機械を中心に、金属製品、非鉄金属、鉄鋼など他の産業では全体的に業績が好調であったことが分かります。 富山県の製造業の比率は全国的には高い方ですが、サービス業などの第3次産業の構成比66.2%(平成23年度)と比べると、その割合は25.3%にすぎません。 このように、県産業全体でみれば製造業の構成比は3割弱であるにもかかわらず、平成23年度の富山県の製造業の寄与度は0.8%と全国8位であり(表5参照)、平成23年度の富山県の経済成長率(名目)2.2%増のうち0.8%を製造業が占めており、富山県全体の成長率を押し上げています。つまり、富山県では製造業の増減が全体の成長率に大きく影響しているのです。 次に、富山県の人口の減少が「1人当たり県民所得」に与える影響について考えてみたいと思います。 急速な人口減少は、国や社会の存立基盤にかかわる問題であり、富山県は全国より早いペースで少子高齢化が進展していることもあり、今後ますます人口の減少が避けられない状況となってきています。表6は平成23年度の各都道府県別の人口増加率を表したものですが、これを見るとほとんどの県で人口が減少傾向にあることが分かります。 今回、富山県は「1人当たり県民所得」が5位となり、茨城県(6位)を上回りましたが(前回:茨城県5位、富山県6位)、この順位変動を「人口増加率」(表6参照)と「企業所得」、「財産所得」、「県民雇用者報酬」の増加率(※)の関係から考えてみたいと思います。 まず、「人口増加率」を見ると、富山県は平成23年度の人口増加率が-0.50%(全国31位)であるのに対し、茨城県は-0.41%(同24位)となっており、富山県の方が茨城県よりも人口の減少が進んでいることが分かります。 次に、「企業所得」を見ると、富山県が対前年度増加率+5.2%(民間法人企業では+12.4%)と高い伸びを示したのに対し(寄与度+1.5%)、茨城県では東日本大震災による発電所被災の影響などで、+3.1%の増加(同+7.6%)であり(寄与度+1.0%)、富山県の方が企業所得の増加率は高くなっています。 また、「財産所得」では、富山県が対前年度増加率+2.6%(寄与度+0.2%)、茨城県は+2.3%(寄与度+0.1%)であり、富山県の方が増加率は高いものの、あまり大きな差はありませんでした。 一方、県民所得に占める割合が最も大きい「県民雇用者報酬」では、富山県が対前年度増加率+0.6%(寄与度+0.4%)であるのに対し、茨城県では−0.3%(寄与度-0.2%)となっており、やはり富山県の方が増加率は高くなっています。 この結果、人口増加率では富山県の方が下回った上に、企業所得、財産所得、県民雇用者報酬の全てにおいて、富山県の方が茨城県よりも増加率が高かったため、「1人当たり県民所得」の額は、富山県が茨城県を上回ったということが言えるかと思います。 しかし、富山県と茨城県の「1人当たり県民所得」の金額の差は僅か11千円しかなく(表2参照)、4位の滋賀県から7位の広島県までの差も42千円しかないことを考えると、各都道府県の総人口(計算の分母)の僅かな増減が、「1人当たり県民所得」の全国順位の変動に大きな影響を与えていることが分かります。
|
4 経済力・地域間格差を示す指標今回の公表結果では、「1人当たり県民所得」の地域間格差を示す変動係数が6年ぶりに僅かに拡大しました(平成18年度から平成22年度までは5年連続で変動係数は縮小していた)。変動係数とは、地域間の所得格差の大きさを示すものであり、変動係数の値が大きいほど地域間格差が大きいことを表しているので、今回の結果は格差が拡大したことを意味しています。 変動係数は、景気変動の動きと連動しており、景気の拡大期には格差拡大し、景気の後退期(平成20年のリーマンショックなど)には格差縮小する傾向にあります。 変動係数が拡大(格差が拡大)する主な要因としては、一般的には上位県の所得が増加(又は人口が減少)し、下位県の所得が減少(又は人口が増加)することが考えられますが、今回の場合は、リーマンショックによる景気の落ち込みから製造業を中心に全体的に景気が回復基調にあることを示しているものと思われます。 このように、「1人当たり県民所得」は、経済的な豊かさ(各都道府県の経済力)を示す指標であり、地域間格差を示す指標でもありますが、一方で、県の経済力を判断する際には、1人当たりの額ではなく総額によって比較することが重要であり、県の経済力(経済規模)を示す指標としての「県内総生産(GDP)」にもっと注目すべきだとする考え方も提唱されています。 つまり、各県の経済力は県内総生産の水準によって比較されるべきであり、GDPに占める各県のシェアが上昇していれば経済力は向上しており、低下していれば経済力は低下していると判断することができるという考え方です。ちなみに、富山県の平成23年度の対全国GDPシェアは0.94%となっており、北陸3県では最も高くなっています(石川県は0.89%、福井県は0.68%)。 この「経済力を総額により判断すべき」という考え方は、世界経済を考えるとより分かりやすく、「1人当たりGDP」で国際比較すると、ノルウェーやスイスなどのヨーロッパの小国が上位になることが多いのですが、ノルウェーやスイスを世界の経済大国と考える人はほとんどいないと思います(日本は10位前後)。 一方で、中国のGDPは2010年に日本を上回り、アメリカに次いで世界第2位の経済大国となりましたが、中国の人口は日本の10倍以上ですから、「1人当たりGDP」で見るとまだまだ低水準となっています。しかしながら、それでも中国が世界の経済大国になったという現実には変わりはありません。 また、国際的にみると、日本のように「1人当たり県民所得」を地域格差の代表的な指標としてとらえるのは例外的であり、国連のマニュアルでは地域の経済的な豊かさを測る地域指標として「1人当たり個人(家計)可処分所得(※)」を用いることを提案しています。実際、アメリカやイギリスなどほとんどの国は個人所得で地域格差を比較しています。つまり、「地域の経済的な豊かさ」は「1人当たり県民所得」で測るのではなく、地域住民の実際の所得によって評価すべきであるという考え方をとっているのです。
表7は、平成23年度の都道府県別「1人当たり個人(家計)可処分所得」の金額と全国順位を表したものです。これを見ると、「1人当たり県民所得」と「1人当たり個人(家計)可処分所得」の全国順位は必ずしも一致していないことが分かるかと思います。 ただし、富山県の場合は、「1人当たり個人(家計)可処分所得」も全国6位と上位であり(平成22年度は5位)、経済的に豊かな県であるということがこの結果によっても裏付けられていると思います。 また、1位の東京都と富山県の数値を比較した場合、「1人当たり県民所得」では1,318千円と大きな差があるのに対し、「1人当たり個人(家計)可処分所得」では438千円の差となっており、実際にはその格差はそれほど極端に大きくないことが分かるかと思います。 なお、県民経済計算の「1人当たり個人(家計)可処分所得」以外にも、各都道府県の「個人所得」や「家計の豊かさ」について比較可能な調査がありますので、参考まで紹介したいと思います。どのようなことを知りたいか、その用途に応じてこれらの調査結果を使い分けてみるのもよいのではないかと思います。 例えば、各県の「個人所得(給料)」を比較するのであれば、厚生労働省が実施している「毎月勤労統計調査(※1)」の結果を利用するのがよいのではないかと思います。また、「家計(世帯)の豊かさ」を比較するのであれば、総務省が実施している「家計調査(※2)」の結果を利用するのがよいのではないかと思います。 ちなみに家計調査の結果によると、富山市は「二人以上の世帯のうち勤労者世帯の可処分所得」が2年連続で全国1位(平成24年:531,325円、平成25年(速報値):522,883円)であり、家計(世帯)単位で見ても富山県は豊かな県であることが分かります。
|
5 おわりに平成23年度富山県民経済計算の推計結果について、5月号と9月号の2回にわたり掲載しましたが、今回は、特に注目される「1人当たり県民所得」に内容をしぼってご紹介いたしました。 「1人当たり県民所得」は確かに県の経済力を測る重要な指標の1つではありますが、その全国順位が上昇したからといって単純に喜ぶのではなく、様々な観点から他の都道府県と比較することで、その要因を分析し見極めることが重要です。 仮に全国順位が上昇したとしても、その主な要因が人口減少にあるのであれば手放しで喜ぶことはできませんし、逆に、全国順位が低下したとしても、人口増加が主な要因であればむしろ歓迎すべきことだからです。 冒頭でも申し上げたとおり、「1人当たり県民所得」は県民所得という名称から個人給与や個人所得の平均と誤解されがちですが、本稿をご覧になり、「1人当たり県民所得」の正しい定義や意味、富山県の産業構造等について、ある程度ご理解いただけたとしたら幸いに存じます。 最近の様々な経済指標を見ると、4月に実施された消費税率の5%から8%への引き上げといった懸念材料はあるものの、雇用情勢の改善は進んでおり、企業の設備投資も増加傾向にあるなど、アベノミクス効果で景気回復が進んでいることを感じさせるものが多くなっています。また、消費者物価は緩やかな上昇を続けており、賃金も上昇しているという報道もよく耳にされるかと思います。しかし、実際には名目賃金は上昇していても消費者物価の上昇に伴い実質賃金は低下しており、多くの人はまだまだ本格的に景気が回復したという実感を得られていないのではないでしょうか。 それを裏付けるかのように、7月22日の経済財政諮問会議では、消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要の反動と外需の伸び悩みが当初の想定よりも大きいと判断され、2014年度の実質GDP成長率の見通しが1.4%から1.2%に、2015年度は1.7%から1.4%に引き下げられました。 また、内閣府が8月13日に発表した2014年4‐6月期四半期別GDP速報(1次速報値)によると、GDP成長率は前期比1.7%減、年率では6.8%減となり、東日本大震災のあった2011年1‐3月期以来の大幅な落ち込みとなっています。 現在、統計調査課では平成24年度の県民経済計算の推計作業を行っています。 県民経済計算は、県の経済規模や産業構造などを総合的に捉えることができる大変高度で重要な経済指標です。この県民経済計算が、行政や企業、各種団体において、施策立案や経済活動など様々な分野でより一層有効活用されるよう、国の基準改正等にも適切に対応し工夫を重ねながら、今後とも推計精度の向上に努めていきたいと考えています。
|