![]()
地理情報システム (GIS)の活用(1)
-ビジネスでのGISの展開
富山大学人文学部助教授 大西宏治
近年、行政機関やビジネスシーンで地理情報システム(Geographic Information System: GIS)が活用されはじめています。GISとは簡単にいえば、コンピュータ上で地図と様々な地域情報を組み合わせ表示するシステムです。今回と次回の「経済指標の見方・使い方」では地理情報システム (GIS)が社会の中でどのように活用されているのか、特にビジネスと行政機関での活用について紹介します。そして、GISはこれからの社会に欠かすこと のできないツールであることを示したいと思います。
1.地理情報システム(GIS)とは?
(1)地理情報システム(GIS)の定義と例
そもそも地理情報システム(GIS)とはどのようなものなのでしょうか? 地域の地図データと地域に関する様々な空間データを組み合わせたシステムです (図1)。地図と地域のデータさえあれば、目的にかなった地図を表示できます(表示機能)。同じ地図上にいろいろなデータを重ね合わせて表示すること (オーバーレイ)で地域の様々な問題を浮かび上がらせることもできます。他にも地域を分析することもできます(分析機能)。また、特定の条件を持った地域 を検索する機能もありますし(検索機能)、地域の様々な情報をデータベースとして格納しておく機能もあります(データベース機能)。以上のようにGISに は、①表示機能、②分析機能、③検索機能、④データベース機能が備わっています。
出典:国土交通省国土計画局総務課国土情報整備室
http://www.nla.go.jp/keisei/gis/kaigi/index-j.html
図2はGISの表示機能を活用したものです。富山県の中に約1Km×約1Kmのメッシュ
を作成し、富山県内の人口分布を示しました
。富山市、高岡市に人口が集中している様子がよくわかります。人口データと富山県市町村やメッ シュの地図が用意されていれば、このように容易に人口分布図を描くことができます。
図3はGISの空間検索機能を活用した例です。GISソフトのArcView
を用いて、富山市内の保育園の分布
と保育園から750mを半径とした円を描いた図です
。15分ぐらい、子連れで歩くこと のできる距離はおよそ750m程度でしょうか。そうすると、徒歩で送迎できる居住地は円で覆われた地域だとわかります。
このように、地図と地域のデータさえあれば、GISを用いて様々な検索、分析、表示を行えることをわかっていただけたのではない でしょうか。
(2)阪神・淡路大震災で有名になったGIS
日本で地理情報システムの知名度が上がったのは阪神・淡路大震災の復興活動のときです。震災の復興作業の際、どの道路が寸断され、どの道路が通行可能な のかの情報がなく、支援活動に支障が生じていました。そこで、震災による被害状況を実地調査し、道路の不通箇所やがれきの状態をGISに入力し、数多くの 人たちで情報を共有し、復興に活かしました。
道路やがれきの情報を単なるデジタル画像としての地図に表示するのではなく、GISに入力したことで、ライフラインの復旧やがれきの撤去作業に大きな威 力を発揮しました。たとえば、がれき撤去作業を住民の申請順に無秩序に行っては効率が悪く、最悪の場合、道路不通箇所を逆に多く作り出してしまう可能性が あります。そこで、GISを用いて撤去作業を行う地区をとりまとめ、作業を実施したところ、がれき撤去や復旧作業が効率よくできました(図1参照)。そし て、GISのデータを更新することで復旧計画を日々、再検討することができました(舟木,2000)。
このようにGISは単にコンピュータ上の画像としての地図であるだけではなく、背後に地域のデータをデータベースとして持っていることで多様な活用が可 能となるのです。
2.GISのビジネスでの活用の可能性
(1)日本マクドナルドの多店舗展開で活躍したGIS
数年前、日本マクドナルドはハンバーガーの平日半額を実施し、店舗数を大幅に増やしました。1994年末には1,481店だったのですが、2000年末 には3,598店になっています。現在でこそ平日半額は終わり、店舗数も減少させていますが、なぜ日本マクドナルドは一気に店舗数を増加させることができ たのでしょうか? その裏側にはGISを活用したマーケティングがあったのです(山口,2001)。
①ハンバーガーを買いそうな顧客層が昼間、夜間、それぞれどこにいるのか? ②他の競合しそうな外食産業の立地がどのようになっているのか? ③徒歩や 自動車の通行量はどのようになっているのか? など、集客に関連する様々なデータをGISへ入力し、採算がとれそうな立地点やマクドナルドの空白地を GISで探しだし、新たな立地点を決めるようになりました。その結果、出店調査の調査員を増やすことなく出店調査にかかる時間を大幅に圧縮することに成功 し、一度に数多くの店舗を出店することができました(図4)。
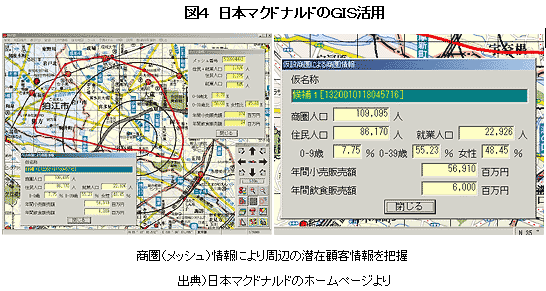
平日半額だけでハンバーガーの売り上げを伸ばしたのではなく、ハンバーガーを買いそうな人のそばに 数多くの店舗を出すこともマクドナルドの売り上げを伸 ばした重要な要因だったのです。そして、急速な店舗数の増加にはGISが大きな役割を果たしたのです。マクドナルドが使ったGISがどのようなものなの か、ホームページで紹介されていますので、文章だけでイメージがつかめなかった方は是非ご覧ください 。
(2)新聞の折り込み広告の範囲をGISから考える
スーパーなどの新聞の折り込み広告はむやみやたらと配布する範囲を広げても効果はあまり得られないといわれています。では、どのように折り込み広告を配 布する範囲を確定すればよいのでしょうか? 新聞店の販売地域とスーパーの商圏を重ね合わせ、折り込み広告を入れる地域を考える必要があります。そのた め、新聞店のデータやどのような人がそれぞれの地域に暮らしているかという居住者の属性、スーパーの商圏などをGISで重ね合わせ、折り込み広告を入れる 範囲を確定することをビジネスとしている企業がいくつも現れています(図5)。
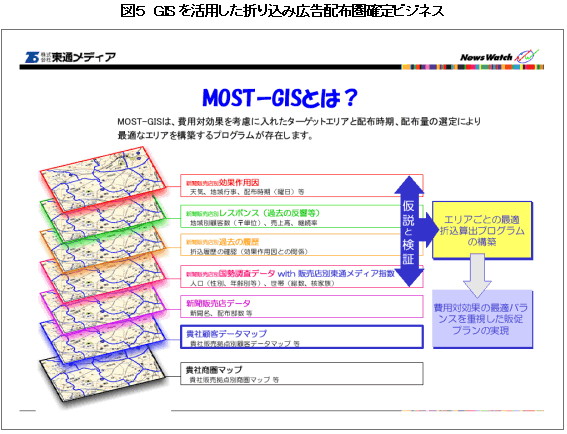
出典 : (株)東通ネット http://www.totsumedia.co.jp/
また、最近、ICチップ入りのカードを会員カードとして発行し、スーパーで会員割引を行うところが増えています。会員になるには 住所の情報が必要とされる場合がほとんどだと思います。そのようなサービスをするスーパーの中には、ICチップに記録された会員情報を元に、来客者の分布 を把握し、マーケティングに活かしている場合があります。
今やマーケティングや顧客管理など、様々なビジネスシーンでGISは欠かせないツールとなっています。
3.犯罪空間の検出とGIS
昨年(平成15年)の夏、東京(警視庁)や大阪(大阪県警)が犯罪マップをインターネット上で公開し、話題になったことをご記憶の方もいらっしゃるかと 思います。これらの犯罪マップの作成にもGISは重要な役割を果たしています(図6)。
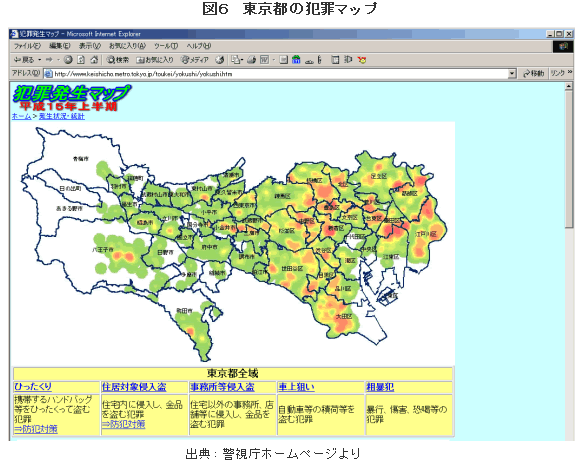
犯罪マップ作成の目的は、犯罪の予防を行うことです。たとえば、ひったくりが多発している地域があれば、その地域がどこであるの かを示し、人々に知らせ ることにより、犯罪に巻き込まれないような注意を喚起するというねらいがあるのです。
また、犯罪の起きた分布のパターンから、車上ねらいが起こりやすい地理的条件や空き巣が発生しやすい地理的条件、ひったくりが起こりやすい地理的条件な どをとらえようという研究も行われています。
警視庁犯罪マップ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/toukei/yokushi/yokushi.htm
大阪府警犯罪マップhttp://www.map.police.pref.osaka.jp/Public/index.html
4.GISをより普及させるために
社会の様々な場面でGISが活用されつつあります。社会の情報の8割は空間的な要素を含んでいるといわれており、それらの情報を円滑に活用しようと考え るとGISはこれからの社会に欠くことのできないツールです。実際、ビジネスや社会活動に活用されています。
かつて、GISはシステムもデータも高価で、一般の人たちが購入し利用することは困難でした。しかし、価格も下がり、GISのフリーソフト(無料のソフ ト)が登場したり、地図データも無料で公開
されたりするようになりました。しかし、GISというものが存在していること、それが社会の中でどのように活用されているのかということについて多くの人 は全く知識を持っていません。
今後、GISの利用者たちは一般の人たちがGISを活用してくれるよう、様々な啓蒙普及活動をしていく必要があると思います。 旅の記録やウォーキングコースを計画するような簡単なGISソフトウエアがあります。興味を持った方は活用してみてはいかがでしょうか。
また、学校教育でもGISを取り上げてほしいと思います。ワープロや表計算ソフトの活用方法を学んだ次に必要な情報リテラシーはGISではないでしょう か。GISを自由に使いこなせるようになった子どもたちが大人になるとき、地図の上に現代社会を分析し、具体的なまちづくりの提案をできるような人材とな るのではないかと思います。
余談ですが、2004年のNHKスペシャル「63億人の地図」(9回シリーズ)はGISをふんだんに活用したテレビ番組ですので楽しみです(http://www.nhk.or.jp/datamap/)。
今回は、GISとはどのようなものなのか、そして、ビジネスでどのように活用されているのかについて紹介してきました。次回ですが、現在、総務省や国土交通省により全国の都道府 県、市町村の業務へGISを活用できるように、様々な取り組みが行われています。そこで、都道府県や市町村でどのようにGISが活用されているのか、先進 的な都道府県や市町村の例を取り上げ、紹介していきたいと思っています。
参考文献
舟木春仁(2000):『GIS 電子地図ビジネス入門』東洋経済新報社
山口廣太(2001):『マクドナルドのIT戦略』経林書房
1) 2万5千分の1の地形図を縦横10等分したものを基準メッシュと呼ぶ。図1には基準メッシュに情報を載せ、人口を表示した。
2)平成7年国勢調査のデータを利用。
3) ESRI社製のGISソフトウエア。Arc ViewのGISソフトウエアのシェアは世界1位だといわれている。
4) データの都合から1990年現在の保育園の分布を示している。
5) このような円を描く空間検索をバッファリングという。
6)マクドナルドの利用したGISに関するホームページはhttp://www.mcdonalds.co.jp/guidance/business_h_f.html
7) たとえば、MANDARAがあげられる(http://www5c.biglobe.ne.jp/~mandara/)。 利用方法の簡単なマニュアルは大西のホームページにある(http://www.hmt.toyama-u.ac.jp/geog/ohnishi/index.html)。
8) 国土数値情報(http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/)や
国土情報ウェブマッピングシステム http://w3land.mlit.go.jp/WebGIS/)が 無料で公開されている。