![]()
農林水産業は、食料や木材の供給だけでなく、国土の保全や水源のかん養等をはじめとした多面的機能の発揮といった、県民生活及び県民経済の安定にとって重要な役割を果たしている。
≪農業≫
本県の農業は、古くから米を主体に発展しており、全国屈指の水田率(96.1%:平成13年)、ほ場整備率(80.5%:平成13年度末)となっている。現在では農業粗生産額の7割余りを占める米を中心に、野菜、花き、畜産などが行われている。また、組織化の進展や農業機械の普及に伴い、稲作の省力化が進む一方、販売農家37,550戸(平成14年)のうち、兼業農家が92.6%を占め、兼業農家率は全国2位となっている。
農家所得は、約674万円(平成13年)と比較的高いものの、このうち、農業所得は約34万円(平成13年)で、全体的に農外所得に依存した農家経済になっている。
こうした状況の中、国では平成11年に「食料・農業・農村基本法」を制定した。平成13年には本県においても、21世紀初頭における農業の持続的発展と活力ある農村づくりを目指す長期計画「富山県農業・農村新世紀プラン」を策定し、(1)食をささえる産業としての農業の展開、(2)将来にわたって持続できる農業構造の確立,(3)県民の生活空間として、住みやすく活力のある農村の創造の3つの基本方向に基づき、「食と生活をささえる農業・農村」を目指した施策を展開している。
専兼別農家戸数の推移
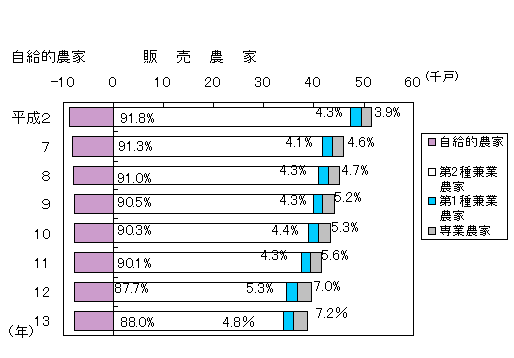
資料出所 富山県統計調査課
資料 北陸農政局富山統計情報事務所「富山農林水産統計年報」
農林水産省「農林業センサス」
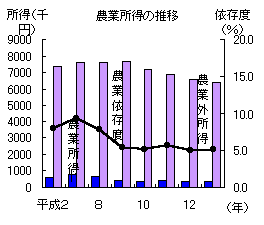
≪林業≫
森林は木材生産機能から水源のかん養、国土や自然環境の保全、地球温暖化の防止、保健・文化・教育の場としての利用等多面的な機能を有している。
また、本県の林業は、林業労働力の減少・高齢化、林業経営費の増大、木材価格の低迷など困難な状況に直面している。
こうした状況に対応するため、森林の適正な整備と保全を図るとともに、県産材供給体制を整備するため、高性能林業機械の導入や林道網の整備、担い手の育成・確保、林業事業体の育成などの取り組みが展開されている。
≪水産業≫
富山湾は、対馬暖流及び日本海固有冷水が沿岸まで接近し、沿岸から沖合に向かって一気に深まる海底谷が複雑な地形をつくり好漁場を形成していることから、定置網漁業を主体とした沿岸漁業が盛んである。しかし、漁業経営は生産者価格の低迷や水産資源の減少等により厳しい環境にあり、適切な資源管理とつくり育てる漁業の推進を目指した取り組みが展開されている