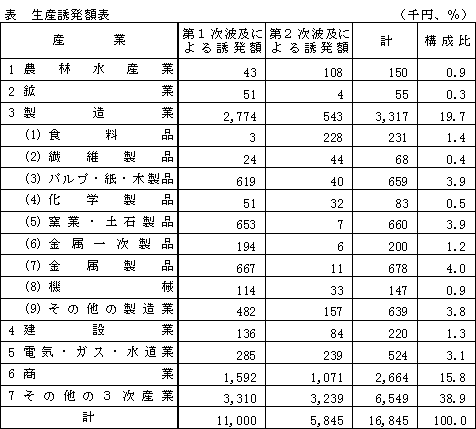(1) 経済的波及効果の把握と産業連関表の意義
こうした波及効果の大きさはどの程度の大きさになるのだろうか。産業連関表を用いれば容易に数量的把握をすることができる。
(2) 住宅新築による波及効果の計測
いま2,000万円の住宅を新築したと仮定すると、県内にはその2,000万円にプラスして1,199万3千円の生産が誘発される。前提条件は次のとおりである。
①住宅敷地は購入済。2,000万円はすべて工事費とする。
②住宅は木造。
③工事費2,000万の内訳
建築工事費1,647万円給排水工事費112万円
電気工事費60万円円
請負会社諸経費181万円
(3) 波及効果の分類
第一次(間接)波及効果…工事請負業者の資材需要により建築資材関連部門が受ける波及効果にそれ以降の究極的効果を含めたもの。
第二次(間接)波及効果…直接効果と第一次波及効果によって生み出された雇用者所得のうち消費にあてられた分が新たに生み出す効果。
図1は一次波及の過程を示したものである。
木工事では、そこに必要な木材の需要(462万円)が、県内の材木屋、製材業者、林業者それに電気・ガス等の業者に次々と226万円(76万円+118万円+7万円+25万円)の生産を誘発することを示している。さらに波及の連鎖は林業の生産のために運送業が必要とされ、そのために軽油やガソリンが発注され原油の精製業者が増産するというように、次第に影響は小さくなりながら続いていく。
このような波及の過程は、建築工事の各工種ごとにくり返し行われ、様々な業種に生産を誘発する。
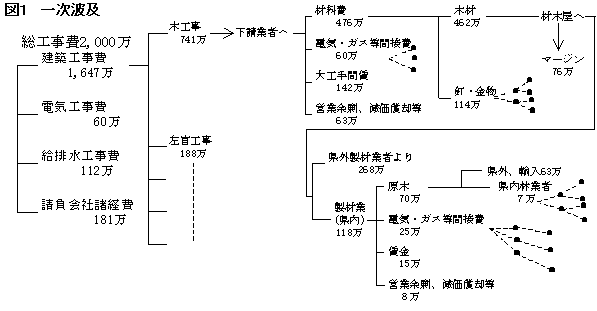
次に図2は同様に二次波及の過程を示したものである。直接効果と一次波及から生じた雇用者所得(575万円)のうち消費支出に向けられた分(375万円)は次々と需要を発生し、一次波及と同様の連鎖を生じる。
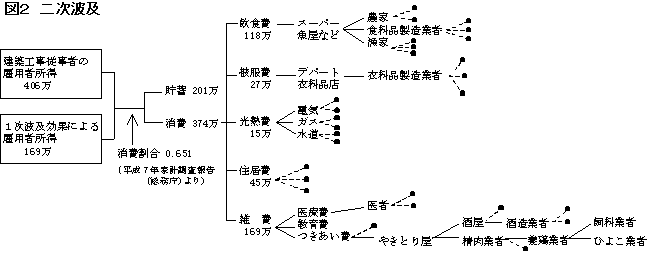
(4) 波及の結果
一次及び二次の波及効果によって県内に誘発される生産額を産業ごとにみると、表のとおりになる。誘発額は一般に、二次波及分が一次波及分より小さなものとなるが、農林水産業、食料品製造業では逆転している。これは二次波及が消費から派生するものであり、食品関係の需要のウェイトが高いことによる。例えば、大工さんがその賃金の一部でヤキトリ屋で一杯飲んだ場合の、酒造業者や精肉業者それに養鶏業者等の生産が含まれている。
また、次のことがいえる。
木材など建築資材の多くは県外からの移入によるものである。例えばウェイトの大きい木材・木製品の県内割合が高まれば高まる程、県内において誘発される生産額が多くなり、住宅投資が県内経済に与えるインパクトも強いものとなる。
仮に波及の過程で生じる需要がすべて県内業者に向けられるとすると、波及効果は319万円の増となる。
数量的に波及効果を求める方法として、波及の過程を一つひとつ積み上げて計算することも考えられるが、実際に計算することは非常に困難である。産業連関表は、この種の問題に対して容易に答を用意することができるほか、為替変動が物価に与える影響の分析など、様々な経済分析の有用な道具として用いられている。