�P
�@�����̖ړI
�H�Ɠ��v�����́A�H�Ƃ̎��Ԃ𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B
�Q
�@�����̍���
���v�@�i���a22�N�@����18���j
�Ɋ�Â��A�u�w�蓝�v�����v�i�w�蓝�v��10���j�ł���A�H�Ɠ��v�����K���i���a26�N�ʏ��Y�Əȗߑ�81���j�ɂ���Ď��{�����B
�R
�@�����̊���
����20�N�H�Ɠ��v�����́A����20�N12��31�������Ŏ��{�����B
�S
�@�����͈̔�
���{�W���Y�ƕ��ށi����21�N�����ȍ�����175���j�Ɍf����u�啪�ނd�|�����Ɓv�ɑ����鎖�Ə��i���ɑ����鎖�Ə��������j�ł���B������O,�R,�T�y�тW�N�ɂ��Ă͑S�����������{���A����ȊO�̔N�͏]�Ǝ҂S�l�ȏ�̎��Ə����̑ΏۂƂ��Ă����i����1981�N(���a56�N)�ȍ~�ł���A�x�R����1999�N(����11�N)�ȍ~�ł���j�B
����20�N�i2008�N�j
�͑S�������̔N�̂��߁A�]�Ǝ҂R�l�ȉ��̎��Ə��ɂ��Ă��ΏۂƂ��Ă���B
�T�@�����̕��@
�����P�ʂ͌X�̎��Ə��ł���A�H�Ɠ��v�������i�{�Јꊇ�����ɂ��Ă͌o�ώY�Ƒ�b�j���z�z���钲���[�ŁA�]�Ǝ�30�l�ȏ�̎��Ə��i�����A���H���͏C�����s���Ă��Ȃ��{
�Ж��͖{�X�������j�ɂ��Ắu�H�ƒ����[�b�v�A�]�Ǝ�29�l�ȉ��̎��Ə��i�����A���H���͏C�����s���Ă��Ȃ��{�Ж��͖{�X�������j�ɂ��Ắu�H�ƒ����[���v��p���A�\���ҁi���Ə��̊Ǘ���
�C�ҁi�{�Јꊇ�����ɂ��Ă͖{�Јꊇ������Ƃ��\����ҁj�j�̎��v�\���ɂ����{���Ă���B
�U�@�W�v���ڂ̐���
�@
(1)�@���Ə���
����20�N12��31�����݂̐��l�ł���B���Ə��Ƃ́A��ʓI�ɍH��A���쏊�A���������邢�͉��H���ȂǂƌĂ�Ă���悤
�ȁA������߂Ď�Ƃ��Đ������͉��H���s���Ă�����̂������i��ƒ����Ƃ͈قȂ�j�B
(2)�@�]�ƎҐ�
����20�N12��31�����݂̌l���Ǝ�A�����Ƒ��]�Ǝҋy�я�p�J���҂̍��v�ł���B�Վ��ٗp�҂͏����Ă���B
�A�@�l���Ǝ�
�y�і����Ƒ��]�Ǝ҂Ƃ́A�Ɩ��ɏ]�����Ă���l���Ǝ�Ƃ��̉Ƒ��Ŗ���V�ŏ펞�A
�Ƃ��Ă���҂������B�����Ɍg����Ă��Ȃ����Ǝ�Ƃ��̉Ƒ��Ŏ�`�����x�̂��̂͊܂܂Ȃ��B
�C�@��p�J���҂Ƃ́A���̂����ꂩ�̎҂������A�u���Ј��A���E�����v�A��p�[�g�E�A���o�C�g����y�Ѣ�o���E�h������ң�ɕ�������B
�@�@(�) ���Ԃ����߂��A����
�P����������Ԃ����߂Čق��Ă����
�@�@(�) ��
�X���͂P�����ȓ��̊��Ԃ������Čق��Ă����҂̂����A���̌��Ƃ��̑O���ɂ��ꂼ��18���ȏ�ق�ꂽ��
�@�@(�) �e��Ƃ���̏o���]
�ƎҁA�l�ޔh����Ђ���̔h���]�Ǝ҂Ȃǂŏ�L(�)�A(�)�ɊY�������
�@�@(�) �d���A�����Ȃ�
�̖�
���̂����A�펞�Ζ����Ė������^�̎x�������Ă����
�@(�) ��
�Ǝ�̉Ƒ��ł��̎��Ə��ɓ����Ă���҂̂����A�펞�Ζ����Ė������^�̎x�������Ă����
�E�@�Վ��ٗp��
�Ƃ́A��p�J���҈ȊO�̌ٗp�҂ŁA�P�����ȓ��̊��Ԃ��߂Čٗp����Ă���l����X
�ٗp����Ă���҂������B
(3)�@�������^���z
����20�N
�P�N�Ԃɏ�p�J���҂̂����ٗp�ҁi�u���Ј��A���E�����v�y�сu�p�[�g�E�A���o�C�g���v�������j�ɑ��Ďx�����ꂽ��{���A���蓖�y�ѓ��ʂɎx����ꂽ���^
�i�����ܗ^���j�̊z�Ƃ��̑��̋��^�z�Ƃ̍��v�ł���B
���̑��̋��^�z�Ƃ́A��p�J���҂̂����ٗp�҂�
����ސE�����͉��ٗ\���蓖�A�o���E�h������҂ɌW��x���z�A�Վ��ٗp�҂ɑ��鋋�^�A�o�������Ă���҂ɑ��镉�S�z�Ȃǂ������B
(4)�@���ޗ��g�p�z��
����20�N�P�N�Ԃɂ����錴�ޗ��g�p�z�A�R���g�p�z�A�d�͎g�p�z�A�ϑ����Y
��A�������Ɋ֘A����O����(*1) �y
�ѓ]���������i�̎d���z(*1)�̍��v�ł���A����Ŋz���܂z�ł���B
�A�@���ޗ��g
�p�z�Ƃ́A��v���ޗ��A�⏕�ޗ��A�w�������i�A�e��A��ޗ��A�H��ێ��p�̍ޗ��y��
���Օi���̎g�p�z�������A���ޗ��Ƃ��Ďg�p�����ΒY�A�Ζ������܂܂��B�܂��A�����H�ꓙ�Ɍ��ޗ����x�����Đ������H���s�킹���ꍇ�ɂ́A�x���������ޗ�
�̊z���܂܂��B
�C�@�d�͎g�p
�z�Ƃ́A�w�������d�͂̎g�p�z�������A���Ɣ��d�͊܂܂Ȃ��B
�E�@�ϑ����Y
��Ƃ́A���ޗ����͒��Ԑ��i�𑼂̎��Ə��Ɏx�����Đ������͉��H���ϑ������ꍇ�A����
�Ɏx���������H���y�юx�����ׂ����H���ł���B
�G�@��������
�֘A����O����Ƃ́A���Ə������i�u�����i�o�z�v�A�u���H�������z�v�A�y�сu���̑�����
�z�v�j�ɒ��ڊ֘A����O����ł���B
�I�@�]������
���i�̎d���z�Ƃ́A����20�N�P�N�ԂɎ��ۂɔ���グ���]���i�ɑΉ�����d���z�ł���B
(*1)�d����19�N
��������A�����ƈȊO�̊�����c������ړI�ŁA���ޗ��g�p�z����
�u�������Ɋ�
�A����O����v�A�u�]���������i�̎d���z�v�����ڂƂ��Ēlj�
������B
����āA����18�N�ȑO�̐��l�Ƃ͐ڑ����Ȃ��B
(5)�@�����i�o�z��
����20�N
�P�N�Ԃɂ����鐻���i�o�z�A���H�������z�y�т��̑������z(*2)�̍��v�ł���A����Ŋz�y�ѓ�������Ŋz���܂�
���z�ł���B
�A�@�����i��
�o
�ׂƂ́A���̎��Ə��̏��L�ɑ����錴�ޗ��ɂ���Đ������ꂽ����(���ޗ��𑼂Ɏx����
�Đ������������̂��܂�) ��20�N
���ɂ��̎��Ə�����o�ׂ����ꍇ�������B�܂��A���̂��̂������i�o�ׂɊ܂܂��B
(�) ��
���Ƃɑ����鑼
�̎��Ə��ֈ����n��������
(�) ���Ǝg�p����
������
�i���̎��Ə��ɂ����čŏI���i�Ƃ��Ďg�p���ꂽ���́j
�@ (�) ��
���̔��ɏo�������́i�̔��ς݂łȂ����̂��܂݁A����20�N���ɕԕi���ꂽ���̂������j
�C�@�����i�o
��
�z���́A�H��o���z�ɂ���Ă���B�������A���̂��̂͂��ꂼ��̉��z�ɂ���Ă�
��B
(�) ��
��ŋy�ѓ�������
�Łi��ŁA�����ŁA�������ŋy�ђn�����H�ł̔[�t�Ŋz���͔[�t���ׂ��Ŋz�̍��v�j���ۂ���ꂽ���̂́A���̐Ŋz���܂߂��H��o���z
�@�@(�) �������A�l����
����
�����̂́A���̕��������������H��o���i
�E�@���H����
��
�z�Ƃ́A����20�N���ɑ��̏��L�ɑ������v���ޗ��ɂ���Đ������A���邢�͑��̏��L
�ɑ����鐻�i���͔����i�ɉ��H�A�������������ꍇ�A����ɑ��Ď�������͎��ׂ����H���ł���B
�G�@���̑���
��
���z�Ƃ́A�①�ۊǗ��A�L�����A���Ɣ��d�̗]��d�͂̔̔������z�Ȃǂ������B
(*2)�d��
��19�N��������A�����ƈȊO��
������c������ړI�ŁA�����i�o�z����
�]�������܂߂�
�u���̑������z�v�����ڂɒlj����Ă���B����āA����
18�N�ȑO�̐��l�Ƃ͐ڑ����Ȃ��B
(6)�@�����i�A�����i�y�юd�|�i�A���ޗ��y�єR���̍Ɋz�i�]�Ǝ�30�l�ȏ�̎��Ə��j
���Ə��̏��L�ɑ�������̂뉿�z�ɂ���ċL���������̂ł���A���ޗ��𑼂Ɏx�����Đ��������ϑ����Y�i���܂܂��B
(7)�@�L�`�Œ莑�Y�̊z�i�]�Ǝ�30�l�ȏ�̎��Ə��j
����20�N�P�N�Ԃɂ����鐔�l�ł���A���뉿�z�ɂ���Ă���B
�A�@�L�`�Œ莑
�Y�̎擾�z���ɂ́A���̋敪������B
(�) �y
�n
(�) ��
���y�э\�z���i�y�ؐݔ��A�����������ݔ����܂ށj
(�) �@
�B�y�ё��u�i���ݔ����܂ށj
(�) �D
���A�ԗ��A�^����A�ϗp�N���P�N�ȏ�̍H��E���A���i��
�C�@���݉�����
�̑����z�Ƃ́A���̊���̎ؕ��ɉ�����ꂽ�z�ł���A�����z�Ƃ͂��̊��肩�瑼�̊�
��ɐU��ւ���ꂽ�z�������B
�E�@�L�`�Œ莑
�Y�̏����z�Ƃ́A�L�`�Œ莑�Y�̔��p�A�P���A�Ŏ��y�ѓ����Ƃɑ����鑼�̎��Ə��ւ̈����n�����̊z�������B
�@�@
�G�@�L�`�Œ莑�Y�z�̎Z���͈ȉ��̂Ƃ���B
(�) �L
�`�Œ莑�Y�N�����ݍ����N�����ݍ��{�擾�z�|���p�z�|�������p�z
���F�擾�z���y
�n�{�����y�э\�z���{�@�B�y�ё��u�{���̑����i��
(�) ��
�݉�����̔N�ԑ����������z�|�����z
(�) �L
�`�Œ莑�Y�������z���擾�z�{���݉�����̔N�ԑ����i�����z�|�����z�j
(8)�@���[�X�_��ɂ��_��z�y�юx���z�i�]
�Ǝ�30�l�ȏ�̎��Ə��j
��
�����g�p������Ԃ��P�N������ݎ،_��ŁA�_����Ԓ��͌����Ƃ��Ē��r���ł��Ȃ����̂ł���B�������A���[�X����ɌW���v
������ʏ�̔�������ɌW����@�ɏ����čs���Ă���ꍇ�́A�L�`�Œ莑�Y�̎擾�ƂȂ�B
�A�@���[�X�_
��z�Ƃ́A�V�K�Ɍ_�����[�X�̂�������20�N�P������12��
�܂łɃ��[�X�������[���A��
�u����Č������������A�����؎���t���������ɑ��郊�[�X�����̌_��z�������A����Ŋz���܂z�ł���B
(9)�@���Y�z�y�ѕt�����l�z�̎Z�o��
�e�X�A���̎Z���ɂ�
��Z�o������B
�@���Y�z�@�@�@�@�@30�l�ȏ�i�b�j�������i�o
�z���{(�����i�N���Ɋz�|�����i�N���Ɋz)
�@�A�t�����l�z�@�@�@30�l�ȏ�i�b�j�����Y�z�|���ޗ��g�p�z���|�������p�z�|��������Ŋz��
�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@29�l�ȉ��i���j�������i�o��
�z
���|���ޗ��g�p�z���|����
����Ŋz��
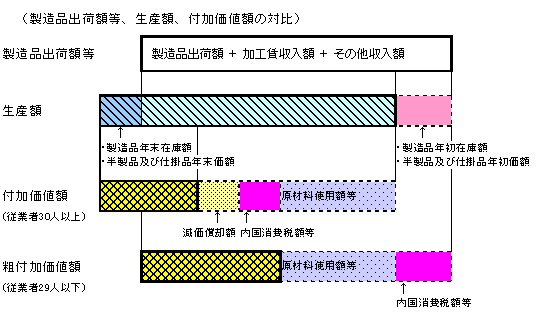
�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
��1 �]�Ǝ�29�l�ȉ��̎��Ə��͍ɂ̒��������Ă��Ȃ����߁A���Y�z���Z�o���Ă��Ȃ��B
��2 �]�Ǝ�29�l�ȉ��̎��Ə��ɂ��ẮA�����i�o�z���Y�z
�Ƃ݂Ȃ��A�������p
�z�����Ă��Ȃ����߁A�e�t�����l�z�Ƃ��ĎZ�o���Ă���B
��3�@��������Ŋz���́A��������Łi��ŁA�����ŁA�������ŋy�ђn�����H�Łj�̔[
�t�Ŋz���͔[�t���ׂ��Ŋz�y�ѐ��v����Ŋz�̍��v�ł���B
��4�@�u�����i�o�z���v�y�сu���ޗ��g�p�z���v�̒������ڒlj��ɂ��A���
�Y�z��y��
��t�����l�z��͕���18�N�ȑO�̐��l�Ƃ͐ڑ����Ȃ��B
(10)�@�H��p�n�i�]�Ǝ�30�l�ȏ�̎��Ə��j
�A
���Ə��~�n�ʐ�
����20�N12��31�����݁A���Ə����g�p�i�����܂ށj���Ă�
��~�n�̑S�ʐςł���B�������A��h�ɁA�O�����h�y�т��̑����������{�ݓ��Ɏg�p���Ă���~�n�ŁA���Y�ݔ��i�q�ɓ����܂ށj�Ȃǂ̕~�n�Ɠ��H�i�����j�A��
���Ȃǂɂ�薾�m�ɋ�ʂ����ꍇ�y�т����̕~�n�̖ʐς����炩�̕��@�ŋ�ʂł���ꍇ�͏����Ă���B�܂��A���Ə��̗אڒn�ɂ���g���\��n�����Ə���
��L���Ă���ꍇ�͊܂܂��B
�@ �C ���Ə����z�ʐ�
��L�̎��Ə��~�n�ʐϓ��ɂ��邷�ׂĂ̌��z���ʐς̍��v�������B�Ȃ��A����20�N12��31��
�����z���̂��̂ł����Ă��A����Ɍ��݉�����Ƃ��Čv�サ�����̂͊܂܂��B
�@ �E ���Ə������z�ʐ�
��L�̕~�n�ʐϓ��ɂ���S���z���̊e�K�ʐς̍��v�ł���B
(11)�@�H�Ɨp���i�]�Ǝ�30�l�ȏ�̎��Ə��j
�A �W ��
(�) �����ʗp����
a) ��������
�s���{�����͎s�����ɂ���Čo�c�����A�H�Ɨp�������͏㐅������搅������
b) �H�Ɨp���� ���p�ɓK���Ȃ��H�Ɨp�����������鐅���i�H�Ɨp�����j����搅������
c) ��ː�
���ˁA�[��˖��͗N������搅���鐅
d) ���̑��̒W�� ��L�̂�����ɂ������Ȃ��ŁA�u������v�ȊO�̂��́B�Ⴆ�A�͐�A�Ώ����͒����r����搅���鐅�i�n�\���j�y�щ͐�~�y�ы��͐�~
���ɂ����ďW��������ɂ���Ď搅���鐅�i�������j�A�_�Ɨp���H����搅���鐅�A���̎��Ə����狟���������ȂǁB
e) �����
���Ə����ň�x�g�p���������z���Ďg�p���Ă��鐅
(�) �p�r�ʗp����
a) �{�C���[�p�� �@�@�{�C���[���ŏ��C
�������邽�߂Ɏg�p���ꂽ��
b) �����p��
���i�̐����ߒ��ɂ����āA�����Ƃ��Ă��̂܂g�p�������A���邢�@�͐��i�����̈ꕔ�Ƃ��ēY
���g�p������
c) ���i�����p�� �����A�����i�A���i�Ȃǂ̐Z�Ђ�n���ȂǕ����I�ȏ����������邽�߂Ɏg�p���ꂽ��
�@ �傤�p�� �@�@�H��̐ݔ����͌�
���E���i�Ȃǂ̐傤�p�Ɏg�p������
d) ��p�p�� �@�H��̐ݔ����͌����E���i�Ȃǂ̗�p�p�Ɏg�p������
�����p��
�@�H����̉��x���͎��x�̒����Ȃǂ̂��߂Ɏg�p������
e) ���̑� �@��L�̂�����ɂ������Ȃ��]�Ǝ҂̈������A�G�p���ȂǁB
�C �C ��
�@�C�A���͉͐�̂����펞���̉e�����Ă��镔������搅����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@ ���f�C�I���Z�x200PPM�ȏ�̐�
�V�@�H
�Ɠ��v�����p�Y�ƕ���
(1)�@���{�W���Y�ƕ��ނ̉���ɔ����A��
��20�N�������H�Ɠ��v�p�Y�ƕ��ނ����肵���B
�Y�ƒ����ނ̎�ȉ�����e�͎��̂Ƃ���ł���B
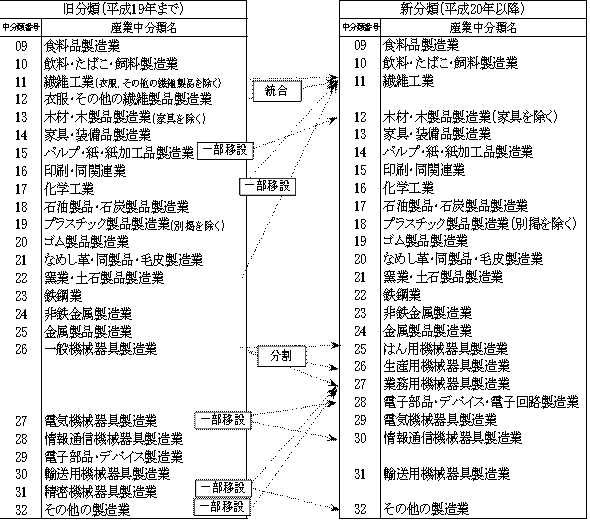
(2)�@�H
�Ɠ��v�����p�Y�ƕ��ނ́A�����A
���{�W���Y�ƕ��ނɏ������Ă��邪�A�ȉ��̂��̂͑��Ⴕ�Ă���B
|
�H�Ɠ��v�����p�Y�ƕ��� |
���{�W���Y�ƕ��� |
|
1421�@�m���E�@�B�����a�������� |
1421
�m�������� 1423�@�@�B�����a�������� |
(3)�@
�u������18�v���X�`�b�N���i�����Ɓi�ʌf����
���j�v�̕ʌf�ɂ���
�́A���\�̂Ƃ���ł���B
|
���� |
�����i�� |
���� |
�����i�� |
|
13 1521 1695 2051 215 2179 2199 2739 2741 2744 322 3229 3231 324 325 |
�Ƌ�E�����i �v���X�`�b�N���� �ʐ^�t�B�����i�����܂ށj ��� �ωΕ� �Ɛ� �͑��^�� �ڐ���̂����O�p��K ���˓� �`�� ���g��E�����i�E�{�^���E���֘A�i �i�M�����E��ΐ��������j ���� ���v�� �y�� �����A�^���p�� |
326 3271 3282 3283 3284 3285 3289 3289 3292 3293 3294 3295 3296 3297 |
�y���E���M�E�G��p�i�E���̑��̎����p�i ���� �� ������E��q�E���傤���� �ق����A�u���V �i���p��i�M�����E��ΐ��������j �m�P�E�a�P�E�������i ���@�r �ŔA�W���@ �p���b�g ���f���A�͌^ �H�Ɨp�͌^ ���R�[�h �ዾ |
�Ȃ��A�\�E�O���t��
�ł́A�Y�ƒ����ނ̖��̂����̂悤�ɏȗ����ĕ\�����Ă���B
|
�ȗ��������� |
�Y�ƒ����ޖ� |
�ȗ��������� |
�Y�ƒ����ޖ� |
||
|
09 |
�H���i |
�H���i������ |
21 |
�q�ƁE�y�� |
�q�ƁE�y�ΐ��i������ |
|
10 |
�����E���� |
�����E�����E���������� |
22 |
�S�| |
�S�|�� |
|
11 |
�@�� |
�@�ۍH�� |
23 |
��S���� |
��S���������� |
|
12 |
�؍ށE�ؐ��i |
�؍ށE�ؐ��i�����Ɓi�Ƌ�������j |
24 |
�������i |
�������i������ |
|
13 |
�Ƌ�E�����i |
�Ƌ�E�����i����
�� |
25 |
�͂�p�@�B |
�͂�p�@�B������ |
|
14 |
�p���v�E�� |
�p���v�E���E�����H�i������ |
26 |
���Y�p�@�B |
���Y�p�@�B������ |
|
15 |
����E���֘A |
����E���֘A�� |
27 |
�Ɩ��p�@�B |
�Ɩ��p�@�B������ |
|
16 |
���w |
���w�H�� |
28 |
�d�q���i |
�d�q���i��f�o�C�X�E�d�q��H������ |
|
17 |
�Ζ��E�ΒY |
�Ζ����i�E�ΒY���i��
���� |
29 |
�d�C�@�B |
�d�C�@�B������ |
|
18 |
�v���X�`�b�N |
�v���X�`�b�N���i��
���Ɓi�ʌf�������j |
30 |
���ʐM |
���ʐM�@�B������ |
|
19 |
�S�����i |
�S�����i������ |
31 |
�A���@�B |
�A���p�@�B������ |
|
20 |
�Ȃ߂��v |
�Ȃ߂��v������i��є���
���� |
32 |
���̑� |
���̑��̐����� |
�W�@�Y�ƕ��ނ̌�����@
(1)�@��ʓI���@�i���Ə����������ďo�ׂ���ŏI���i�ɒ��ڂ����i�t�j
�����i���͒����H�i���P�i�̎��Ə��ɂ��ẮA�H�Ɠ��v�����ɗp���鏤�i���ޕ\�̐����i�y�ђ����H�i�ԍ��i�U���j�̏�S���������ĎY
�ƕ��ނ����肷��B
�����i���͒����H�i�������̏ꍇ�́A�܂��A��Q���i�Y�ƒ����ށj�̓���̂��̂��ƂɁA��Q���ʂ̐����i�o�z���͉��H�������z�̍��v
���Z�o���A���̍��v���ő�̏�Q���������Ē����ނ����肷��B���ɂ��̌��肳�ꂽ�Q���̂�������A��L�Ɠ������@�łR���i�Y�Ə����ށj�����肵�A����ɂS
���i�Y�ƍו��ށj�l�Ɍ��肷��B
���������āA�����i���͒����H�ԍ��i�U���j���قȂ���̂����Ă���ꍇ�A��L�̕��@�Ō��肳�ꂽ�Y�ƕ��ށi�Q���̒����ށA�R����
�����ޖ��͂S���̍ו��ށj�ɂ��ׂĂ̏o�z���͉��H�������z���v�コ��邱�ƂɂȂ�B
����āA�ő�ƂȂ鐻���i�o�z���͉��H�������z���ύX�ɂȂ����ꍇ�A���Y���Ə��͑O��̎Y�ƕ��ނƂ͈قȂ�Y�ƕ��ނɌ��肳���
�i�Y�ƈړ��j�B
���@�Y�Ɗi�t��
�̗�
�@�i�ڔԍ��@�@
�����i�o�z
�Q�W�S�Q�P�P�@
�@10,000���~�@�@�Q�X(16,000���~)��
�R�O(15,000���~)���Q�W(10,000���~)
�Q�X�S�P�P�P�@
�@ 5,000���~�@�@�Q�X�S(9,000���~)��
�Q�X�U(7,000���~)
�Q�X�S�Q�Q�P�@
�@ 4,000���~�@�@�Q�X�S�P(5,000���~)��
�Q�X�S�Q(4,000���~)
�Q�X�U�X�P�P�@
�@7,000���~�@�@�@�@�Y�Ɗi�t���Q�X�S�P
�R�O�P�T�P�P�@
�@15,000���~
(2)�@����ȕ��@�i���ޗ��A�@�B�ݔ����ɂ��i�t���j
�S�|�Ƃ̈ꕔ�i��ʊi�t�����ו��ނ�2211�2241�2249�2471�2479�ɂȂ����ꍇ�j�����ẮA���ޗ��A�@�B�ݔ��A�����H���Ȃǂɒ��ڂ��āA��L�̕��@�ƈقȂ���ʂȊi�t���@���̂��Ă����i����i�t�j�B
�X�@���v�\
���v�\���A�u�|�v�͊Y�����l�Ȃ����͒������Ă��Ȃ����ځA�u�O�v�͎l�̌ܓ��ɂ����\�P�ʖ����A�u����v�̓}�C�i�X�̐��l��\���Ă�
��B
�u�ԁv�́A�P���͂Q�̎��Ə��Ɋւ��鐔�l�ŁA��������̂܂܌f����ƌX�̐\���҂̔閧���R��鋰�ꂪ���邽�߁A�铽�����ӏ��ł�
��A�R�ȏ�̎��Ə��Ɋւ��鐔�l�ł����Ă��A�O��̊W����P���͂Q�̎��Ə��̐��l���O��̊W���画������ӏ����铽�Ƃ����B�]�ƎҐ��ɂ��ẮA����16�N����(����17�N�W���ȍ~���\�̂���)�ɂ��Ă͔铽��������
���B
���v�\���ŁA�O�N�䖔�͍\���䓙�ɂ��ẮA�����_�ȉ���Q�ʂ��l�̌ܓ����Ă���A�܂��A����ςݏグ�v�ƍ��v�l����v���Ȃ��ꍇ��
����̂́A�l�̌ܓ��̊W�ɂ��B
10�@�n��ʋ敪
�s�����ʏW�v�̒P�ʂ͒�
�������_�̎s�����ł���A�L�挗�̋敪�͎��̂Ƃ���ł���B
|
�L�挗 |
�s���� |
|
�V��n�� |
���Îs�A�����s�A���P���A������ |
|
�x�R�n�� |
�x�R�s�A����s�A�M�����A��s���A���R�� |
|
�����E�ː��n�� |
�����s�A�X���s�A����s�A�ː��s |
|
�v�g�n�� |
�v�g�s�A��v�s |
�@
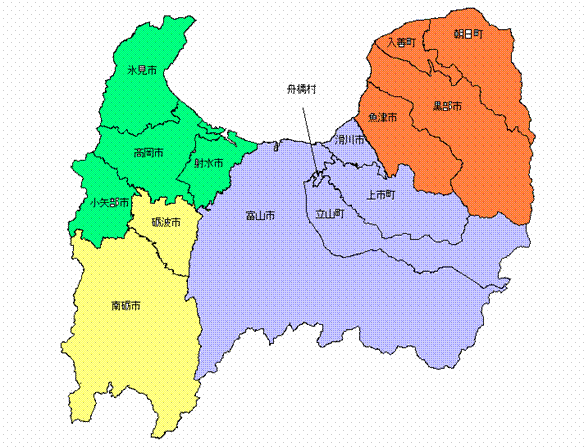 |
11�@���̑�
(1)�@����20�N�̑O�N��ɂ��ẮA���{�W���Y�ƕ��ނ̉��肪�s��ꂽ���߁A����19�N�̐��l��20�N�̕��ނōďW�v���v�Z���Ă�
��B
(2)�@����19�N�̑O�N(����18�N)��ɂ��ẮA���Ə��̕߂������s�������߁A
���n����l���������̂Ōv�Z����
����B�܂��A�����Ƃ̎��Ԃ�I�m�ɔc�����邽�߁A�������ڂ�ύX�������Ƃɂ��A����18�N�ȑO��
���l�Ƃ͐ڑ����Ȃ��B
(3)�@���������݂ɋx�ƒ��A���Ə������y
�ё��ƊJ�n�㖢�o�ׂ̎��Ə��ɂ��ẮA�W�v���珜�O����Ă���B
(4)�@���̒������ʂ́A���ŏW�v��������
�ŁA����A�o�ώY�ƏȂ����\����u�H�Ɠ��v�\�i�Y�ƕ҂ق��j�v
�̐��l�Ƒ��Ⴊ���蓾��B
(5)�@��
�̓��v�\�ɋL�ڂ��ꂽ���l�𑼂�
�]�ڂ���ꍇ�́A�u����20�N�i2008�N�j
�x�R���̍H�Ɓv�ɂ��|�L���邱�ƁB
�@�@(6)�@�{���̓��e�ɂ��Ă̖₢���킹��͎��̂Ƃ���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���̓��e�ɂ��Ă̖� �����킹�͉��L���Ăɂ��肢���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@930�]8501�@�x�R�s�V���ȗւP �ԂV��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �x�R���o�c�Ǘ������v�����ۏ��H�W
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ Tel 076-444-3193(����)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ Fax 076-444-3490(�ۓ�)