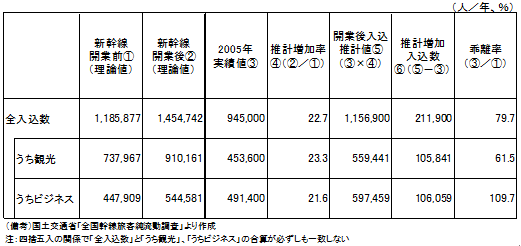ポスト北陸新幹線に向けて
|
|
|
|
2015年3月14日に北陸新幹線が開業する。50年来の悲願が達成する「北陸新幹線元年」であると同時に、新しい時代へのスタートでもある。 本稿では、北陸新幹線の効果、富山県経済の現状を整理しつつ、北陸新幹線開業後「ポスト北陸新幹線」における富山県について、考察を試みることとしたい。 |
1 北陸新幹線の効果2013年3月に株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」)が公表した「北陸新幹線開業による富山県内への経済波及効果」調査によれば、年間約88億円(うち直接効果約57億円)の経済波及効果があると試算されている。これは、北陸新幹線開業に伴う時間短縮効果によって首都圏からの入込数が増加することによるものである。 調査の概要であるが、「東京からの時間距離」や「地域資源(県内GDP、観光資源数など)」等の指標を組み合わせて「首都圏から全国各地への入込数推計モデル」を構築し試算したものである。 ここで注目すべきポイントは、乖離率である。モデルから試算された理論値(上表①)と実績値(上表③)の差異で、乖離率が100%を超える場合は他地域との比較で実力以上の入込数を確保、100%に満たない場合はその実力を発揮できていないと評価できる。 富山県の場合は、ビジネス入込数は概ねモデル理論値通りの実績を示しているが、観光入込数はモデル理論値を大幅に下回る結果となっている。 |
2 旅客純流動調査から見た富山県の現状筆者はよく「ビジネスは富山県、観光は石川県」と聞く。一般的にもそう言われているのであろう。現実にはどうか、国土交通省の調査をまとめたものが図表2である。 図表2 全国幹線旅客純流動調査(2010年、国土交通省)
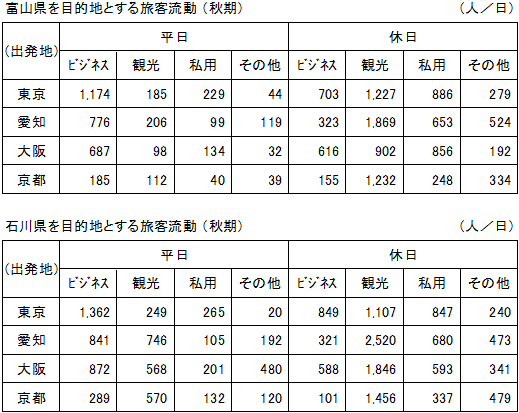 平日の東京からのビジネス客は、富山県は1,174人/日と、石川県の1,362人/日を下回っている。一方で、休日の東京からの観光客は、富山県は1,227人/日と、石川県の1,107人/日を上回っている。本件データ(東京)のみ参照すれば、観光の富山県、ビジネスの石川県となる。読者の実感と比較して如何であろうか。 石川県の観光資源は「兼六園」という中核となる存在(キラーコンテンツ)が市街地にあるが、富山県の場合、魅力的な観光資源が多く、かつ郊外に分散している結果、賑わい創出にまでは至っていないとも考えられるだろう(富山県「新幹線開業に関する首都圏住民に対する意識調査について」によれば、回答者の20%超を獲得した観光地は、石川県1カ所(兼六園)に対し富山県は4カ所となっている)。 北陸新幹線の開業から1年後の2016年3月には北海道新幹線(新青森~新函館北斗間)が開業する。北陸地域の観光産業にとっては大きな脅威となろう。 今後の観光産業は、地域間の競争が激しくなることが予想される。富山県全体の問題として、数多ある魅力的な観光資源の中から「富山県の顔(アイコン)」となるべきキラーコンテンツを醸成していく必要がある。同時に、地域全体の持続的発展、観光品質の向上などを指向する組織的取組(観光資源の評価や利害関係の調整など)を担う日本型DMO(Destination Management Organization)の設立なども検討に値しよう。 なお、大阪・京都から富山県を訪れる観光客は、現状、東京からのそれを大きく上回っており、県内の観光産業に大きく寄与している。しかしながら、北陸新幹線開業によってサンダーバードの富山直通は全て廃止となるため、その動向については注視すべきである。 |
3 富山県経済をとりまく現状富山県の経済状況は、「一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復しつつある」状況にある(2014年10月、富山財務事務所)。 実際に、県内の大型小売店販売額(2014年10月速報値、経済産業省「商業動態統計」)は前年同月+2.4%(同全国平均+1.0%)と比較的高い伸びを示しており、県内における企業の設備投資(2014年6月時点、DBJ調査)も、2014年度は前年度比+41.2%(同全国+15.2%)と旺盛な投資意欲を示している。 同時に、完全失業率(2014年7~9月平均、総務省「労働力調査」)も3.0%(同全国平均3.5%)と全国平均を下回って推移しているが、この点については、少し考察を掘り下げたい。 図表3 富山県の労働関連数値比較
完全失業率の低下は、一般的には「就業者数の増加」に伴う失業者の減少を想像されるであろう。しかしながら、実際には就業者数が減少している点、注目すべきである。 就業者数が減少しているにもかかわらず完全失業率が低下している理由は、労働力人口の減少によるものである。富山県の経済状況の底堅さ(雇用環境の堅調さ)によるところもあろうが、本件データからは、労働力人口の減少によるものと評価すべきであり、富山県は長期的には「慢性的な人手不足時代」に突入したとも表現できよう。 富山県の生産年齢人口(15~64歳)であるが、2010年は66.2万人であったところ、2025年には54.9万人にまで減少すると推計されている(総務省「国勢調査」、日本の地域別将来推計人口(2013年3月推計))。 就業者数が減少する中で課税対象所得が増加していることは、一人当たりの賃金増加を示しており、今後も、生産年齢人口が減少すると予測される中では、こうしたトレンドを避けることは出来ないであろう。 |
4 富山県が選ばれ続けるために北陸新幹線開業後「ポスト北陸新幹線」の富山県が持続的に成長するために必要なことは何か、これまで述べてきたことを踏まえ、考えてみたい。 大きな可能性をもつ観光産業の育成、特に地域外からの誘客は重要である。その際、豊富すぎて個々のインパクトが薄くなっている観光資源を整理し、地域外へ強力にPRできるキラーコンテンツを育てていく必要があろう。 但し、当然のことながら、地域外にPRできる本物の観光資源は、その土地や周辺地域の住民に評価され、大切に守り続けられているもの(シンボル)そのものであり、言い換えれば「地域への愛着」がカタチとなったものである。 そして、これらを維持・育成していくためには、住民自身の積極的な評価や関与が求められるところである。 企業から見た富山県はどうか。 新規の企業誘致も重要だが、「ものづくり県」「工業県」と評される礎となった技術力ある優良な企業を、厳しい時も富山県を支え続けてきた数多くの企業を、今後も富山県に繋ぎ止めておく努力こそ重要であろう。 北陸新幹線開業によって世界が身近になるに比例してグローバル競争に晒されていく中で、富山県が企業に選ばれるために、そして選ばれ続けていくために、必要なことは多々ある。 ただ究極的には、企業の経営者や従業員が、富山県という「地域への愛着」を持つことが重要ではなかろうか。 こう考えると、ポスト北陸新幹線の富山県にとって必要なことは数多くあるが、重要な観点は「富山県への愛着」を醸成することであろう。 最後に、そのための試みの一つとして、アートを中心とした地域づくりを提案したい。 図表4にあるとおり、富山市内だけでも、数多くの美術館・博物館等がある。しかも、北陸新幹線開業後数年内には富山駅の南北がつながり、公共交通機関による回遊性が大幅に向上するのである。 またアート(art)の語源は、ラテン語の「アルス(ars)」で、自然の配置、技術、才能などの意味があり、テクニックの語源となるギリシャ語「テクネ(techne)」の訳語に基づいている。こう考えると、アートは、高い技術力を誇る富山県内の企業を表現するキーワードの一つと言えよう。 2015年「北陸新幹線元年」、富山県がアートにあふれ、ますます成長することを願って本稿を締めたい。 図表4 富山市内の美術館等
 以上 (注 本稿の内容・分析に関わる箇所は、筆者個人に帰するものであり、株式会社日本政策投資銀行の公式見解ではありません。) |