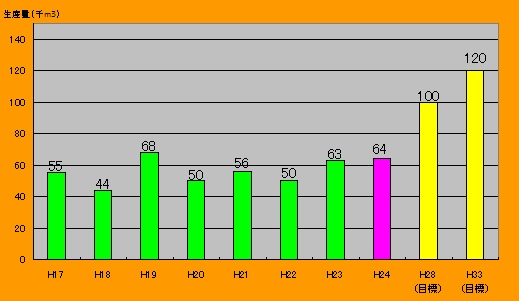県産材の利用促進について富山県農林水産部森林政策課 |
|
|
1 はじめに富山県内の森林のうち、民有林の28%にあたる約5万haはスギを中心とした人工林です。このうち、木材として本格的に利用可能な9齢級(41〜45年生)を超える森林が約7割を占め(図-1)、資源的に成熟期に入りつつありますが、長期にわたる木材価格の低迷などから素材生産量は年5〜6万立方メートル台と低く推移しています(図-2)。 県産材の利用を促進することは、林業生産活動による森林資源の循環利用と健全な森づくり、木材産業の振興につながります。このため、県では「富山県森林・林業振興計画」において、県産材素材生産量の目標を平成28年度10万立方メートル、平成33年度12万立方メートルとし、市町村や森林組合、木材業者等の関係者と一体となって、間伐や林内路網整備、森林境界の明確化、高性能林業機械の導入、木材加工流通体制の整備等による県産材の安定供給とともに、県産材の利用促進を進めています。ここでは、住宅等の県産材の利用促進や新しい取り組みをご紹介します。 図-1 民有林のうち人工林(針葉樹)の齢級別面積及び蓄積(平成24年3月31日現在)
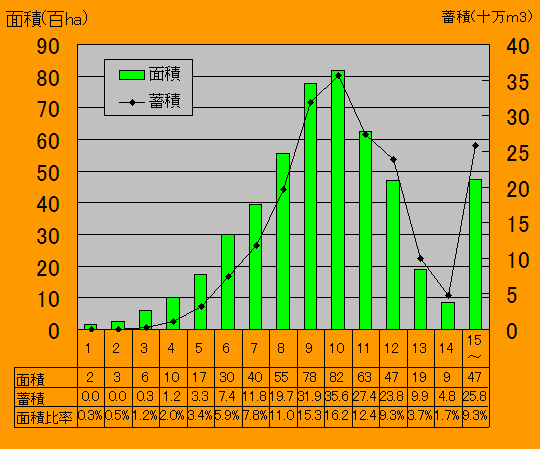 資料:富山県森林政策課調べ |
2 住宅における県産材の利用促進木材需要の多くは建築用材であり、県内の新設住宅着工戸数の8割以上が木造であることから(表-1)、住宅に県産材を使うことは県産材の需要拡大に直接つながります。県では平成22年度より、県産材を一定量以上使った住宅の新築・増改築に対し、使用した量に応じて最大40万円を助成する「とやまの木で家づくり支援事業」を実施しています。平成22〜24年度の3年間で延べ257棟に助成しましたが、利用した施主さんへのアンケート結果から、県産材の温もりや地元の木材を使うことへの安心感など、満足度が高いことがうかがえました。また、この事業をきっかけに、これまで県産材を利用していなかった工務店が地元の製材所と連携し、新たに県産材の取り扱いを始めるなどの広がりも見せています。 表-1 木造率の現状
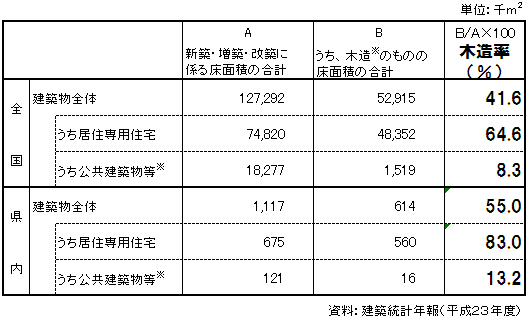 写真-1 県産材を使った住宅(とやまの木で家づくり支援事業)
 |
3 公共建築物等での木材利用の推進建築用材の需要の多くは住宅ですが、今後、我が国の人口は急速に減少すると推計されており、住宅着工戸数が大幅に増加することは期待できません。一方、高度経済成長期に整備された公共建築物の多くは、今後、建て替え期に入ると見られます。毎年の公共建築物における木造率は、新たに着工された建築物全体の中の割合は低いものの(表-1※)、公共建築物は展示効果が高く、木造で建築することは、利用者に木材利用の重要性や木の良さに対する理解を深めてもらうことに大変効果があります。国では、平成22年10月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の施行と「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」を策定し、耐火が求められない低層の公共建築物については積極的に木造化を図ること、木造化が困難と判断されるものについても、内装等の木質化を促進することとしました。 このような動きを受けて、県では、平成23年4月に「富山県公共建築物等木材利用推進方針」を定め、平成33年度の公共建築物等の木造率25%を目標に、駐在所など県有施設の木造化を図るとともに、市町村や福祉施設等に対し、木造化や内装木質化への支援を行っています。 また、公共建築物等の木造化を推進するため、昨年度、学識経験者や民間事業者、市町村等からなる「富山県木造公共建築物等推進会議」を設置するとともに、今年3月には、木材の利用に対する疑問や設計上の留意点、優良な事例を紹介した、発注者向けの木造公共建築物推進のための手引きを作成し、普及促進を図っています。 写真-2 木造公共建築物(中部コミュニティセンター(富山市藤木))

|
4 木育の推進「木育」とは、木材に対する親しみや木の文化への理解を深めるため、多様な関係者が連携・協力しながら、木の良さや木材利用の意義を学ぶ教育活動のことです。本県では、平成19年度に創設した「水と緑の森づくり税」を活用して、未来を担う子どもたちが「遊び」を通じて、小さい頃から身近に木に触れ、木の良さを体感してもらうための取り組みを行っています。
写真-5 親子連れで賑わうイベント会場の県産材遊具コーナー

写真-6 こどもの城で遊ぶ園児たち
 |
5 新たな取り組み(木質バイオマス発電)県内の木材需要のうち、径が細かったり、曲がったものなど製材にならない形質の悪い低質材は約50%を占め、これまで大半は製紙用チップとして利用されてきました。しかし、リーマンショック以降の紙需要の減少などから、国産製紙用チップの需要が大きく減少し、森林資源の循環利用を図っていく上で、低質材の安定的な需要先の確保が課題となっています。 このような中、昨年7月より再生可能エネルギー固定価格買取制度がスタートし、未利用間伐材については有利な条件(表-2)が整備されたこと、搬出されず森林に残された間伐材が多くあること、県内で木質バイオマス発電に意欲を示す事業者が現れたことなどから、県では、平成24年度国補正予算を活用し、今年度、民間事業者が実施する木質バイオマス発電施設整備に対し支援することとしました。 現在、県が公募により選定した事業者が平成27年度からの稼動に向け、プラント設計等を行っており、準備が整い次第、建設に着手する予定です。 表-2 再生可能エネルギー固定価格買取制度における
木質バイオマスの買取価格と買取期間 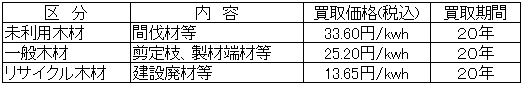 写真-7 木質バイオマス発電所(他県の事例)
 |
6 おわりに県産材の需要拡大を図るには、このような県産材の利用促進策とともに、低コストで効率的な原木生産流通体制の整備や、年間を通じた品質・性能の確かな県産材の安定供給体制の整備、さらに、イベント等を通じて県民への県産材利用の普及啓発を図っていくことが重要です。 県では、森林・林業・木材産業の活性化を図るため、今後とも、森を育てる「川上」と木材を使う「川下」が連携し、関係者一体となって、県産材の利用促進に取り組む施策を推進することとしています。 |