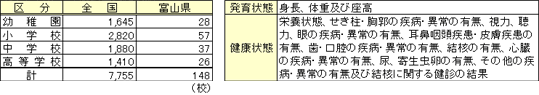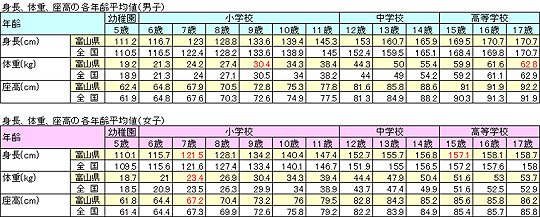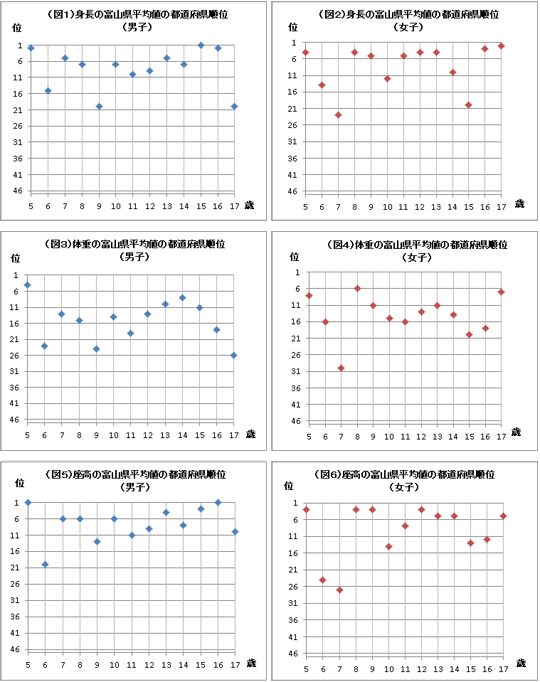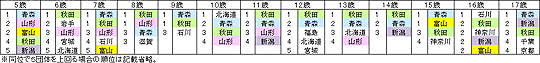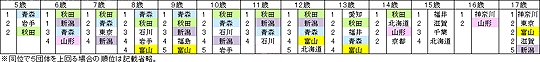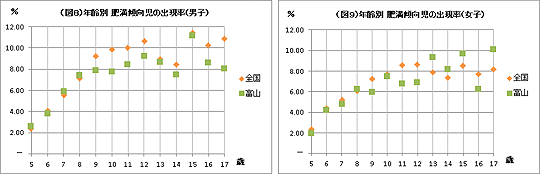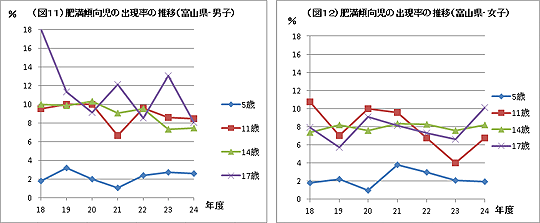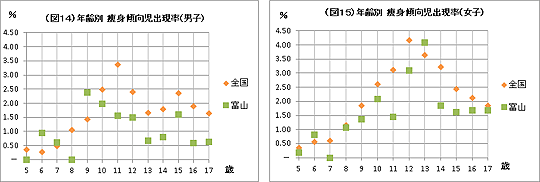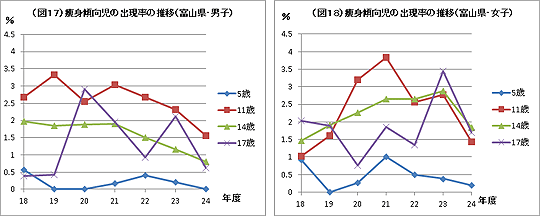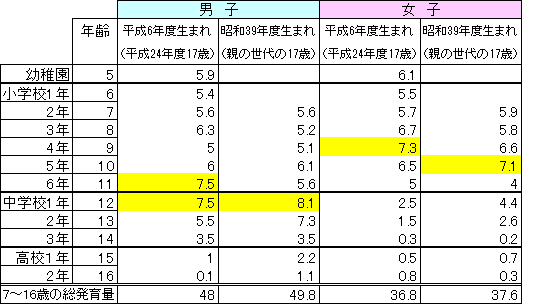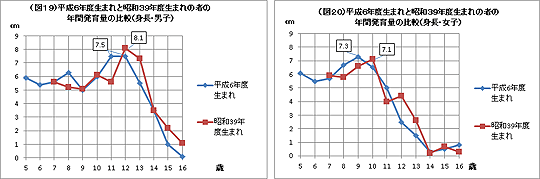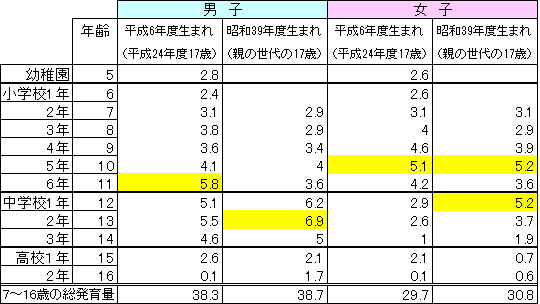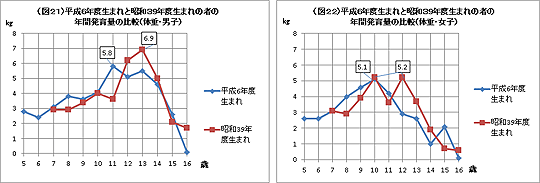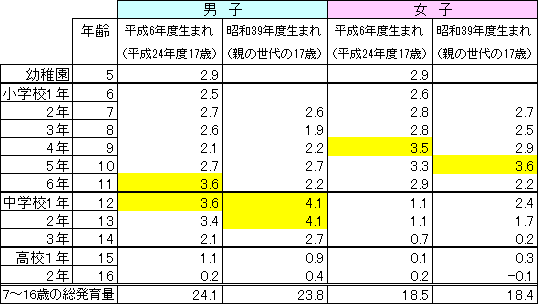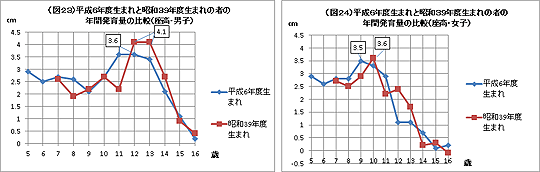平成24年度学校保健統計調査からみる
|
|
|
1 はじめに学校保健統計調査は、文部科学省が昭和23年から毎年実施している基幹統計調査で、学校における幼児、児童及び生徒の発育や健康の状態を明らかにすることを目的に実施されており、平成24年度の調査も、4月1日から6月30日の間に実施されました。 調査対象は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校に在籍する、満5歳から17歳(4月1日現在)までの幼児、児童及び生徒で、学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、 なお、この調査は、抽出調査のため、全ての学校が対象となるわけではありません。平成24年度の調査では、下記の表1のとおり富山県内は148校の学校で実施され、全国では発育状態調査は全幼児、児童及び生徒の4.9%、健康状態調査は23.4%が対象となっています。
|
|
保健分野も経済と密接な関係があり、また、学校保健統計調査は、各都道府県の結果が公表されていることから、本稿では、発育状態調査の結果から、富山県の幼児、児童及び生徒の発育の状態を、全国との比較や親の世代の年間発育量との比較を交えてご紹介したいと思います。 |
2 平成24年度の富山県の調査結果(1)身長、体重、座高の結果身長、体重、座高の各年齢平均値(表2)と、その都道府県順位(図1から図6)をみると、男子9歳及び17歳の体重、女子7歳の身長、体重、座高、女子15歳の身長については全国平均値を下回っていますが、ほとんどの年齢において全国平均値を上回っており、都道府県順位も上位から中位に位置しています。このことから、富山県の幼児、児童及び生徒の発育状態は、全国的な比較において良好であると考えられます。 |
|
それでは、都道府県によって幼児、児童及び生徒の発育状態に特徴はあるのでしょうか。平成24年度の調査結果から、都道府県で平均身長が高い順に5つあげてみました。表3及び表4からみると、男子、女子ともに青森県や秋田県、山形県、新潟県の平均身長が高い傾向が見られます。富山県はというと、男子は5歳、7歳、15歳、16歳で、女子は8歳、9歳、12歳、13歳、17歳で、5位以内となっています。 なお、青森県や秋田県をはじめとする東北地方の幼児、児童及び生徒の平均身長が高い傾向について、平成24年調査以前について同様に調べてみると、同じような傾向が少なくともここ10年は続いていることがわかりました。 |
(2)肥満傾向児、痩身傾向児の出現率について【肥満傾向児】性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上であるときに肥満傾向児としています。
算出方法を変更した平成18年度以降での全国的な傾向は以下のとおりで、肥満傾向児の出現率の推移は、男子、女子ともに減少傾向にあります。 それでは、平成24年度調査における富山県の状況についてみていきたいと思います。 富山県の幼児、児童及び生徒(男女計)の肥満傾向児の出現率については、全国値との比較の観点からみると、図7にあるように、5歳から7歳は全国値とほぼ同率で増加し、8歳で若干全国値を上回り、9歳から12歳が全国値を大きく下回り、13歳と15歳で若干全国値を上回る結果になっています。 |
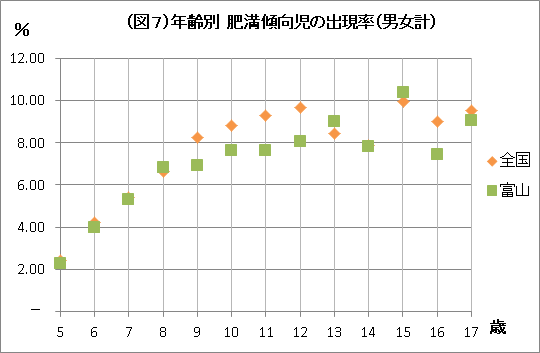 |
|
男女別の出現率(図8、図9)については、男子は男女計(図7)の動きとほぼ同じ出現傾向を示していますが、女子は13歳から15歳及び17歳で全国値を大きく上回っています。 |
|
富山県の男女の値を比較してみると、6歳、13歳、14歳及び17歳を除き、男子の肥満傾向児出現率が女子を上回っていることから、全国的な傾向(前記 |
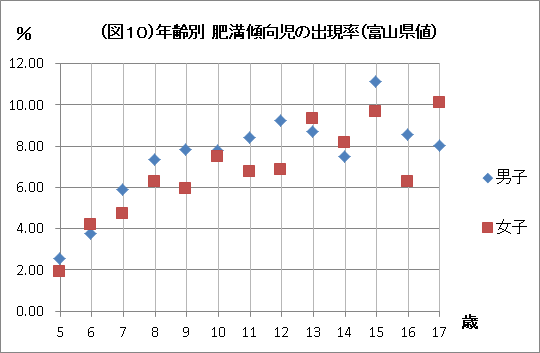 |
|
また、肥満傾向児の出現率の推移(図11、図12)は、男子、女子ともに14歳が他の年齢と比較して、横ばいに近い形を示しています。 |
【痩身傾向児】性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が−20%以上であるときに痩身傾向児としています。 算出方法を変更した平成18年度以降での全国的な傾向は、男子、女子ともに、増加傾向にあります。 富山県の幼児、児童及び生徒(男女計)の痩身傾向児の出現率については、平成24年度調査からみてみると、図13にあるように、6歳及び9歳以外では全国値を下回っています。 |
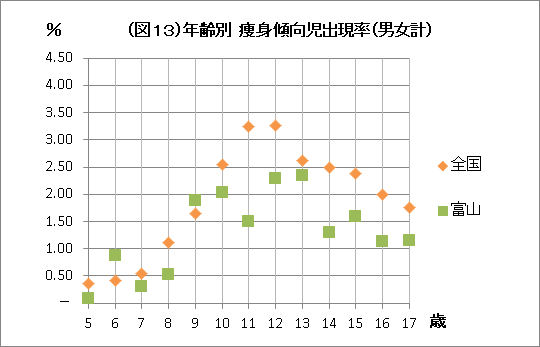 |
|
男女別の出現率(図14、図15)については、男子は6歳及び9歳で出現率が全国値を大きく上回っています。女子は、全国値を上回る又は下回るの違いはありますが、全国の傾向と同じく、12歳や13歳で出現率が大きくなっています。 |
|
富山県の男女の値を比較してみると、12歳以上の女子の出現率が男子を上回り、特に12歳及び13歳における差が大きくなっています。(図16) |
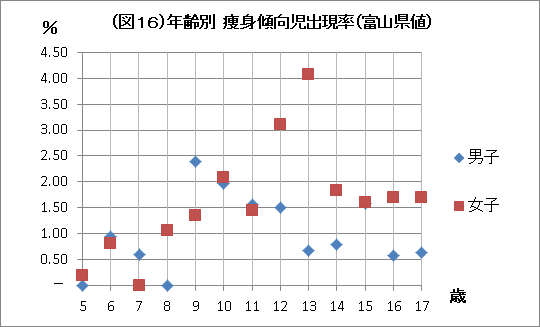 |
|
また、痩身傾向児の出現率の推移(図17、図18)は、17歳男女がともに調査年度により大きく増減し、その他の年齢においては男子、女子ともに、凸形に近い形を示しています。全国的には増加傾向であるので、各年代において年度の経過の中で近年は下降の動きを示してみえる富山県の傾向は幼児、児童及び生徒の健康にとって好ましい動きと考えます。 |
3 世代間での年間発育量の比較次に、富山県の17歳(平成6年度生まれ)の年間発育量を、富山県の親の世代の年間発育量と比較してみたいと思います。
比較する親世代の数値については、昭和39年度生まれの者の数値をとっていますが、5歳時の数値(昭和45年度調査)及び6歳時の数値(昭和46年度調査)は、都道府県別平均値がありませんでしたので、空欄になっています。また、12歳時の数値(昭和52年度調査)及び13歳時の数値(昭和53年度調査)は、都道府県別の数値がなかったものの、北陸地域(新潟、富山、石川、福井)の平均値があったことから、それを使用しています。 |
(1)身長17歳(平成6年度生まれ)の年間発育量(表5、図19、図20)をみると、男子では11歳時及び12歳時に、女子では9歳時に、最大の年間発育量を示しています。 また年間発育量を親の世代と比較すると、男子では年間発育量が著しくなる時期が1歳早くなっており、女子でも年間発育量が最大となる時期が、1歳早くなっています。 |
(2)体重17歳(平成6年度生まれ)の年間発育量(表6、図21、図22)をみると、男子では11歳時に、女子では10歳時に、最大の年間発育量を示しています。 また年間発育量を親の世代と比較すると、男子では年間発育量が最大となる時期は2歳早くなっており、女子では年間発育量が最大となる時期は、ほぼ同じになっています。(親世代は12歳時に、再び10歳時と同じ年間発育量を示していますが、12歳時の数値は北陸地域の値であることにご注意ください。) |
(3)座高17歳(平成6年度生まれ)の年間発育量(表7、図23、図24)をみると、男子では11歳時及び12歳時に、女子では9歳時に最大の年間発育量を示しています。 また年間発育量を親の世代と比較すると、男子では年間発育量が著しくなる時期が1年早くなっており、女子でも年間発育量が最大となる時期は、1年早くなっています。 |
|
これらの結果からわかることは、親世代と子世代で見ると、成長の途中段階では、子世代の方が成長のピークを迎える時期が若干早くなっていますが、最終的な成長量については、大きな差はないこと、また、男子と女子を比較すると、親世代も子世代も、女子の方が成長のピークを迎える時期が早いことがわかります。 |
4 おわりに今回は、発育状態調査の結果についてご紹介しましたが、このほか健康状態調査の結果も文部科学省HPに掲載されておりますので、ご覧ください。 文部科学省HP「学校保健統計調査」 また本調査は、幅広く活用される貴重な統計の作成のために、調査実施校のご協力を得て、平成25年度も実施されることとなっております。 |