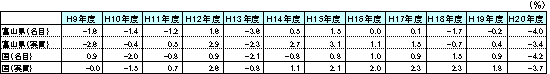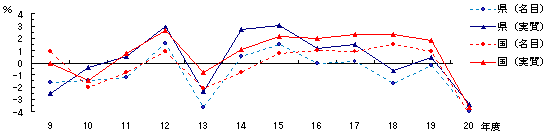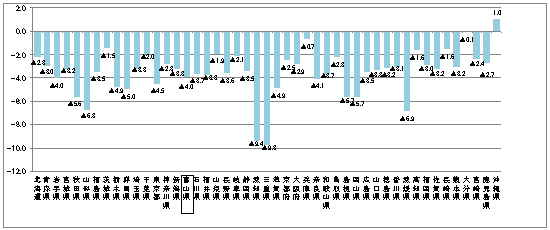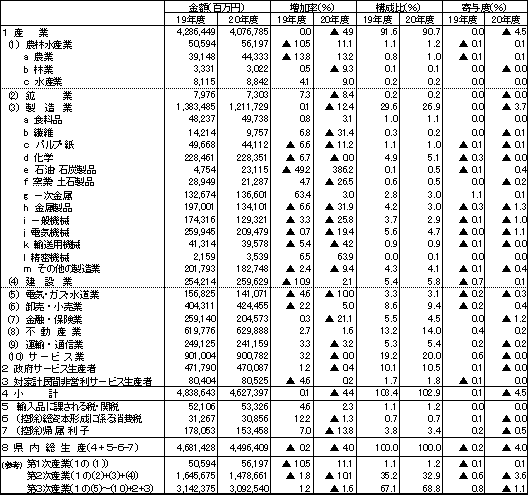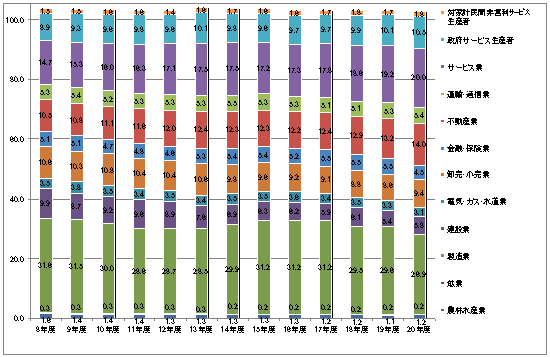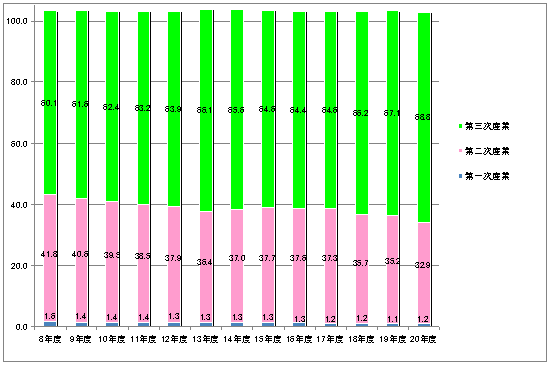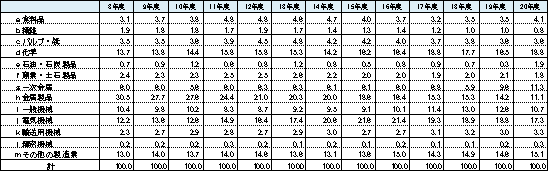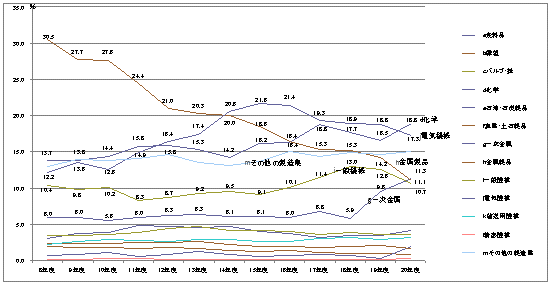富山県民経済計算推計結果にみる県内経済統計調査課 南保 勇治 |
1 はじめに富山県は、平成23年2月に、平成20年度富山県民経済計算の結果を公表しました。また、平成23年4月に、各都道府県の推計結果をとりまとめた「平成20年度の県民経済計算について」が、内閣府から公表されました。 内閣府の公表を受けての県内での報道内容は概ね次のようなものでした。
ここで言う「1人当たり県民所得」とは、県民雇用者報酬、財産所得、企業所得を合計したものを県人口で除したものであり、個人の所得ではなく、企業利潤なども含んだ県経済全体の所得を表しているものであることに注意を要します。 全体として平成20年度の国内及び県内の経済活動が大変厳しいものであったことが報じられましたが、実際の富山県経済の状況がどのようなものであったのか、以下、国や他県との比較も含めて見ていきたいと思います。 |
2 平成20年度の経済概況平成20年度の日本経済は、前半は米国などの金融不安、景気の減速傾向、原油・原材料価格の高騰などから緩やかな景気の弱まりを示していました。そこへ、9月の米国リーマン・ブラザーズ証券の経営破綻を発端とした世界的な金融危機が発生して世界同時不況とも呼ぶべき事態が引き起こされ、日本経済をけん引していた外需が大幅に減少し企業の業績が急速に悪化しました。そして、これが賃金の低下などを引き起こして家計にも影響を及ぼし、個人消費や住宅投資も減少させるなどして、年度後半に深刻な景気後退を招きました。 平成20年度の本県経済も、当然にこのいわゆるリーマンショックの影響を強く受け、平成20年度県内総生産は名目で前年度比4.0%減の4兆4,964億円、実質で前年度比3.4%減の4兆9,672億円といずれも大きな減少となりました。また、1人当たり県民所得も前年度比6.3%減の2,949千円となりました。 平成20年度の概要を前年度に比較して示したものが表1です。
表1 富山県及び国の状況
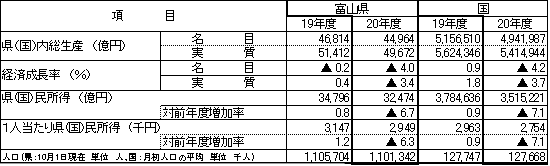
(注) 国値は内閣府『国民経済計算年報(平成22年版)』に、県人口は総務省『人口推計年報』による。 また、経済成長率(名目及び実質)を国のものと併せて表示したものが表2、それをグラフ化したのが図1です。 図1をみると、やはり平成20年度の急激な落ち込みが目立ちます。特に、国の成長率は、平成14年度以降、「戦後最長の景気回復」とも呼ばれて好調であったものが、平成20年度に一気に悪化した様子がよくわかります。なお、平成13年度の落ち込みは、いわゆるIT不況と米国同時多発テロの影響による景気落ち込みによるものです。 本県の成長率は、名目で3年連続のマイナス、実質で2年ぶりのマイナス成長となりました。また、過去に遡って本県の経済成長率の推移をみると、平成15年度までは、国の成長率とほぼ同一か、やや上回る勢いが見られますが、それ以降の成長率は、いずれの年も全国に及びません。「戦後最長の景気回復」と呼ばれるこの時期に、本県ではその恩恵を十分には享受できず、逆に県民雇用者報酬の伸び悩みなどによる民間消費の落ち込みなどで厳しい状況にあったことがみてとれると思います。なお、富山県の県民雇用者報酬、企業所得、財産所得の推移を示したものが図2です。これによれば、企業所得がある程度の伸びを示していた期間もありますが、県民雇用者報酬は逓減傾向にあったことがわかります。
図2 県民雇用者報酬、企業所得、財産所得の推移
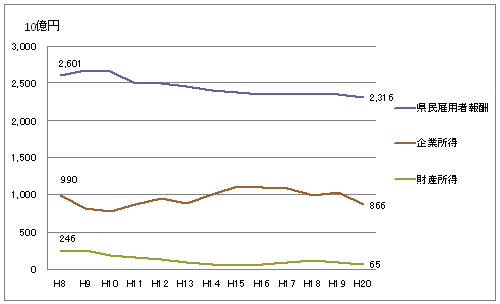 図3は平成20年度の各都道府県の名目成長率の一覧です。 図3をみると沖縄県を除き、各県は軒並みマイナスとなっています。 特にマイナスが目立つのは、愛知県と三重県です。それぞれの県の県民経済計算報告書を調べ、その要因を探ってみました。まず、愛知県では、主力産業である自動車の輸出が急減して過去に例のない規模の生産調整が行われたことなどの結果、輸送用機械が大きく落ち込んだほか、電気機械、一般機械などが減少しています。また、三重県では半導体製品の需要減少や単価の下落、液晶パネルの大幅な単価下落などにより電気機械が大幅減となったほか、輸送用機械、一般機械、化学なども減少しているようです。両県にとどまらず他の都道府県の数字を見ても、今さらながらリーマンショックの影響の大きさがわかります。 一方、このような経済情勢の中で、沖縄県が唯一プラス成長を記録し、目を惹きます。理由としては、沖縄県では、輸出向け製造業の割合が比較的小さい一方で、観光などのサービス業の割合が大きく、今回の外需急減の影響が比較的小さかったこと、また、多くの地方の県とは異なり、人口と世帯数の両方が増加したことに伴い不動産業が増加したことなどが考えられます。 |
3 経済活動別の県内総生産では、本県の平成20年度の経済活動はどのようなものであったのでしょうか。 表3は経済活動分野別の名目県内総生産額、増加率、構成比、寄与度を前年度と併せて示したものです。 まず、表3をみて感じるのは製造業と金融・保険業のマイナス幅の大きさです。特に本県は、製造業が県内総生産の最大の割合を占める主要産業であり、表4に示したとおり全国的にも製造業の比率の高い県です。したがって、この製造業のマイナスが本県経済に大きな影響を及ぼすこととなります。図3では、他県に比べて本県のマイナス幅自体は目立ちませんが、富山県も今回のリーマンショックのダメージを強く受けた県であると思います。
表4 各都道府県製造業構成比
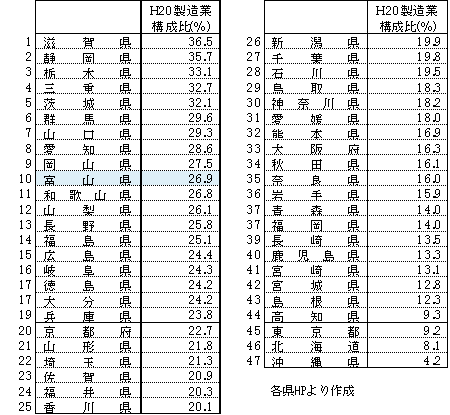 それでは、具体的に表3の各産業の生産額などを見ていきます。
なお、「2 政府サービス生産者」は国(出先機関)、県、市町村の公務や公立学校などの生産額、「3 対家計民間非営利サービス生産者」は社団法人、財団法人、政党、宗教法人、私立学校などの生産額が推計されており、それぞれ0.4%減、0.2%増となりました。 また、「5 輸入品に課される税・関税」は、関税及び輸入品に係る消費税などからなります。 「6(控除)総資本形成に係る消費税」は、設備投資や在庫投資に係る消費税控除額からなり、まだ費用化(価格に転嫁)されていないものであるため、ここで控除して総生産額から除きます。 「7(控除)帰属利子」は、金融業生産額のための特殊な項目であり、各経済活動別の県内総生産(付加価値)に含めて計上されている利子分と金融業で一括計上されている利子分の二重計上を解消するためここで控除します。 これら5、6、7は経済活動別に分割することが難しいため、ここで一括して加算(5)、控除(6、7)して県内総生産を推計することとなっています。 |
4 産業構成比の推移次に、県内の産業構成比の推移を平成8年度から年ごとに示したものが図4です。 図4を見てみますと、製造業が、一貫して本県の主要産業を占めているのは変わりありませんが、僅かずつですが次第にその比率を低めていく傾向にあります。 また、近年の公共事業費の減少の影響からか、建設業の占める割合が、大きく減少していっているのが目立ちます。 一方で、サービス業が年々比重を高めてきており、本県でも産業のサービス化が着実に進みつつある様子がわかります。 なお、不動産業は、県民経済計算上、帰属家賃を含めることとなっているため、持ち家率の高い本県では大きな比率を占める形となっていると思われます。 参考として第一次産業、第二次産業、第三次産業の占める割合の推移表を図5として示しました。ものづくり県を自負する富山県ですが、生産額の面では既に7割近くがサービス業を中心とした第三次産業が占める形となっています。 また、豊かな農林水産物を産する本県ですが、生産額だけでとらえると第一次産業は1%台に留まっています。 |
5 製造業における各産業の推移ここでは、特に製造業のなかの各部門の占める割合の推移を見てみます。 平成8年度からの比率を示したものが表5、それをグラフ化したものが図6です。 図6をみると、平成8年度から平成20年度までの限られた期間の中でも、本県製造業の中でかなり大きな変化が起きていることがわかります。 まず、「h金属製品」が、平成8年度は製造業のなかで圧倒的多数の30.5%を占めていましたが、平成20年度ではわずか11.1%へと減少しています。本県の金属製品では、住宅用アルミ製サッシ、ビル用アルミ製サッシの生産が大きな部分を占めており、近年、この生産が大きく減少しているものと思われます。 平成14年度以降、県内製造業で最大割合となっていた「j電気機械」は、本県では集積回路などの電子部品製造が大きな額を占めていますが、この分野の国際的な競争の激化による製品単価の下落などが影響してか、近年は逓減傾向にあります。また、比較的順調に推移してきた「i一般機械」も、近年の景気下降の影響を受けて生産用機械が減少するなどして構成割合が若干小さくなってきています。 他方で、「d化学」は、堅調に推移し、平成20年度は県内製造業で最大となりました。 「くすりの富山」といわれるように、本県は伝統的に製薬業がさかんであり、特に、近年はOEM生産(相手先ブランド名による生産)が増加するなどして、生産額を伸ばしています。OEM生産は、利益幅が薄いことや自社ブランドの育成につながらないことなどの問題が指摘されたりしますが、これが推進力となって、他の産業が伸び悩む中でも化学は比較的順調に推移しているのが現状です。 鉄鋼、非鉄金属の「g一次金属」は、ここ2年間、アルミ地金や棒鋼などの生産額が増えたことなどにより比率を高めています。 |
6 おわりに県民経済計算は、推計対象年度の各種統計資料が出揃ってからこれをもとに推計するという制約上、推計対象年度から1年半程度遅れて公表されます。このため、県民経済計算は、他の経済統計に比較して速報性に欠け、特にリーマンショックのような大きな経済変動や大規模災害のような社会変動などには即応できない弱点があります。 しかしながら、公表される県民経済計算は、法人、個人を含めた県民の経済活動の諸側面を、様々な統計資料を使用して県民経済計算の概念に従って加工、組み立てて作成された総合経済指標であり、その結果は地域経済全体を表している唯一の指標といえます。 これにより、時系列での分析、他県との比較などを通じて県経済の評価、特徴の把握などが行え、これが行政、企業、各種団体などの様々な活動や施策、経済活動を基礎の部分で支えるものとなっています。 この県民経済計算が、さらに様々な分野でお役に立てるよう、今後とも工夫を重ねていきたいと考えています。 |