厚生部における人材確保対策(その2)
|
1.はじめに少子高齢化が進行し、労働力人口の減少が見込まれる中で、福祉・介護サービスに対するニーズは、ますます多様化・高度化しており、これらのニーズに対応できる人材を、質・量の両面から、安定的に確保していくことが求められています。 しかしながら、(全国的に)福祉・介護職は、他の職種と比べ、給与水準が低いこと、身体的・精神的な負担が大きいこと、さらに3K職場といったイメージがあること、などから離職率も高く、人材の確保・定着が困難な状況にあります。 本県においても、福祉・介護職の有効求人倍率は、一時期からは落ち着いてはいるものの、依然として高い水準で推移していますし、県内の介護福祉士養成校の入学者数も平成15年をピークに減少しており、将来の福祉・介護人材の不足が危惧されています。 このような状況の中、富山県では平成20年4月に「富山県福祉人材確保対策会議」を立ち上げ、関係機関・団体と連携して、福祉・介護人材確保のための方策を検討するとともに、総合的な対策として「福祉人材確保緊急プロジェクト」に取り組んでいますので、その内容について紹介いたします。 |
2.福祉・介護人材の現状と課題について(1)介護福祉士養成校入学者数の減少県内の介護福祉士養成校の入学者数は、平成15年をピークに減少に転じ、平成20年には入学定員に対する入学者数の割合である充足率が過去最低の62.4%となっております。その後、微増傾向となっていますが、依然、極めて低い水準(平成22年:64.7%)にあります。
富山県内の介護福祉士養成校入学者数・充足率の推移
 (2)依然として高い介護職の有効求人倍率県内の介護関連職種(常用パートを含む)の有効求人倍率は、平成20年10月に2.24倍と極めて高い水準となった後急速に収束し、平成22年4月には1.12倍となっていますが、全職種の有効求人倍率(0.62倍)と比較すると、依然として高い水準にあります。
県内の有効求人倍率の推移(富山労働局調べ)
 (3)低い給与水準給与水準について、介護施設で働く介護職員(施設介護員)の年間収入を全職種と比較すると、若年層(20〜24歳)においては男性で388千円、女性で74千円低くなっています。 また、中堅層(35〜39歳)においては更に格差が拡がり、男性では1,542千円、女性では810千円低くなっています。 同様に看護師と比較しても中堅層では、男性で974千円、女性で1,652千円それぞれ低くなっており、同じ医療・福祉系の職種と比較しても低い給与水準にあると言えます。
職種・性・年齢階級別
決まって支給する現金給与額及び年間賞与その他特別給与額(全国) 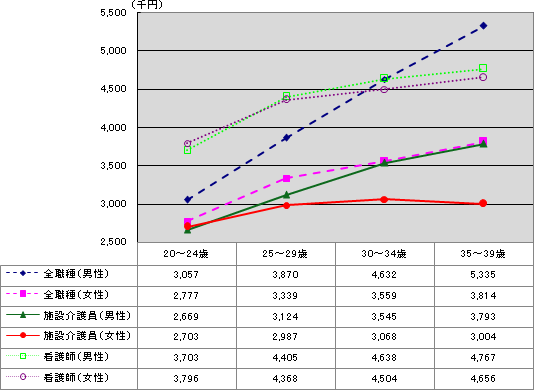
資料:「平成21年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)」 ※事業所規模10人以上の常用労働者を雇用する事業所に雇用される常用一般労働者について年収を推計。 ※一般労働者とは短時間労働者以外の者をいう。 (4)高い離職率介護員(訪問介護員・介護職員)の離職率は、全労働者と比較すると、平成17年においては5.1ポイント、平成20年においても4.1ポイント高く、継続して高い水準で推移しています。 特に就職後3年未満で離職する割合が高く、平成20年には75.5%となっています。
介護員(訪問介護員・介護職員)の離職率の推移(全国)
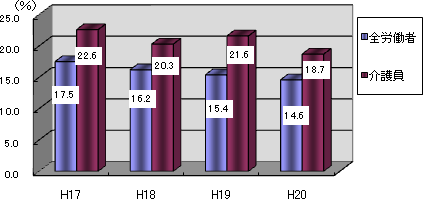
※介護員は「介護労働実態調査((財)介護労働安定センター)」より
就業年数別介護員(訪問介護員介護職員)離職者の内訳(全国)
(%) 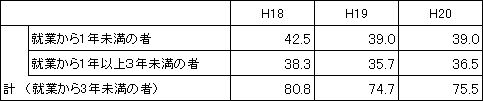
資料:「介護労働実態調査((財)介護労働安定センター)」より |
3.県の人材確保に対する取り組みについて
|
| 目的: | 中高校生・保護者等に対し、福祉の仕事の使命感・充実感を伝え、福祉職場の魅力を知ってもらうとともに、進路指導担当教員に福祉職場への理解を深めてもらう。 |
|---|---|
| 対象: | 中学生、高校生、保護者、高校進路担当教員 |
| 内容: |
  中高生の職場体験 |
| 目的: | 「若い世代が福祉・介護の仕事に関心を持つ⇒学校で学ぶ⇒実際に働く」といった一連の流れをつくっていくための「専門員」を各養成施設に1名配置し、福祉・介護の仕事の魅力を伝達し、将来的に福祉・介護の仕事の選択を促すよう相談・助言、指導等を行う。 |
|---|---|
| 対象: | 定員に対する充足率が原則6割未満の介護福祉士養成施設 |
| 内容: | ア)中学校・高校等を訪問し、福祉・介護の仕事や魅力を紹介する。 イ)中・高校生、家族、教員の相談に応じ、助言・指導を行う。 |
 福祉職場説明会 |
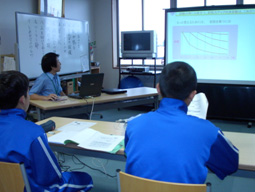 14歳の挑戦 |
(2)教育・養成
福祉を目指す人に対する教育・養成を目的として実施している事業としては、失業者を介護従事者として雇用し、介護スキルを習得させる「介護サービス支援ステーション運営事業」や、「介護福祉士等修学資金貸付事業」等を実施しています。
特に働きながら介護資格(介護福祉士等)を取得させる「介護サービス支援ステーション運営事業」については、これまで142名(平成22年6月30日現在)を雇用するなど一定の成果を上げています。
| 目的: | 介護福祉施設において失業者等を介護従事者として新たに雇用し、介護業務に従事させるとともに、働きながら介護資格(介護福祉士またはホームヘルパー2級)を取得させる事業を委託することにより、介護に必要な知識や技能を身につけた人材を養成・確保するとともに、雇用の創出と介護サービスの質の向上を図る。 |
|---|---|
| 委託先: | 介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所を運営する法人 |
| 雇用目標: | 平成22年度 計180名 |
| 目的: | 介護福祉士養成施設又は社会福祉士養成施設に在学する学生に対し、修学資金の貸付を行い、養成施設卒業後に県内において5年間介護等の業務に従事した場合に返還を全額免除するもの。 |
|---|---|
| 貸付対象: | 介護福祉士・社会福祉士養成施設に在学する学生 |
| 貸付金額: | 月額5万円、入学準備金20万円、就職準備金20万円 |
| 貸付人数: | 25名 |
| 貸付利子: | 無利子 |
(3)確保
福祉・介護人材の就労を支援する事業としては、福祉職場への就職希望者に対し、あらかじめ職場体験を行う機会を提供し、実際の職場の雰囲気やサービスを直接知ってもらう「福祉職場体験事業」や介護福祉士等の資格を持ちながら、福祉・介護分野に就業していない潜在的有資格者の再就業のための研修を実施し、福祉・介護職員の人材確保につなげる「潜在的有資格者就業支援研修」の実施等があります。
| 目的: | 人材センターやハローワーク等での職業紹介の際に、職場体験を併せて仲介するもの。就職希望者には、あらかじめ職場体験を行う機会を提供し、実際の職場の雰囲気やサービスを直接、知ってもらい、また、事業者には就職希望者のパーソナリティを理解してもらうことにより、就職希望者と事業者が求める人材像とのギャップを埋め、円滑な人材参入を促進する。 |
|---|---|
| 対象: | 福祉職場就職希望者(50人程度) |
| 内容: | 福祉・介護事業所の職場体験(一人あたり7日間程度) |
| 目的: | 介護福祉士等の資格を有しながら福祉・介護サービスに就業していない潜在的有資格者に対する再就業のための研修を実施し、福祉・介護分野への新たな人材の参入・参画を促進することを目的とする。 |
|---|---|
| 対象: | 介護福祉士等の有資格者で介護分野に未就業の者 |
| 内容: | 介護に関連する知識・技術や介護の現状と課題等に係る研修の実施 |
  福祉・介護サービスチャレンジ研修 |
(4)定着
福祉・介護人材の定着を図り、人材の質の確保を目的とする事業としては、人材定着支援アドバイザーが、職場訪問や窓口相談等を行うことにより、就職して間もない従事者に職場の労働環境、人間関係等に関する様々な助言を実施する「福祉・介護人材定着支援アドバイザー事業」や、若手介護職員の身体的・精神的不安等による離職を防止する「介護職員フォローアップ研修会・交流会」を実施しています。
| 内容: | アドバイザーが、職場訪問や窓口相談を行うことにより、職場の労働環境、人間関係等に関し若手職員に助言。また、訪問・相談等の結果を踏まえ、労働環境の整備等について、事業者に対し助言・指導。 ・対象:施設等に従事する介護職員 ・相談窓口の設置:週2日 定時に実施 ・電話相談には随時対応 |
|---|
 新任介護職員基礎研修会 |
| 目的: | 若手介護職員の身体的・精神的不安等による離職を防止する。 |
|---|---|
| 対象: | 就業3年未満の介護職員 |
| 内容: | 腰痛対策やメンタルヘルス等の講義、交流会 |
(5)給与水準の改善について
福祉・介護人材の職場定着のためには、根本的には給与水準の改善が必要となりますが、県では、国に対して、介護報酬の引き上げについて強く要望してきました。
こうしたこともあり、平成21年度から介護報酬が3%引上げられ、さらに介護職員の賃金改善に充当するための資金が、職員一人当たり1万5千円程度、交付される処遇改善措置がとられました。
| 概要: | 介護職員の処遇改善のため、県に基金を設け、介護職員の賃金改善を行う事業者に対し、介護報酬とは別に「介護職員処遇改善交付金」を交付 |
|---|---|
| 交付額: | 介護職員常勤1人当たり月額1.5万円の賃上げに相当する額 |
| 実施期間: | 平成21年10月〜24年3月 |
4.おわりに以上の他にも、県では、関係機関・団体と連携して多くの事業を実施していますが、高齢化の進展に伴い、今後ますます福祉・介護人材の需要が高まることが予想されます。県としては、引き続き、「富山県福祉人材確保対策会議」における意見や議論なども参考としながら、福祉・介護人材の定着支援や福祉職場のイメージアップなど、意欲と能力のある人材の確保に向けた実効性のある対策を講じ、県民誰もが安心して暮らせる社会づくりに取り組んでいくこととしています。 |