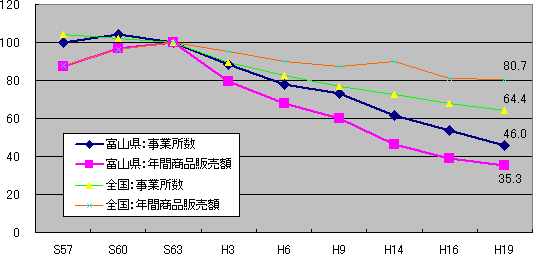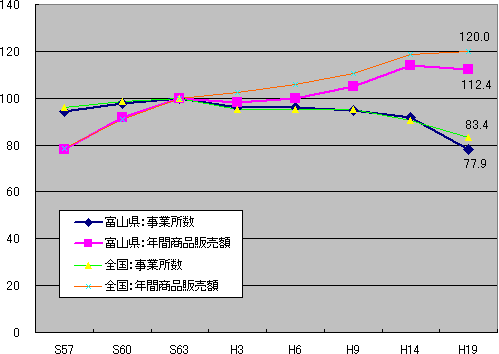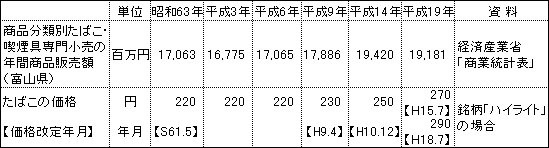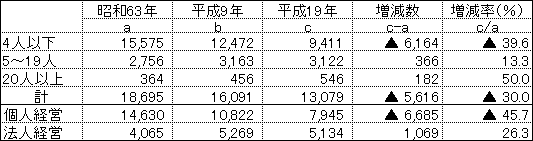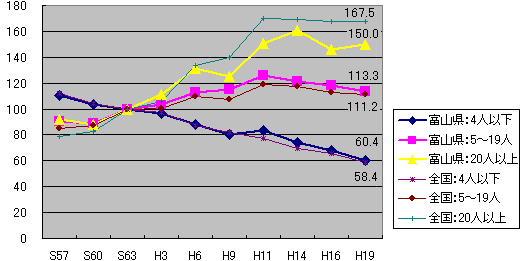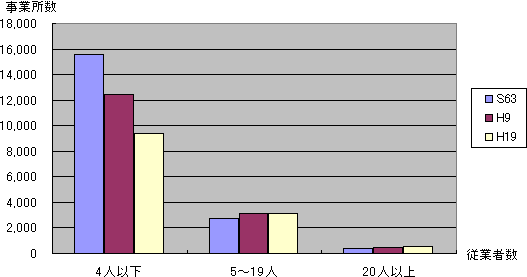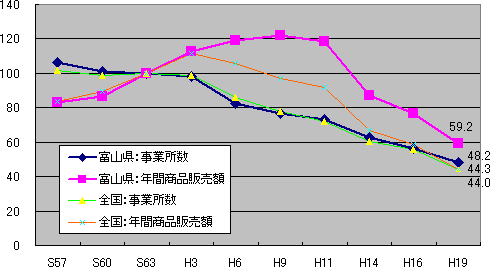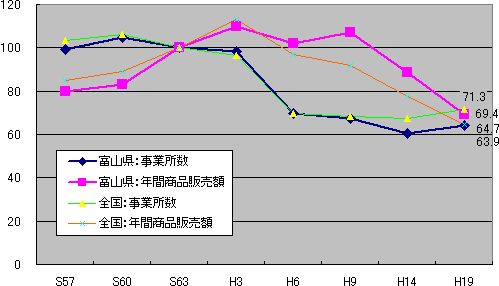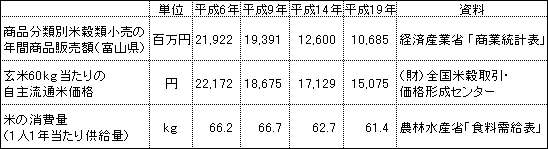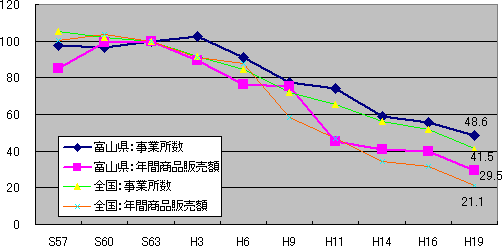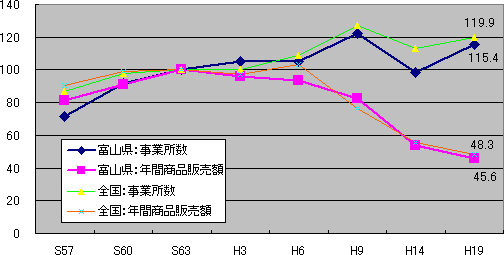商業統計(小売業)からみた富山の姿(1)総合県税事務所自動車税センター(前統計調査課)山
|
はじめに商業統計調査は、我が国の商業の実態を明らかにすることを目的として、「卸売・小売業」に属する事業所を対象に昭和27年に開始し、平成9年以降、5年毎に実施しています。また、その中間年(調査の2年後)には簡易調査を実施しています。 平成19年6月1日現在で実施した商業統計調査結果をみると、富山県の小売業は、前回(平成16年)と比較すると、事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積ともに減少しています。(表1) また、事業所数は昭和54年以降、減少傾向にあり、年間商品販売額は平成9年までは増加したものの、その後は減少しており、全国と概ね同じ動きをしています。(図1) 平成19年調査の20年前に当たる昭和63年を100とすると、平成19年の事業所数は70.0(全国70.2)と3割の減少、年間商品販売額は111.1(同117.3)と約1割の増加となっています。 本稿では、商業統計調査の結果を用いて、次の観点から富山県小売業の動向をみてみます。(IV 業態別の動向については、次号に掲載)
I 全国順位でみる富山
表1 平成19年商業統計調査結果:小売業
図1 事業所数、年間商品販売額の推移(S63=100)
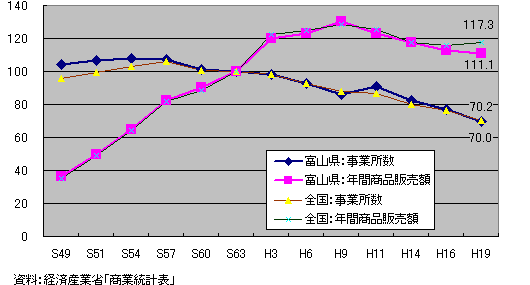
【小売業とは】
【事業所(商業事業所)とは】 【年間商品販売額とは】 【売場面積とは】 |
I 全国順位でみる富山富山県の小売業の特徴を探るため、人口当たりの事業所数及び年間商品販売額の全国順位を調べたのが表1-1です。 この結果、富山県では、 以下、平成19年の全国順位を取り上げ、その背景の一端について推察してみます。 1 女性ファッション関連産業分類の人口当たり事業所数は、婦人服小売業が第1位、呉服・服地小売業が第2位、化粧品小売業が第3位となっています。 また、商品分類の人口当たり年間商品販売額は、呉服・服地が第3位、婦人服、化粧品が第12位となっています。 富山県の女性の就業率は全国第5位(平成17年国勢調査 総務省)、共働き率は全国第3位(同)、勤労者世帯の実収入は全国第6位(平成20年家計調査年報 総務省)、勤労者世帯の消費支出は全国第1位(同)と高くなっています。 女性の社会進出が進み、しっかり稼いで自分のために使うことや冠婚葬祭など人付き合いに必要なものを買ってきたことが商業統計に表れているのではないかと思われます。 2 住宅関連産業分類の人口当たり事業所数は、建具小売業第1位、宗教用具小売業と骨とう品小売業が第2位、家具小売業第3位、畳小売業第4位となっています。 商品分類の人口当たり年間商品販売額は、建具は第2位、骨とう品は第4位、畳は第6位、宗教用具と中古品は第8位、家具は第9位となっています。 富山県の持ち家率(住宅に住む一般世帯に占める持ち家世帯の割合)は全国第1位(平成17年国勢調査 総務省)、3世代同居世帯の割合(一般世帯)は全国第5位(同)、1住宅当たりの居住室の畳数(専用住宅)は全国第1位(平成20年住宅・土地統計調査 総務省)となっています。 かつては「家を建てたら一人前」とも言われ、富山県民は蓄えを住居に係る経費に充てるなど、「家」にずいぶんこだわりを持っていることが商業統計からも読み取れます。また、富山県は現在も全仏教寺院の70%を真宗寺院が占めており、真宗王国と呼ばれるほど浄土真宗が大変盛んな地域であることもこの要因の一つであると思われます。 3 医薬品関連産業分類の人口当たり事業所数は、医薬品小売業(調剤薬局を除く)が第1位、商品分類の人口当たり年間商品販売額は、一般用医薬品小売が第4位となっています。 また、富山県の医薬品生産金額は全国第4位(平成19年薬事工業生産動態統計調査 厚生労働省)、配置用医薬品生産金額は全国第1位(平成16年薬事工業生産動態統計調査 厚生労働省)です。 “売薬さん”(配置販売従事者)は、「富山のくすりやさん」と親しまれ、得意先に薬を預けておき、後で使った分の代金をいただく「先用後利(せんようこうり)」といわれる行商商法によって、全国各地に家庭薬を届けてきました。“売薬さん”をはじめ、「富山のくすり」を担う人材の育成や医薬品の開発と品質の向上に努めてきたことが、結果に表れていると推察されます。 表1-1 産業分類別・商品分類別人口当たり事業所数及び年間商品販売額の全国順位
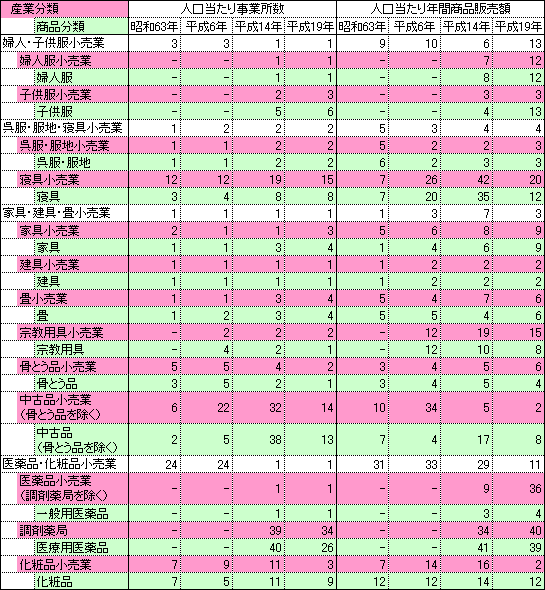
(注)表中 - は調査当時、産業(商品)分類されていないものである。 【産業分類、商品分類とは】
この事業所は、産業分類では年間商品販売額の最も多い呉服・服地小売業に格付けされ、事業所数1、年間商品販売額1,800万円として計上される。
一方、商品分類では商品別に事業所数が計上され、延事業所数は3となる。
|
II 規模別の動向
|
| 昭和33 年 | 百貨店法施行 | 百貨店の新設を規制 |
| 昭和49 年 | 大規模小売店舗法(大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律)施行 | 大型小売店の出店を規制 |
| 昭和54年 | 大規模小売店舗法改正 | 規制強化(調査対象面積を従来の1,500㎡以上に加えて、500㎡以上を規制の対象とする) |
| 平成元年〜 | 国内外から大規模小売店舗について規制緩和の要求 | |
| 平成4年 | 大規模小売店舗法改正 | 規制緩和(これまで商工会議所(商工会)に置かれ大型店の出店を扱っていた商業活動調整協議会が廃止され、出店調整期間を1年以内に短縮) |
| 平成12年 | 大規模小売店舗法の廃止、大規模小売店舗立地法の施行 | さらに緩和( |
| 平成19年 | 改正まちづくり3法(大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、改正都市計画法)の施行 | 郊外出店を規制 |
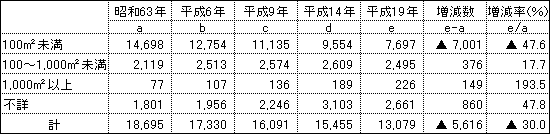
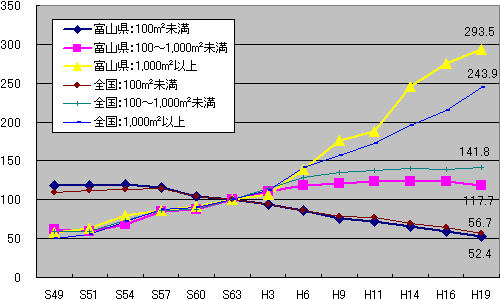
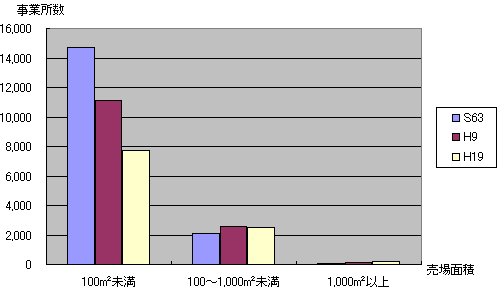
III 販売環境の変化による動向
|
| 平成15年5月 | 健康増進法第25条による受動喫煙の防止 |
| 平成15年7月 | 「富山市まちの環境美化条例」施行−市内の指定地域での歩きたばこやポイ捨てを罰則付きで禁止 |
| 平成18年4月 | 禁煙治療の保険適用が制度化(喫煙は病気との観点を導入) |
| 平成18年6月 | JR東日本が平成19年春から新幹線及び管内を相互発着する特急列車を全面禁煙すると発表 |
| 平成20年7月 | 未成年の喫煙防止対策の一環として、たばこ自動販売機用成人識別カード「タスポ」導入 |
| 平成20年11月 | 富山県庁本庁舎の「建物内禁煙」の実施 |
| 平成22年2月 | 公共の場の全面禁煙を厚生労働省が自治体に通知 |
国民健康栄養調査(厚生労働省)による喫煙率をみると、平成元年では男性55.3%、女性9.4%、平成20年では男性36.8%、女性9.1%となっており、それぞれ18.5ポイント、0.3ポイント低下しています。
たばこ・喫煙具専門小売業の事業所数は、産業分類別で平成19年は262事業所で、昭和63年の569事業所と比較すると、半減(▲307事業所減、▲54.0%減)しています。
これは、経営者の高齢化、喫煙に対する厳しい風潮など複合的な要因で閉店を余儀なくされているものと思われます。
一方、年間商品販売額は、商品分類別で平成19年は191億8100万円で、昭和63年の170億6300万円と比較すると、約1割(21億1800万円増、12.4%増)の増加となっています。
喫煙者が減少しているにもかかわらず、商品分類別の年間商品販売額が増加したのは、たばこ価格の上昇(例えば銘柄「ハイライト」の場合、昭和61年5月の220円から平成18年7月の290円へと31.8%増)が一因となっていると考えられます。(図3-3、図3-3a、表3-3)