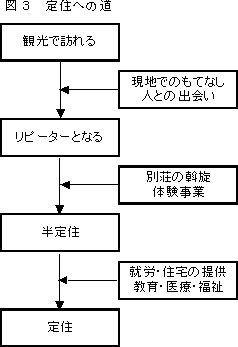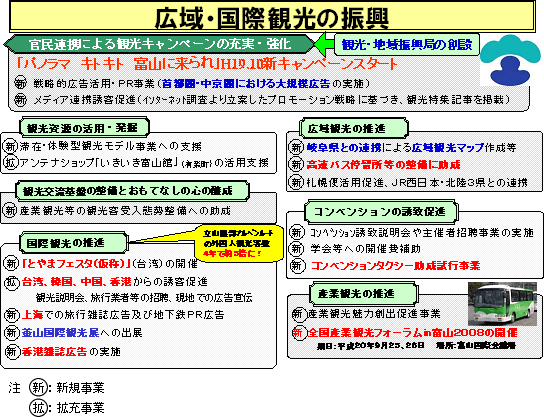人が動くということ−観光・地域振興局誕生−富山県観光・地域振興局地域振興課
|
1.はじめに本格的な少子・高齢化の進展、人口減少時代の到来、高速交通体系整備に伴う地域間競争の激化に対処するとともに、富山県の魅力をさらに高め、全国や海外に強くアピールしていくためには、観光振興・交流人口の拡大、定住・半定住の促進に、より積極的に取り組んでいくことが求められている。 このため、県では、平成20年4月1日に、新たに「観光・地域振興局」を設け、 |
2.観光・地域振興局が誕生した背景(1)人口減少・高齢化社会(成熟社会)の到来図1のように、富山県の人口は、国勢調査ベースでは、平成7年の1,123千人をピークに減少しており、国立社会保障・人口問題研究所の推計(中位推計)によれば、平成47年には880千人と平成17年に比べ20.9%減少すると予測されている。ただし、65歳以上の高齢者はその間58千人増加し全人口の36.0%となる。一方15歳〜64歳の生産年齢人口は△223千人と大幅に減少し、労働生産性の著しい向上がない限り、経済は成熟(停滞)〜縮小に向かうといえる。 図1 富山県年齢階級別人口の推移と推計(千人) 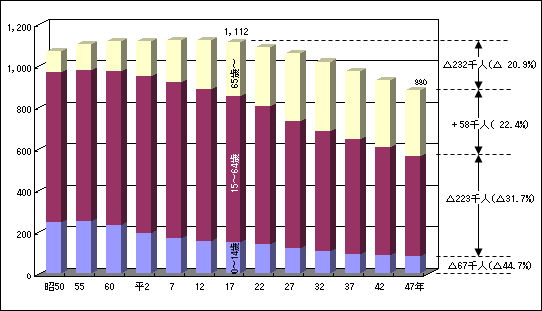 生産年齢人口の推移をもう少し詳しく見たものが図2である。(図は、たとえば、平成7年に5〜9歳だった人は10年後の平成17年に15〜19歳となっており、この集団が10年間で男性1,713人、女性2,112人減少したことを表している。) この間の死亡率は極めて低いため、その差はほぼ社会増減と見ることができる。富山県の場合、大学進学時と大学卒業時に人口が流出する。その後、男性は半数程度が戻ってくるものの、女性は4分の1程度しか戻ってこない。この結果、人口の減少は、出生率の低下による人口減に加え、社会移動による人口減が加わることとなる。 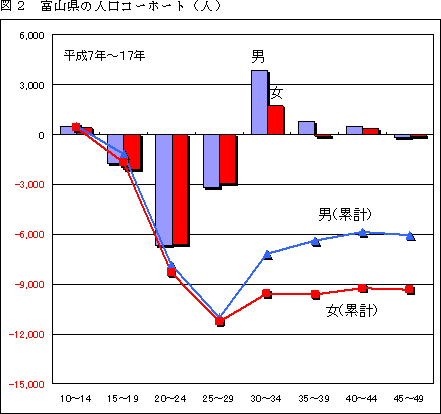
注 コーホート:ある一定の期間に出生した個人の集団 |
||||||||||
(2)地域間競争の激化表1 高速交通網の整備状況
表1は、都道府県の高速交通網整備の現状である。高速道路がつながっていない道県は、北海道、鳥取、島根、沖縄の4つ、空港のない府県は、関東や近畿周辺の府県に限られている。新幹線についても、過半数の都府県に新幹線の駅がある。まさに日本全国フリークエントサービスである。飛行機を使えば、全国どこでも同じような時間に到達することができる。料金も、早期割引運賃を使えば全国ほぼ変わらない。 一方、日本経済の成熟化が進み、かつてのような経済成長が見込めない現在では、少ない追加のパイの奪い合いにならざるを得ない。 また、国際航空路に関しても、韓国のソウルへの定期便を有する都道府県は24あり、海外との交流に関しても特段の優位性が薄れている。 このような状況の中、各都道府県は、それぞれ知恵を絞って施策展開を図り、地域間競争を戦っている。 |
||||||||||
(3)交流から定住へ
|
||||||||||
3.新たな時代に対応するための施策群アメリカの経済学者フィッシャーは、貨幣数量説を証明するために、次の方程式を生み出した。 MV=PT(M:貨幣の量 V:貨幣の流通速度 P:物の価格 T:物の量) 富山県の場合、第二次産業を中心として獲得された付加価値(M)は大きいものの、貯蓄率が高く消費が少ないためVが小さく、結果としてストックとしての富ほどにフローとしての消費活動が喚起されず、一人当たりGDPの高さに比べ物やサービスの流れが少ない。 この貨幣方程式を、マンパワーを使って作ってみよう。 MmVm=PT(Mm:マンパワー Vm:人の流動 右辺は同じ) ここで、左辺を、定住人口(m1)と交流人口(m2)に分ける。 MmVm=Mm1Vm1+Mm2Vm2=PT 観光・地域振興局は、まさにマンパワー方程式の左辺を拡大するための施策を展開していくために作られたものである。 それでは、ここから、それぞれの部門別に20年度予算に盛り込まれた事業を紹介していく。 (1)観光戦略図4は、国土交通省が実施した「宿泊旅行統計調査」による都道府県別の宿泊者数である。宿泊者には観光客以外にビジネス客なども含まれるが、広い意味での交流人口を把握する資料である。 富山県は38位となっている。これは、富山県が東京、大阪、名古屋の日帰り圏にあるため、ビジネス客などの宿泊需要が小さいことも要因として考えられるものの、まだ宿泊客を増やす余地が大きいことを示している。 ※表をクリックすると大きく表示されます 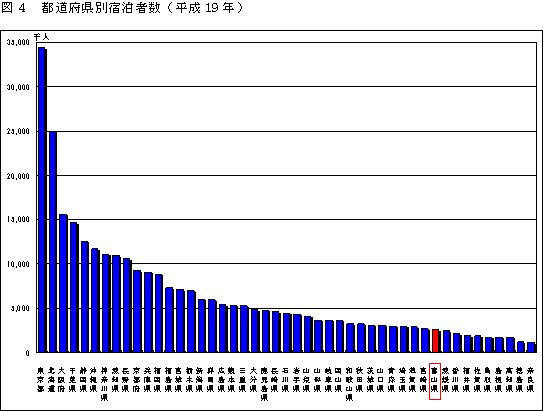
一方、(財)日本交通公社が、全国の観光資源を独自に評価した「観光資源評価台帳」に記載された観光資源数(図5)によれば、富山県の自然資源数は全国第5位となっており、自然をアピールする観光資源には恵まれていることがわかる。富山県は、工業県として発展したことなどから、自分のことをアピールするのが苦手であるとも言われているが、せっかくの観光資源を積極的に活用していけば、交流人口の増加を図ることができる条件を備えているともいえる。 ※表をクリックすると大きく表示されます 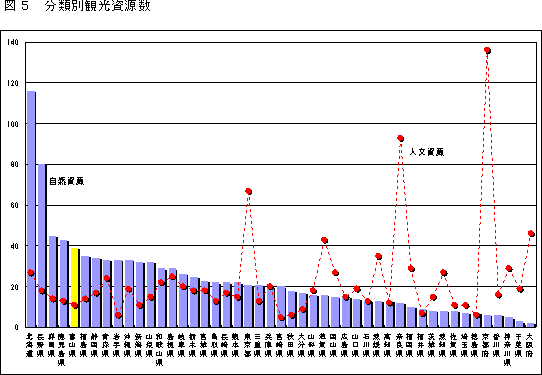
県では、昨年10月に、昭和58年から続いた「いい人、いい味、いきいき富山」に代わる新しい観光キャンペーン「パノラマ キトキト 富山に来られ」をスタートさせ、下図のような施策展開を図ることとしている。 |
(2)地域ブランド戦略図6は、日本テレビ系列の日曜日朝の番組「遠くへ行きたい」で紹介された都道府県の回数を見たものである(沖縄については系列局がないことが関係していると思われる)。 首都圏や近畿圏近郊は「遠くへ‥」ではないため少ない。 ※表をクリックすると大きく表示されます 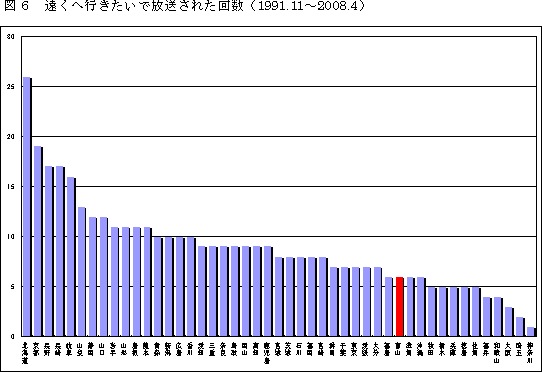
富山県は6回で34位タイであるが、このうち2回は2007年に放送されている。特に2007年7月22日放送は「新・富山名物 アラカルト」ということで富山の新たなブランドを紹介していた。 放送回数の多少は、視聴率を獲得できる地域の資源数、すなわち地域ブランドの量であると考えれば、富山はまだまだの感はあるものの、近年、ブランド力が向上しているとも見える。また、昨年から今年にかけてビール会社とタイアップした「ぶりしゃぶ」は、「富山は食べ物がおいしい」というブランドイメージを全国に広めることとなった。 富山県では、「富山ブランド推進本部」を設置し、さまざまな分野で富山をブランド化するための施策に取り組んでいる。 ※画像をクリックすると大きく表示されます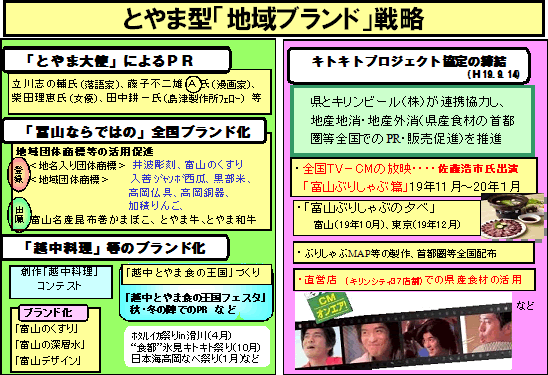 |
(3)定住・交流促進戦略観光戦略により、富山との交流を広め、ブランド戦略により富山県ヘの理解が深まることにより、富山県が「くらしたい国」として認識されていけば、富山への定住者が増えていくものと考えられる。 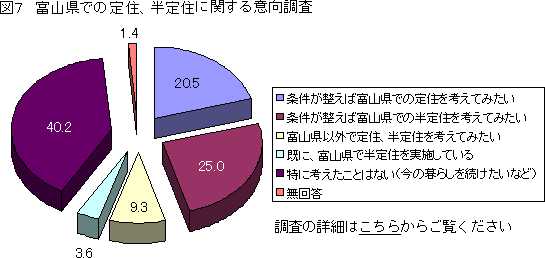 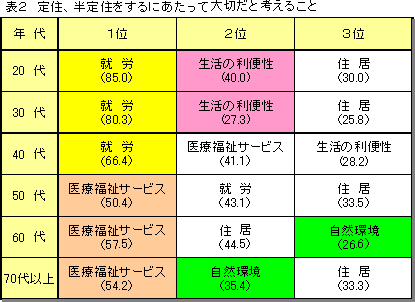
図7と表2は、富山県が平成18年に、首都圏・中京圏・関西圏の富山県出身者・富山県にゆかりのある人に対して行ったアンケートの調査結果である(回答数947)。 全体の半数近くが、条件が整えば、富山への定住若しくは半定住を考えてみたいと回答している。 また、平成19年に東京、大阪で開催された定住・交流に関するフェア会場でアンケートをとったところ、回答数170人のうち「富山県への移住や週末滞在等を実施してみたい」と回答した人が77人(45.3%)であったことから、富山県への定住に対する潜在的な需要はあるものと思われる。 このため、富山県では、平成19年7月に「くらしたい国、富山」推進本部を設置し、ホームページやパンフレットの発行による情報発信や、体験交流事業の実施などにより、富山への定住・半定住を進めていくこととしている。 (「くらしたい国、富山」のホームページはこちらからご覧ください) なお、表2に見られるように、定住、半定住にあたって考慮される条件は、年代別(ライフステージ別)に異なることから、20年度においては、これらに対応した施策を展開していく。 ※画像をクリックすると大きく表示されます 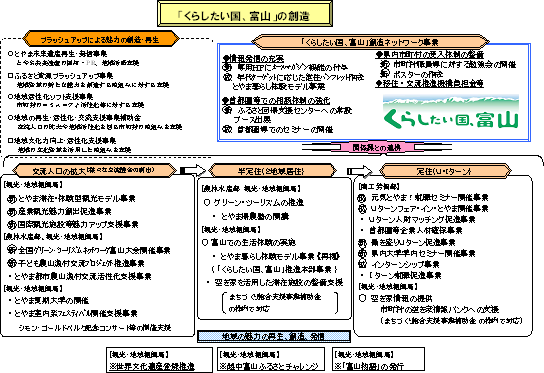 |
4 今後の展開手法観光、ブランド、定住・交流を担当するセクションが一つになった「観光・地域振興局」では、それぞれの垣根を越え、以下のような積極的な連携を図っていくこととなろう。 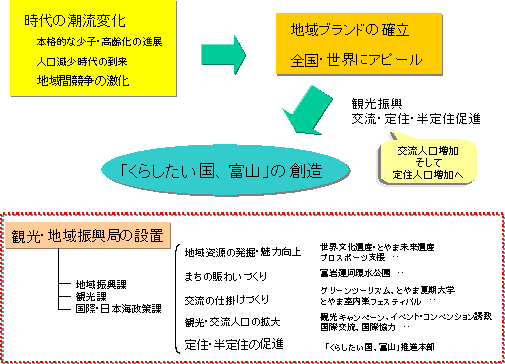 ※表をクリックすると大きく表示されます 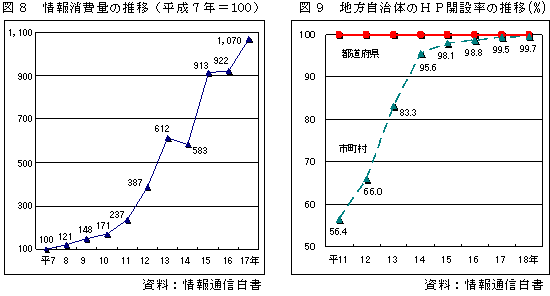 世は「情報化社会」ではなく、すでに「情報社会」である。図8のように、日本の情報消費量は10年間で10倍になった。地方自治体のほとんどがホームページを開設している(図9)。 人々が旅行に関する情報を入手する手段も、平成12年に11.2%だった「インターネット」が平成16年には26.0%となり、「旅行専門雑誌」と肩を並べるようになっている。 情報は、紙や電波媒体全盛期の「出せば見られるはず」(マス媒体、供給側の論理)から「見てもらう」(パーソナル媒体、需要側の論理)ことを意識していかなければならない。そのためには、量を増やすことと同時に質(適時性、正確性、付加価値性など)を高めていくことが大切だ。 観光・地域振興局では、観光〜交流〜定住といった流れをシステムとして提供し、行政が持つ情報の信頼性を生かした情報の提供を図っていく必要がある。 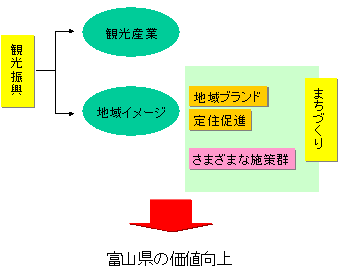 行政が行う観光振興には、観光産業振興の側面と地域のイメージ形成の側面がある。 行政が行う観光振興には、観光産業振興の側面と地域のイメージ形成の側面がある。
観光・地域振興局では、前者はもちろん、地域ブランドや定住促進サイドを含め、さまざまな施策群、そしてさまざまなセクターとの連携により、富山県全体の価値を向上させていくための施策を展開していくこととなる。 |