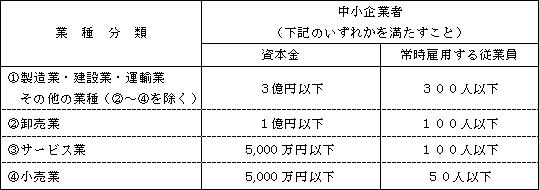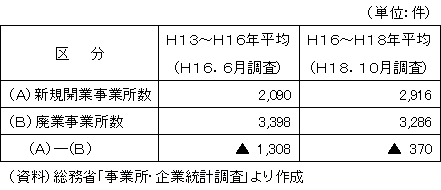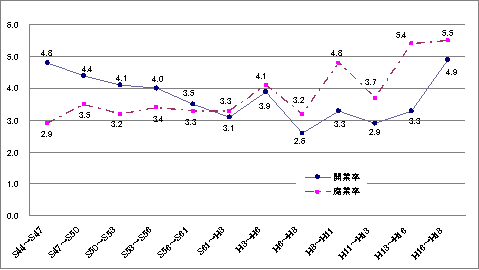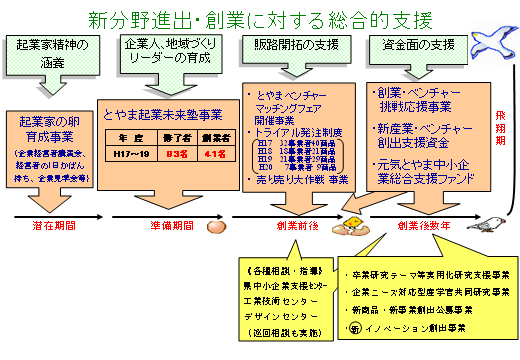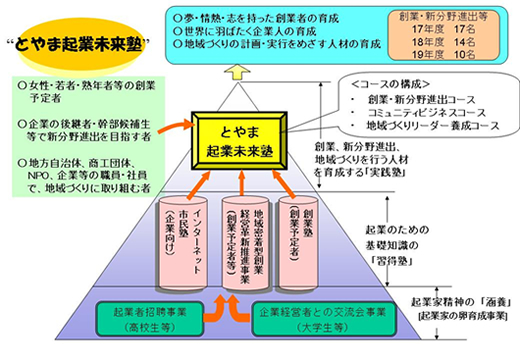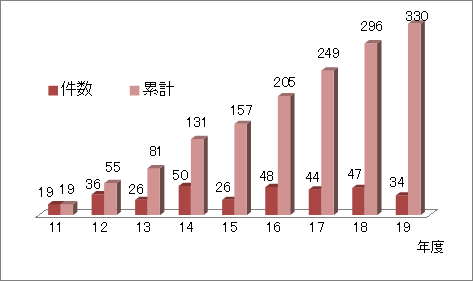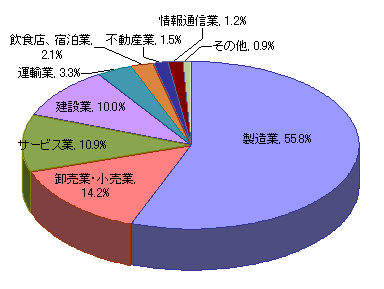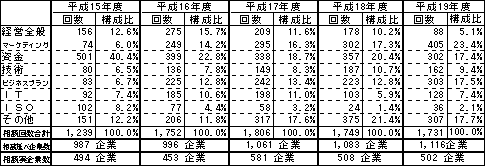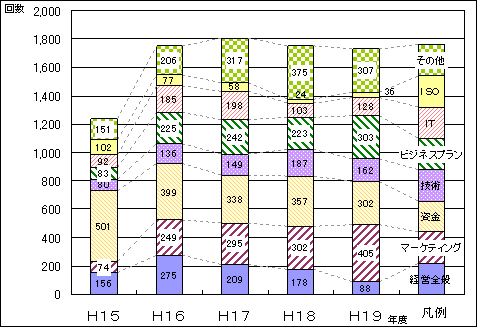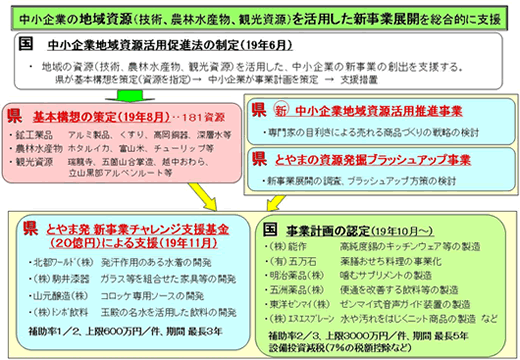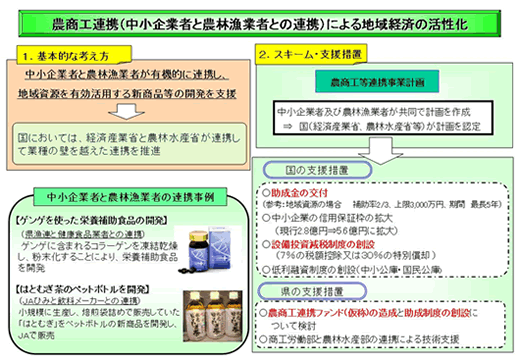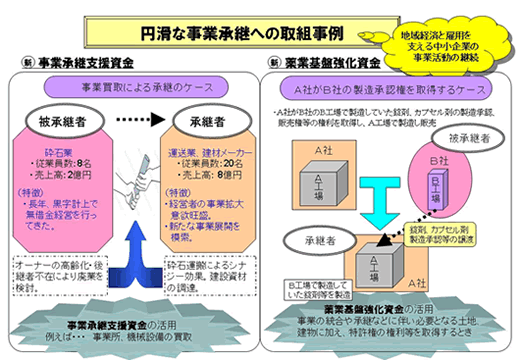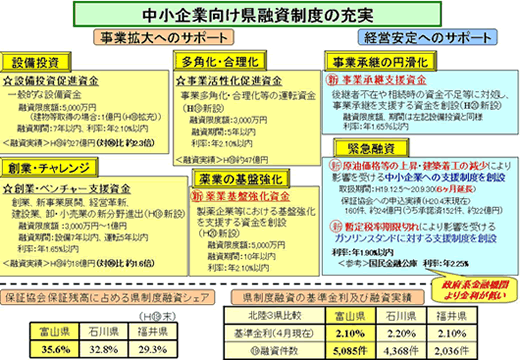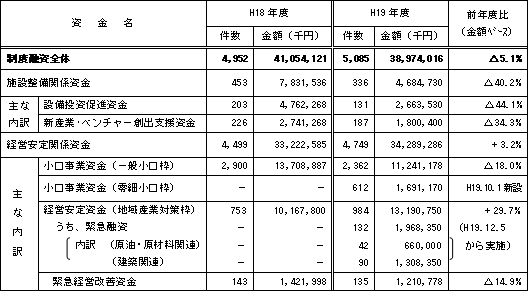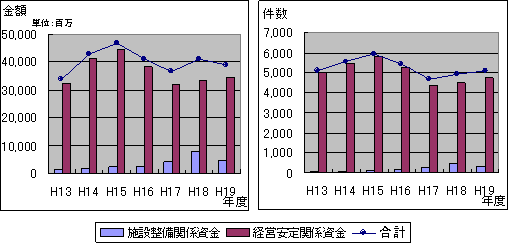富山県の中小企業支援施策について
|
1.はじめに中小企業は新たな産業を創出し、雇用を生み出し、地域経済社会を担う、いわば日本経済の屋台骨を支える存在である。 本県は製造業のウェイトが高く、アルミ金属、医薬品、機械工業の他、電子部品・デバイス・電子材料分野など日本海側屈指の工業集積を誇るが、大企業だけでなく、国際的にも高い評価を得ている技術力、開発力を持つ多くの元気な中小企業が存在している。
しかし、最近の経済情勢をみると、本県経済は緩やかな回復基調に足踏みが見られ、円高の影響や原油・原材料価格の高騰、改正建築基準法の施行後の建築着工件数の減少など、中小企業を取り巻く経済情勢は依然として厳しい状況が続いている。 経済産業省「中小企業白書 2008年版」によると、約4万3千社ある本県事業所の99.8%を中小企業が占めており、本県の産業・経済の基盤を支え地域の活性化を図るためには、中小企業の企業活力を高めることが大切である。 そのためには、中小企業が抱える課題に的確に応え、中小企業者自身による新たなチャレンジを積極的に支援していく必要がある。 本稿では、本県の前向きにチャレンジする中小企業に対する県の支援施策のうち、経営・事業運営支援分野について、紹介したい。
表1 中小企業基本法による中小企業の定義
|
3.新しい取組みへの支援(1)地域資源活用「中小企業地域資源活用促進法」に基づき、昨年度から取り組んでいる富山ならではの地域資源(産地の技術、農林水産物品、観光資源等)を活用した新商品開発等を促進するため、今年度は、専門家を招き、目利きを通した富山ならではの売れる商品づくりの戦略検討を行うとともに、引き続き、県が創設した「とやま発 新事業チャレンジ支援基金(20億円)」を活用して、中小企業の意欲的な取組みを支援していくこととしている。
「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」 181資源指定
※表をクリックすると大きく表示されます |
||||
(2)農商工連携さらに、中小企業者と農林漁業者とが連携した新商品、新サービスの開発・販売促進等の取組みを支援するため、先日、国会において農商工等連携促進法が成立したが、県としても、農商工連携による地域の企業の意欲的な取組みに対する支援制度について検討を進めていくこととしている。
※表をクリックすると大きく表示されます |
||||
(3)事業承継今、日本の企業の8割が後継者問題に悩んでいると言われている。中小企業経営者や従事者の高齢化が進行する中、後継者不足等により廃業する中小企業が増加し、雇用の確保や技術・ノウハウの承継に深刻な影響が出はじめている。 本年5月には、中小企業における経営の承継の円滑化を図るため、相続に伴う株式の分散を防止するなど、遺留分に関し民法の特例を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が成立した。 県では、今年度から、新たに県制度融資に「事業承継支援資金」を設け、後継者不在や相続時の資金繰りが困難なこと等により存続見通しがつかない中小企業の円滑な事業承継を図るため、金融面から積極的に支援していくこととしている。
※表をクリックすると大きく表示されます |
4.金融面での支援施策金融は、企業が円滑に企業活動を進める上で、大切な「血液」のようなものであり、県内中小企業の円滑な資金供給に努めている。
(1)県制度融資での支援金融面では、県制度融資において、業種、目的等を限定せず利用しやすくした「設備投資促進資金」を設けたほか、売上減少又は経常赤字の中小企業者を支援する「経営安定資金・地域産業対策枠」や事業の多角化、合理化等を支援するいわば前向きな運転資金である「事業活性化資金」を設けるなど、中小企業者のニーズに即した使いやすい制度となるよう常に見直しを行ってきている。
※表をクリックすると大きく表示されます |
||||
(2)19年度の利用実績平成19年度の県制度融資の利用実績は、制度融資全体で5,085件、約390億円の利用があり、利用件数では、小口利用が増えたため、対前年度比2.7%の増加、金額では同5.1%の減少となった。設備投資関係の融資額が同40.2%の減少となった一方で、運転資金関係は、件数、融資額共に前年度を上回っている。(表4、図5) これは、大型の設備投資が一段落したと考えられる一方、運転資金の需要が増えたということで、景気の停滞や原油高騰などにより、中小・零細企業の苦しい経営状況が反映されたものと考えられる。
表4 県制度融資の利用状況について ※表をクリックすると大きく表示されます |
||||
図5 県制度融資実績の推移
|
||||
(3)緊急融資の実施
 原油・原材料価格の高騰や住宅建設等の減少により経営上影響を受ける中小企業を対象に緊急融資を実施(H19.12.5〜) 原油・原材料価格の高騰や住宅建設等の減少により経営上影響を受ける中小企業を対象に緊急融資を実施(H19.12.5〜)
 暫定税率関連(石油商業枠)緊急融資の実施(H20.4〜) 暫定税率関連(石油商業枠)緊急融資の実施(H20.4〜)
道路特定財源の暫定税率期限切れにより経営上の影響を受けるガソリンスタンドを営む中小企業に対する運転資金の緊急融資を実施
|
5.おわりに企業の平均寿命は約30年と言われており、それ以上生きながらえるためには、様々な環境要因から、企業そのものが変革していく必要がある。
イギリスの社会学者のハーバード・スペンサーの言葉に「適者生存」 (survival of the fittest)という言葉がある。 これは、強いものや優秀なものが生き残るのではなく、その時の環境変化に適応し、自らを進化させてきたものだけが生き残るというものである。 この言葉はまさしく中小企業にピタリとあてはまると思われる。
中小企業は、大企業よりも小回りがきき地域に密着していることから、ひたむきな経営者が引っ張る企業は変化に対し機敏に対応することが可能である。それをアシストし、知恵を出し、企業のニーズにあった支援をしていくことが行政の大切な役割である。
この7月には日本海側と太平洋側をつなぐ人流・物流の大動脈である東海北陸自動車道が全線開通し、中京圏からの時間距離が短縮され、物流の変化や商圏の拡大が予測される。 また、あと7年後には北陸新幹線が金沢まで開業することにより、交流人口の拡大や観光面の活性化など県内の中小企業にとっても、ビジネスチャンス、大きな追い風となることが期待される。 今後も、関係機関とも連携しながら、富山の中小企業をどんどん元気にする一翼を担っていきたい。 |