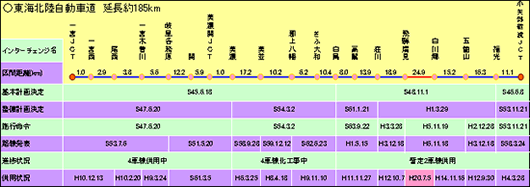東海北陸自動車道 全線開通への期待 (その1)
|
 平成20年7月5日(土)、東海北陸自動車道は、最後の未開通区間、飛騨清見インターチェンジから白川郷インターチェンジ間約25kmが開通することになり、これをもって、昭和47年の工事着手以来36年を経ていよいよ全線開通する。 本稿では、東海北陸自動車道の構想から開通までの歩みについてかいつまんで紹介する。 |
1)東海北陸自動車道構想東海北陸自動車道の構想は、主に名古屋側から持ち上がったようである。経済的な先進地であった名古屋側からは、現在の伏木富山港を名古屋の港として利用するために、東海地域と北陸地域の結びつきを強める必要性が古くから指摘されていた。 資料・「太平洋への道」より抜粋(昭和39年北日本新聞社発行) 昭和八年ごろ 岐阜大学小出保治教授 「東岩瀬に建設中だった運河を視察にいったことがある。当時、満州と日本の距離をどう縮めるかが課題だった。東京は新潟港を通じて大阪は舞鶴港を通じて満州との交流を考えていた。そこで私は名古屋は伏木、岩瀬港を利用すべきだと思った。そのためには富山・名古屋間の道路をよくする必要があった。」
名古屋市の戦災復興にあたった当時の同市技監田淵寿郎 「昭和十四年ごろ名古屋土木出張所長をしていて富山、石川、福井の各県をみて回り、将来の発展策は太平洋沿岸と日本海沿岸の都市が結びつくことで、そのためには富山港、伏木港は名古屋港の一つであり、名古屋港は富山港、伏木港の一つであるという考えをもった。おたがいにヒンターランド※ となるためには東海北陸道がぜひ必要であり、名古屋の都市計画はこのような構想をふくめて立案した。」 ※ ヒンターランド:港湾を経由して輸出入される貨物の発生源又は最終消費地
一方、北陸側では国道41号や国道156号など生活に密着した道路の整備が急務であり、東海北陸自動車道の必要性は名古屋側に比べると、さほど認識されていなかったようである。 |
2)高速道路建設の機運の高まりそもそも日本の高速道路建設は、昭和30年6月に「国土開発縦貫自動車道建設法案」が超党派の議員提出法案として国会に提出されたことに端を発す。 この法律は、国土の普遍的開発を目的として謳い、国会を含め社会的にも大変な議論を呼び、法案提出から2年近くを経て、昭和32年3月に可決、同年4月に公布施行されている。この後、東名高速道路の建設が徐々に進んでいく中で、各地において高速道路建設を希望する声がわき上がってきた。東海北陸自動車道も、その中の一つであった。 また、北陸において高規格道路の必要性が認められていくようになる契機の一つとして昭和38年豪雪があったようである。38年豪雪時には、現JR高山線だけが富山と他を結ぶ線として機能し、食料や資材等救援物資の搬入や富山からの製品出荷に役立ったことから、富山と太平洋側の高規格交通による結びつきの強化が必要であると認識されるようになっていったようである。 |
3)ルートの決定東海北陸自動車道が名古屋を起点とすることに異論はなかったが、北陸のどこに結ぶのかは当然問題になった。福井県、石川県、富山県、また富山県の中でも富山市、高岡市など色々な案が持ち上がったようである。この綱引きが実際どのようなものであったのかは、不明であるが、最終的に昭和38年5月17日付け「三県申し合わせ」が締結された。 三県申し合わせ
その後、昭和38年7月の建設促進同盟会総会において「いずれにも裨益する」道路として国道156号沿いの建設が決議され、現在のルートの概略が決定した。 |
4)ワイズマン報告以上のような経緯を経て、東海北陸自動車道の構想は、その概要が固まっていたが、建設に向けこれを後押ししたのがワイズマン報告である。 昭和39年4月に、アーネスト・ワイズマンを団長とする国連調査団が名古屋入りした。この調査団は、当時の建設省が愛知、三重、岐阜の三県を含む中京圏の開発計画について助言を得るために招聘したものだが、ワイズマンは中京圏ではなく、北陸地方も含めた中部圏を提言し、北陸と直結する内陸高速輸送網の必要性を強く説いた。中部圏は地理的に各地域の役割分担が可能であり、名古屋を中心とした各地域の開発を説くなど、現在の目で見ても参考になる。この報告を受け、東海地方では北陸への関心がますます高まったようである。 |
5)東海北陸自動車道建設法の成立このような状況下、昭和39年6月に「東海北陸自動車道建設法案」が議員立法として国会に提出された。この法案はあっさりと成立し、同年7月1日に公布され、東海北陸自動車道の建設に具体の筋道が付けられた。 |
6)建設の歩み−着工から全線開通まで−
東海北陸自動車道の建設は、昭和47年6月、一宮ジャンクション〜美濃インターチェンジ間32.4kmの施行命令から始まる。昭和39年の東海北陸自動車道建設法公布から8年での事業化であった。 昭和61年に岐阜各務原インターチェンジ〜美濃インターチェンジ間19.1kmが初めて開通し、その後も建設は着実に進んだ。平成4年3月には富山県内区間で初めて小矢部砺波ジャンクション〜福光インターチェンジ間11.1kmが暫定2車線で供用され、平成14年11月までに県内全区間が暫定2車線供用された。これにより、東海北陸道全線のうち、未開通区間は、飛騨清見インターチェンジ〜白川郷インターチェンジ間の24.9kmを残すのみとなった。 しかし、この区間は10本のトンネルがある典型的な山岳道路であり、中でも籾糠山(もみぬかやま)を貫く飛騨トンネルは、道路トンネルとしては国内2番目の延長10.7kmを誇り、大変な難工事となった。籾糠山の名のとおりの軟弱な地盤、最大土かぶり約1,000mの高い土圧、大量の湧水などの対策のため工事は難航し、平成9年7月の掘削開始から平成19年1月の貫通まで9年半の歳月を要した。 更に飛騨トンネルは、貫通後もトンネル内部で変状が発生し、追加の対策工事を要するなど最後まで全線開通に向けた関門として立ちふさがったが、この度、ようやく無事完成を迎え、東海北陸自動車道は、昭和47年の着工以来36年を経て平成20年7月5日全線開通することとなったのである。
飛騨トンネルの工事の詳しい状況は、中日本高速道路(株)のホームページに掲載されています。
http://www.c-nexco.co.jp/corp/construction/project/hida_tunnel.html
 今後は、富山県内を含む暫定2車線区間の4車線化が望まれるとともに、東海北陸自動車道が企業立地、物流、観光など様々な分野へ効果を発揮することに期待がかかる。 |
|
〔参考文献〕 ・ 道を拓く−高速道路と私− 全国高速自動車国道建設協議会発行 ・ 太平洋への道 北日本新聞社発行 |