産業用繊維の世界 −アパレルだけが繊維じゃない−富山大学経済学部教授 松井隆幸
|
1.はじめにみなさんは、「繊維」・「繊維製品」というと何を思い浮かべるでしょうか。ワイシャツ、ズボン、スカート、ブラウス、下着…いわゆる「衣料」(アパレル)ですよね。「待てよ、布団やカーペットも繊維じゃないか?」と思った人、鋭いです。これらも「家庭・インテリア用」という繊維製品の重要なカテゴリーです。ここでは、そのどちらにも属さない「産業用繊維」と呼ばれる「機械・建築等にも使われるような繊維」について、紹介していきます。 「繊維」と言うと斜陽・衰退産業として語られることが多く、日本では量的にも縮小しています。そして今日、量産品では中国、高級品ではイタリアが圧倒的な競争力を持っています。ただし、これは衣料用繊維について言えることであり、産業用繊維は、日本やその他の先進国でも年々その比重を拡大しているのです。 図1の化学繊維・合成繊維の用途別使用量を見てください。日本で加工される化学繊維や合成繊維のうち、衣料用は現在では30%以下です。アジアからの輸入品に押されて、その規模が縮小していることが背景にあります。これに対して産業用は年々比重を増し、衣料用を上回っています。 ただし、この統計から見えない点もあります。図に含まれない天然繊維は、衣料用の割合がずっと高くなります。逆に、やはり図にないガラス繊維や炭素繊維は、ほぼ全量が産業用です。また「家庭・インテリア」の中にも、私の考えでは産業用に入れたほうがよいものがあります。 「産業用繊維」の範囲は、必ずしも統計でいう「繊維産業」のとり方と一致しません。また、繊維のデータは、重量で量られることが多いのですが、炭素繊維など、軽量でも、価格・付加価値の高いものがあることも注意を要します。 いずれにせよ、まず「繊維イコール衣料」ではないことをご理解下さい。 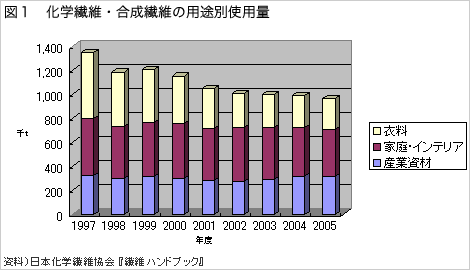
|
それでは産業用繊維とはどのようなものでしょう。衣料やインテリアに比べてイメージしにくいかと思います。ここには、自動車・機械・建築・医療・衛生など様々な分野で使われる繊維が含まれます。複合材料(繊維強化プラスチック)の分野に目をやると、航空・宇宙・エネルギーなどの分野も関係してきます。 「機械に使われる繊維」と聞いてもピンとこないかもしれません。身近なところで自動車を例にとりましょう(図2)。まずカーシートの多くは編物、シートベルトやエアバッグは織物です。また天井材やトランク材、ドアの一部には不織布が使われています。タイヤの内側にはタイヤコードという一種の織物がゴムを補強していますし、エアフィルター・吸音材・スピーカー材・ブレーキパットなどは機械の中に隠れています。またドアやフロント、部品の一部には後述の複合材料が使われることがあります。ある意味自動車も「繊維のかたまり」なのです。 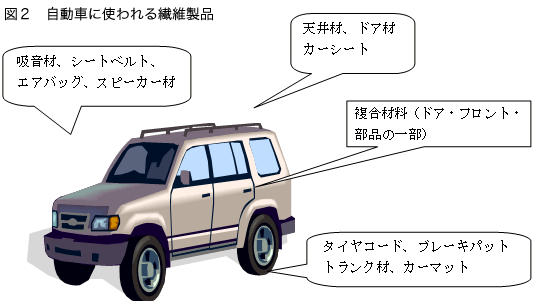 さて、自動車など交通機関の内装は図1では「インテリア」に含まれますが、私は産業用としての性格が強いと思います。産業用繊維が衣料やインテリアと異なるのは、ファッション・デザインよりも、強度・耐火・防水・耐薬品などの機能性が重視される点です。交通機関の内装も、耐火・耐光・防臭・タバコ防融(注1)といった機能性が強く求められます。多数の犠牲者が出た2003年の韓国の地下鉄火災の際には、地下鉄内装材の耐火基準が問題にされました。もっとも内装であるからには、ファッションも重要なのですが。 このほか繊維が多用されているのが、土木・建築の分野です。地盤・建造物・道路などの補強材、排水材、遮水材、防炎材、防音材、ゴムやセメントの補強材、ドーム建造物の屋根材などに広く繊維が用いられています。素材はポリエステル・ビニロン・アラミド繊維・炭素繊維・ガラス繊維など、形態は織物・ネット・不織布などがあります。東京ドームなどの屋根材のガラス繊維、橋脚補強用の炭素繊維(通常は鉄板ですが、重機が入れない地形の場合)も有名です。 中空糸膜(注2)など繊維の微細加工技術を液体フィルターに応用したものは浄水・純水製造・海水淡水化などの装置や、人工透析などの医療機器に応用されています。医療・介護分野では、この他抗菌・消臭・吸湿速乾などの機能を持つ繊維製品が開発されています。 また、きわめて高い強度をもつものを「スーパー繊維」と呼びます。その中でも広範に使われているアラミド繊維は、ブレーキパットや防護服、高強度ベルト、耐熱フィルターなどに用いられます(注3)。スーパー繊維にはこの他に、軽量の高強力ポリエチレン繊維、低吸湿性のポリアリレート繊維、耐薬品性に優れたフッ素繊維などがあり、3でみる炭素繊維もその一つです。 |
3.繊維に見えない繊維−不織布、複合材料、人工皮革−産業用繊維の中には我々の身の回りにあるのに、「繊維製品」として意識されないものがあります。たとえば不織布(注4)、複合材料、人工皮革です。 (1)不織布図3をご覧下さい。近年、日本の繊維産業が縮小する(増加傾向の産業用繊維や不織布自身を含む)中で、不織布は成長を続け、2006年には過去最高の生産量に達しています。この不織布、実はあちこちにあります(表1)。身近なところではお茶パックやクリーニング済み衣料の包装などに見られる、あの、布のような紙のような素材です。「紙」おむつ、ウエット「ティッシュ」など他の素材の名で呼ばれてきたのが知名度の低い一因でしょう。不織布は用途に応じて様々な機能を持っています。例えば手術用の布にはバクテリアや血液の飛散を防ぐ機能が必要ですし、耐熱性の必要な高温での集じんにはガラス繊維やフッ素繊維の不織布が用いられます。精密な機械をつくる現場では、ミクロのほこりを取り除くためのエアフィルターやワイパーに不織布が用いられます。 では不織布は普通の「布」とどう違うのでしょう?通常の「糸」は1本の繊維ではなく、多数の細かい繊維を集めたものです(糸のほつれた部分を思い出して下さい)。それを織ったり編んだりしたものが「布」です。不織布では糸の状態を経ずに、細かい繊維を、熱・接着剤・かぎ針・水流などを使ったり、融けた素材をノズルで噴出してコンベア上で成形したりして、いきなりシートにします。この結果、織物や編物を使った製品に比べて 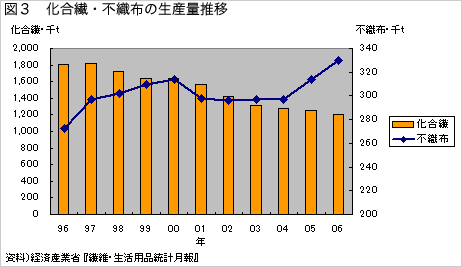 表1 不織布の用途例
資料)日本不織布協会、各社Web。
(2)複合材料次は複合材料です。複合材料とは、ガラス繊維や炭素繊維で補強された樹脂(プラスチック)を指します。 複合材料は「軽く、強く、錆びない」性質をいかして様々な分野で使われていますが、ほぼ全量が「産業用」です。コストの安いガラス繊維は、最も広く使われている複合材料用繊維です。日本では住宅向け中心でしたが、建築、自動車、電子部品等でも製品開発が進んでいます(表2)。光ファイバーの多くも一種のガラス繊維ですし、断熱材や音響絶縁材に使われるガラス短繊維もあります。 表2 ガラス繊維複合材料の用途例
資料)ガラス繊維協会Web、強化プラスチック協会「ここにも、あそこにもFRP」他。
炭素繊維はきわめて高い水準で軽さと強度を合わせ持っていますが、高価なので以前はスポーツ向け高級品や航空機の一部に限られていました。ところが近年になって航空機の構造材に広く使用されるようになり、機械・建築・エネルギーなどの用途も急速に広がり (表3)、量的にも拡大しています(図4)。価格次第ですが、燃料効率改善の要求から、今後、自動車での使用が広がるといっそうの需要拡大が期待されます。 表3 炭素繊維複合材料の用途例
資料)炭素繊維協会Web、強化プラスチック協会上掲資料他。
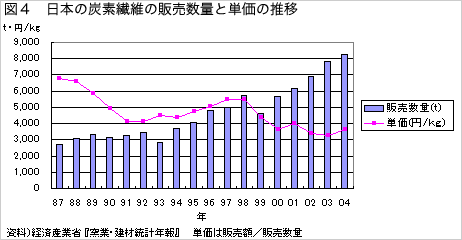 現在、量的に多いのは強度=「壊れ難さ」に優れるPAN系炭素繊維ですが、剛性=「変形し難さ」に優れるピッチ系炭素繊維も、工業用大型ロールや大型ガラス基板搬送アームなど「たわみ」や「振動」を避けたい工業部品に利用されています(注5)。 図1のところで、「ガラス繊維や炭素繊維は図にない(化学繊維・合成繊維に含まれない)」といいましたが、これらは産業分類では「繊維」にも入らずに、「窯業・土石」(セメント、板ガラスなど)に含まれます。さらに繊維そのままで製品になることはなく、強化繊維として樹脂と組み合わされて「複合材料」に加工されます。「複合材料」は、まず繊維に見えませんし、産業分類では「プラスチック製品」に含まれます。また前述のアラミド繊維も、しばしば複合材料に加工されて利用されます。 |
(3)人工皮革やはり繊維に見えないのが、次の人工皮革です。天然皮革、いわゆる本皮(ほんがわ)はコラーゲン繊維が微細な3次元構造をもっていて、通常の布をもとにした塩ビレザーや合成皮革とは、その触感に大きな差がありました。超極細繊維(注6)を3次元に絡み合わせた不織布を用いて、本皮に負けない触感を実現したのが、人工皮革です。 人工皮革の用途は衣料・靴・家具・カーシート・鞄・スポーツ用品などで、図1の「衣料」、「家庭・インテリア」、「産業資材」の3つの用途すべてにまたがっています。合成皮革より触感に優れ、本皮より手入れが容易という長所に加え、世界的な自然保護の流れの中でニーズが高まっています。たとえば欧米製の高級家具でも日本製の人工皮革の使用が広がっています。 |
4.衣料用繊維の技術と製品開発今日では日本や先進国の繊維産業の重要な柱である産業用繊維ですが、もともとは衣料用繊維の企業が新事業の一環として開発したものが多くを占めます。衣料製造の各工程と製品開発の技術関係を示したのが図5です。 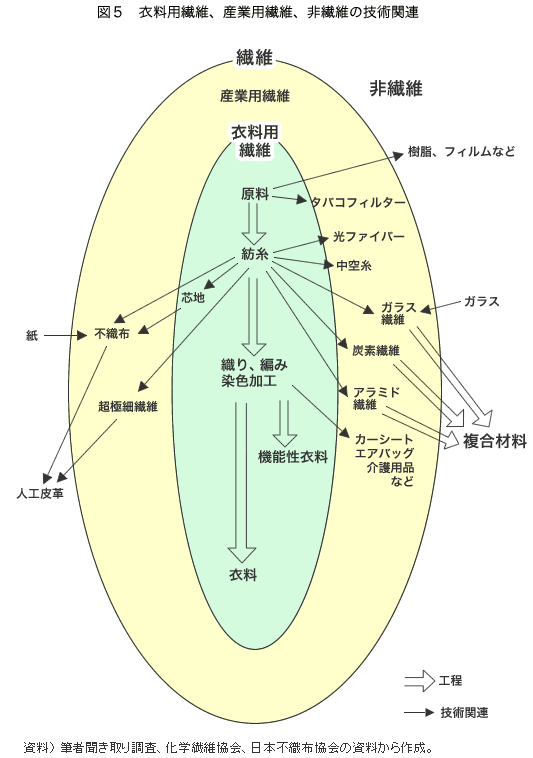 衣料製品ができるには、繊維の材料を合成する工程、合成した物質を細く長くする紡糸工程、紡績・撚糸などによって繊維を糸の形に集積させる工程、織り・編みなどを通じて布を作る工程、それを染色加工する工程、裁断・縫製により最終製品を作る工程があります。 まず、原料合成の技術からは、樹脂・フィルム・接着剤など様々な化学製品が生まれています。これが「非繊維」分野への展開であり、量的にはここが最大でしょう。糸を作る技術は、中空糸、極細繊維、アラミド繊維・炭素繊維・ガラス繊維などと関連があります。ある種の繊維と樹脂とを組み合わせたものが複合材料です。不織布はシート形成方法によって分かれますが、長繊維紡糸(ノズルから噴き出す)、衣料用芯地(これも不織布です)、紙の技術と関連を持っています。また超極細繊維を用いた不織布に樹脂を含侵させたものが人工皮革です。 ここまで見てきた中でも、炭素繊維・スーパー繊維・人工皮革などはとくに日本が競争力を持つ素材です。さらに自動車・機械・衛生材料などでは、使用する日本産業の要求水準が高いことが、日本の産業用繊維の機能の高さにつながっています。 織り・編み・染色加工など衣料用繊維の「川中」部分を担ってきた北陸地域でも、産業用繊維への事業展開が盛んになってきています。織りや編み、そして染色加工ルーツの表面加工の技術がいかされ、カーシート・エアバッグ・防電磁波材・介護用品・建築用繊維・水産資材・スポーツ用品・複合材料向け繊維加工などへの展開が見られます。紡糸の技術を応用して、プラスチック製光ファイバーでトップに立つ企業もいます。 |
5.繊維とは何かさて、「繊維」とはいったい何でしょう?「繊維イコール衣料」というイメージを離れ、原点に帰って考えてみると、つまるところ、繊維とは「細くて長いもの」であり、それを集めてつくったのが「繊維製品」です。そこから出発して、様々な機能と製品との関係を考えることができます(図6)。 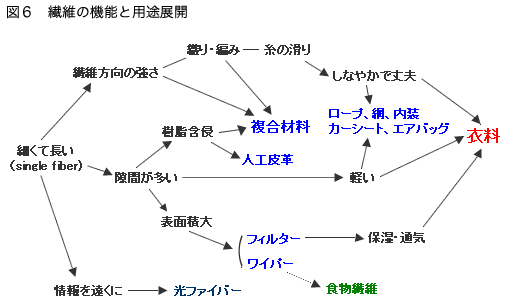 通常、我々が目にする「糸」は、「繊維」を紡績や撚糸等によって集めたものです。「繊維状のものは繊維方向に引っ張ったときに強い」という性質を持っていますが、繊維を集めて糸にして、それを織ったり編んだりすることによって、糸の滑りを利用したしなやかで丈夫な製品ができます。これを活用したものに、ロープ・カーシート・エアバッグなどがあります。 細くて長いものを集めた素材は、隙間がたくさんできます。繊維を骨組みにして強化した樹脂が複合材料です。ここでは「織りや編み」は複数方向の強さを持たせることに、「隙間が多い」ことは樹脂を浸み込ませるのに役立ちます(注7)。 また、隙間が多いということは、「表面積が大きい」ということでもあり、これがろ過を目的とするフィルター、ふき取りを目的とするワイパーの用途に結びつきます(注8)。さらにフィルターとは「何かを通して、何かを通さない」ことですから、保温通気、防水透湿などの機能に結びつきます。 さらに、隙間が多いものは軽くなります。 これらをみると、古くからある「衣料」は、実は繊維の持つ様々な機能を集約したものであることがわかります。そしてそこから産業用繊維が開発される場合は、むしろ図6の矢印を逆にたどっていくといえるでしょう。いずれにしろ、繊維を「細くて長いもの」ととらえなおすことにより、その世界は大きく広がるのではないでしょうか。 |
| ※(注○)をクリックすると、本文の該当の箇所まで戻ります。 | |
| (注1) | タバコの火を落としたとき、穴が開きにくいこと。 |
| (注2) | ストロー上の構造を持つ微細な繊維を束ねて、ろ過機能を持たせたもの。 |
| (注3) | ブレーキパットや防護服などに用いられるのが強度に優れたパラ系アラミド繊維、耐熱フィルターや消防服に用いられるのが耐熱性に優れたメタ系アラミド繊維である。 |
| (注4) | 表1にあるように衣料用・インテリア用の不織布もあるが、大半が産業用である。 |
| (注5) | PAN系はポリアクリロニトリル繊維、ピッチ系は石油重質分を原料として得られるピッチ繊維を、それぞれを炭素化して得られる。 |
| (注6) | 明確な定義はないが、0.1デニール(9,000mで0.1g)未満のものを指すことが多い。 |
| (注7) | ただし複合材料の開発では、繊維とは別の「樹脂」「成形」の技術が重要である。 |
| (注8) | ここで大きな表面積をコンパクトにまとめるために、極細繊維、中空糸、不織布などの技術が活用されている。 |
|
||||