| 中心市街地の活性化に向けた取組みについて 富山県 商工労働部 商業流通課 |
はじめに平成18年5月、これからの少子高齢化や人口減少社会に対応したまちづくりや中心市街地の再生を目指して、中心市街地活性化法、都市計画法などが改正されました。(中心市街地活性化法は平成18年8月22日施行、都市計画法は平成19年11月末までに全面施行) そこで、県内の中心市街地の現状や課題、中心市街地の再生に向けた県の施策などについて紹介します。 |
1 県内の中心市街地の現状皆さんご承知のとおり、モータリゼーションの進展により、本県ではこれまで住宅をはじめ、大型商業施設、公共公益施設などの様々な施設が郊外へ立地するようになり、通勤や買い物など日常生活に自動車が欠かせない社会となりました。 その一方、中心市街地(街なか)では、人口の郊外への流出が進むとともに、空き地や空き店舗が目立ち始め、商業活動等の衰退に歯止めがかからない状況にあります。 |
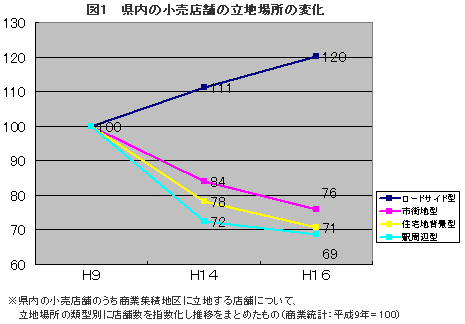
市街地の広がりを示すものさしとして、人口集中地区(DID)*1という指標が用いられています。これによると、県内の人口集中地区(DID)の面積は昭和35年(1960)に39k㎡だったのが、平成12年(2000)には106k㎡に増加する一方、人口密度は8.342人/k㎡から4.051人/k㎡と半分以下に減少しており、県内の市街地が薄く広がっていることがわかります。
|
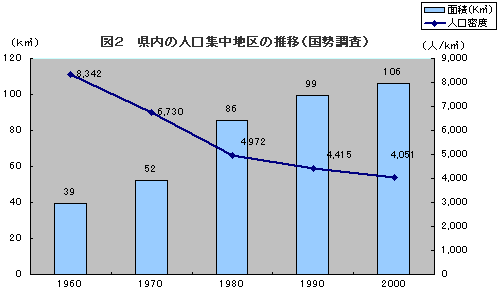 また、富山市、高岡市の中心市街地における歩行者通行量の推移を見ると、平成16年(2004)における歩行者通行量は、富山市では昭和61年(1986)の約4分の1、高岡市では5分の1近くにまで減少しています。 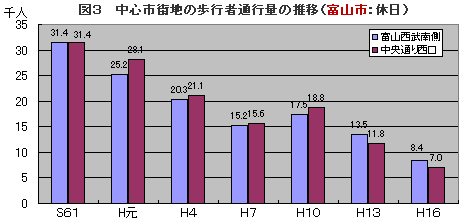 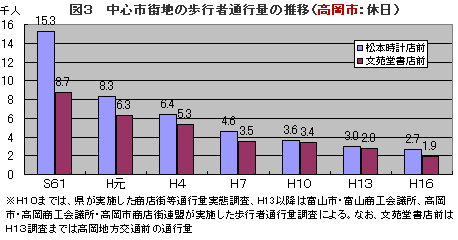
|
昨年度、県内の12,000人(有効回答率45.7%)を対象に実施された中心市街地などに関する意識調査「消費者購買動向調査」によると、地元商店街に対する満足度について、「大いに不満」、「やや不満」を合わせて4割以上の人が不満であるとする一方、「満足」「やや満足」の人が1割以下と地元商店街の現状に満足していない状況がわかりました。満足していない理由として、「駐車場が少なく車で行きにくい」、「買い物しないと駐車料金がかかる」など駐車場に関する不満が多くあげられました。
|
|
一方で、中心市街地が衰退していくことは、将来を考えると問題があるかどうかという問いに対しては、「大いに問題がある」、「問題がある」を合わせて約6割の人が衰退していくことに問題があるとしており、特に「50歳代以上」は、他の年代に比べ問題があるとする割合が多くなっています。 その理由として、「地域の活力がなくなる」、「車の運転が困難な人にとって住みにくくなる」、「賑わいのある場がなくなる」と答えた人が多くなっています。 このことから、県民は地元商店街の現状には不満を持ちつつも、中心市街地の必要性を感じていることがわかります。 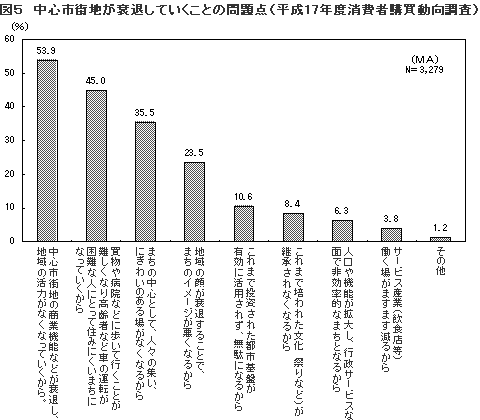 |
3 今後の課題と県や国のこれまでの動き(1)少子高齢化、人口減少最近、日本の人口が減少に転じたことが明らかになり話題となりましたが、本県ではすでに人口減少が始まっており、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本県の人口は2015年には107万人、2030年には95万人にまで減少すると予測されています。また、2015年には高齢者人口が年少人口の2倍、2030年には3倍を超し、人口全体の3分の1を占め、全国平均よりも少子高齢化が進んで行くと予測されています。 このことから、これまでの人口増加を前提とした郊外を中心とする開発を進めるよりも、既に社会基盤整備がされている中心市街地等をリニューアルするなど、自動車を利用しない人にとっても利便性が高く、環境面や財政面での負荷が小さいまちづくりを進める必要があると考えられます。 (2)富山県広域まちづくり商業振興懇談会本県では、17年度、今後の広域的なまちづくりや商業振興のための方策について幅広く検討するため、富山県広域まちづくり商業振興懇談会を設置し、大規模商業施設の立地について地域に与える影響や一般消費者の意識等を調査・分析し、今後、講ずべき施策の方向性などについて検討してきました。 本年2月には、上記懇談会から中心市街地の活性化には、商業者や地権者だけでなく、住民、行政など地域の総力を挙げて取り組むことが必要などとする「広域的なまちづくりのあり方に関する提言」がまとめられ、知事に提出されました。 (3)まちづくり三法の見直し国では、いわゆる「まちづくり三法」の見直しが検討され、今回の中心市街地活性化法や都市計画法などの改正となりました。 「中心市街地活性化法」では、
「都市計画法」や「建築基準法」では、
詳しくは国土交通省HPをご覧下さい。 |
4 県の具体的な施策県では、まちづくり三法の見直しや「富山県広域まちづくり商業振興懇談会」の提言を踏まえ、次のような事業を実施し、中心市街地などの魅力向上が図られるよう取り組むこととしています。 (1)がんばる商店街支援事業商店街の魅力や集客力を向上していくために、商店街が自ら考えた独自の総合的な活性化プランの着実な取組みを行う「がんばる商店街」に対し、県と市町村が助成します。 例えば、商店街、大型店、駐車場などが連携して行う共同イベントの実施、空き地、空き店舗の文化・教養・娯楽施設や若者等によるチャレンジショップへの有効活用、各種イベントの実施、商店街の魅力向上のための景観整備や地産地消、共通サービスの実施など、ハード・ソフト両面の様々なアイデアを凝らした取り組みへの支援等が考えられます。 (2)中心市街地活性化基本計画ステップアップ事業改正された中心市街地活性化法では、国が市町村の作成する「中心市街地活性化基本計画」を認定し、重点的に支援することとなりますが、県では、基本計画を策定しようとする市町村に対して支援することとしています。 (3)まちの賑わい拠点創出事業中心商店街等に賑わいの拠点を創出するため、NPO法人等が、地域の有するさまざまな資源を活用して取り組む、商店街の活性化に寄与する事業に対し助成を行うこととしています。 |
おわりに平成19年度中に東海北陸自動車道が全通し、平成26年(2015)頃までに北陸新幹線が開業するなど、本県において高速交通網の整備がますます進む中においては、いわゆる「ストロー効果 *3」による活力の停滞を招かないためにも、活気あふれるまちづくりやにぎわいの拠点づくりが喫緊の課題であるといえます。 中でも中心市街地は、様々な都市機能(居住、商業、サービス、オフィス、教育、文化、医療、福祉など)が集積する「地域の顔」であることから、中心市街地に立地する商業者、地権者をはじめ、住民、行政など幅広い参画を図りながら、魅力ある商業空間の形成や賑わいの核となる中心市街地の再生が必要であり、県として各種施策を推進していきたいと考えております。
|