| 富山県の火災の発生状況について 富山県 知事政策室 消防・危機管理課 |
はじめに富山県は全国でも有数の住みやすい県といわれている。その背景には、持ち家率の高さなどがあるが、地震や台風や、火災の災害が少ないこともその一因となっている。3月に消防庁より発表された平成17年の火災概況(概数)では、本県の出火率は15年連続して全国最小となった。 本稿では、本県及び全国の火災発生状況や本県の火災予防の取り組みなどについて概括する。 |
1 出火件数平成17年における本県の出火件数は275件で、全国で2番目に少なく、前年と比較して29件(9.5%)減少した。なお、平成17年における全国の出火件数は57,487件で、前年と比較して2,900件(4.8%)減少している。ちなみに、出火件数が最少だったのは鳥取県で270件、3番目に少なかったのは福井県で299件となっている。 また、過去10年間で見ると、平成10年の出火件数が本県や福井県、全国で最も少なくなっている。この年は全国的に冷夏に見舞われるとともに、冬は暖冬であったことから、火災が発生しにくい状況であったと考えられ、火災の発生件数が天候に左右される面が出た例といえる。 |
ア 出火件数の推移(単位:件) 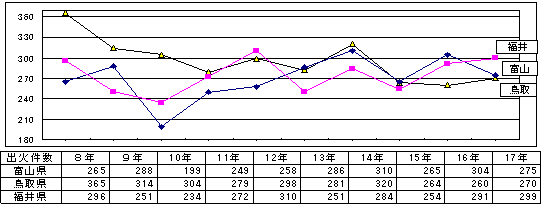 イ 全国の出火件数の推移(単位:件) 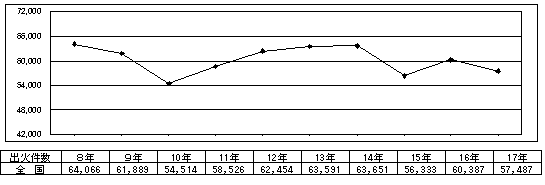 |
2 出火率
各県で人口規模が異なることから、全国での火災発生状況の比較として、人口一万人あたりの出火件数である出火率がしばしば用いられる。 平成17年における本県の出火率(人口1万人当たりの出火件数)は、前年より0.26ポイント減少し、2.46となり、全国で一番小さく、平成3年より15年連続して全国最小となった。 全国の出火率は、前年より0.23 ポイント減少し、4.53となっている。ちなみに、本県に次いで出火率が小さかったのは京都府で2.79、次に小さかったのは新潟県で2.98となっている。また、出火率が最も大きかったのは鹿児島県で6.69、次いで茨城県の6.10、山梨県の6.03となっている。 |
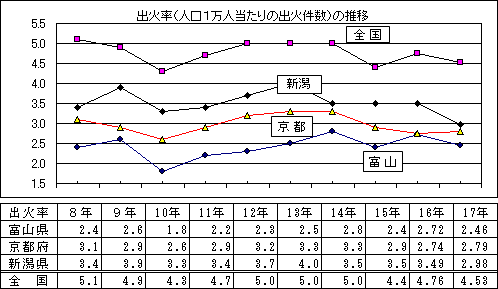 |
3 月別出火件数平成17年における本県の出火件数は、4月が32件と一番多く、次に6月の29件となっており、過去5年間では3月〜4月が最も多くなっている。 また、全国の出火件数は、平成17年においては4月が6,311件と一番多く、過去5年間では、本県と同様に3月〜4月が多くなっている。 このため、総務省消防庁の提唱で、火災の多発する3月に春季全国火災予防運動が、また、暖房器具を使う機会の増加する11月に秋季全国火災予防運動が行われており、本県においても県と市町村消防機関などが中心となって、多彩な行事を実施し、火災予防に努めている。 ア 富山県の月別出火件数 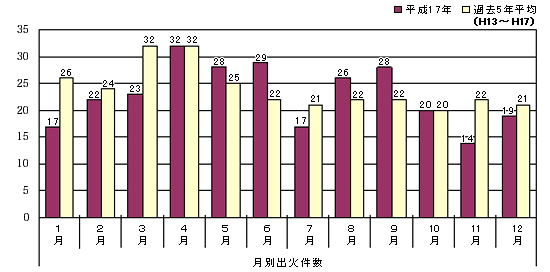 イ 全国の月別出火件数 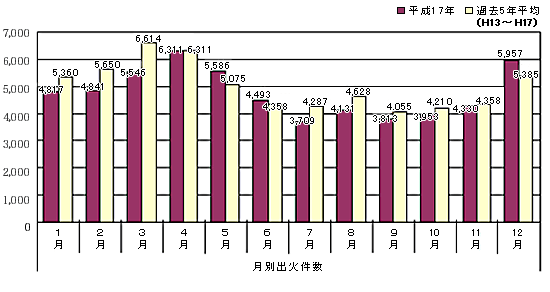 |
4 主な出火原因平成17年における本県の出火原因は、件数は減少したものの依然として「放火」が一番多くなっており、以下、「こんろ」、「たばこ」、「ストーブ」、「放火の疑い」の順となった。 また、全国では、「放火」が9年連続して一番多い出火原因となっている。 「放火」対策については、総務省消防庁では、「放火防止対策戦略プラン」をとりまとめ、全国の消防機関などに配布しており、また、本県においては、市町村消防機関などの啓発のほか、放火追放ポスターの作成・配布や富山県安全なまちづくり条例に基づく自主防犯活動の推進などにより、悪質な放火の撲滅を目指している。ア 富山県の火災の出火原因
イ 全国の火災の出火原因
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 火災による死者と住宅用火災警報器の設置義務化(1) 火災による死者平成17年における本県の火災による死者は19人と、前年比2人の減となり、住宅火災による死者(放火自殺者等を除く)も減少した。 全国では、2,197人が火災により亡くなっているが、住宅火災による死者(放火自殺者等を除く)は増加傾向にあり、平成17年は前年比で185人増加して1,223人となり、データの存在する昭和54年以降最多となっている。 ア 富山県の火災による死者 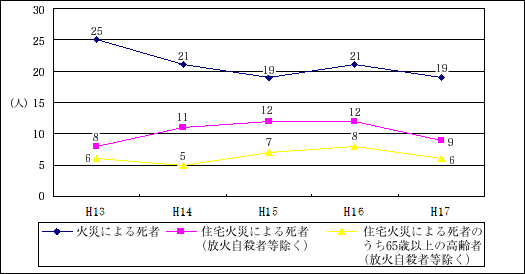 イ 全国の火災による死者 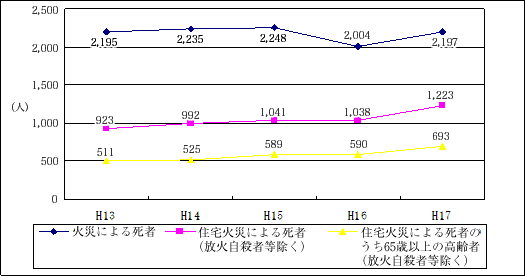 (2) 住宅用火災警報器の設置義務化本県及び全国では、住宅火災での死者のうち約6割が65歳以上の高齢者となっており、また、逃げ遅れによる死者も多いことから、より早く火災の発生を知っていれば助かった方も多いと思われる。 このような状況を踏まえて平成16年6月に消防法が改正され、新築住宅については平成18年6月1日から、既存住宅については、富山県内の市町村条例により平成20年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられた。 設置場所は、住宅内の寝室や寝室に通じる階の階段天井などに設置していただくことになる。 |
 |
現在市販されている住宅用火災警報器は、大きく分けると、「煙」に反応するタイプ(煙式)と「熱」に反応するタイプ(熱式)の2種類があるが、寝室・階段には煙式を設置する。 また、設置方法によって乾電池タイプと配線タイプの2通りに分けられ、配線タイプには、出火した部屋以外の火災警報器に連動して火災を知らせるタイプもある。 |
住宅用火災警報器は、消火器などとともに、ホームセンターなどで取り扱っており、消防署が直接販売することはないので、不適切な訪問販売等にはご注意いただきたいと考えている。 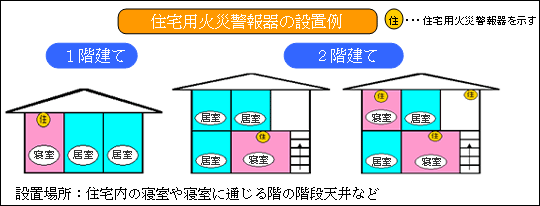 |
|
終わりに本県の出火件数が少なく、出火率が低いのは、県民の皆さんの防火意識の高さによるものであり、その背景には、持ち家率の高さや住宅の平均面積の広さに見られるように、自分の家を大切に守ろうという意識とともに、長年にわたって、防火思想の普及啓発などに消防職員や消防団員などの消防関係者はもとより、少年消防クラブや婦人防火クラブなど多くの民間防火組織の地道な取組みがある。しかも、小さい子供の頃から防火思想などの教育が地域で熱心に行われてきており、県においても、小学生火災予防研究発表大会の開催や小中学生防火ポスター図案の募集などを行っているところである。 しかし、本県の出火件数が少ないとはいえ、一旦火災が発生すると、一瞬にして生命や財産を失ってしまう。 万が一の火災が発生した際に、逃げ遅れなどによる悲惨な犠牲を少なくするため、県民の皆さんには、日頃の火災予防はもとより、住宅用火災警報器設置の促進についてご理解とご協力をお願いします。 |