| �R�N�ڂ��}
����x�R����A�������̊����Љ�� �����o�ώ��� �x�R����A������ �������@�c���@�Y�� |
|
�x�R���Ɖi�N�A�F�D���Ȃ̊W�ɂ���ɔJ�Ȃ̑�A�s�Ɍ��̗B��̊C�O�������Ƃ��ĂQ�O�O�S�N�t�ɕx�R����A���������J�݂���A���N�łR�N�ڂ��}���܂��B�i*1�j �����œ��������̊����Љ�ƒ����o�ώ���ɂ��ĊȒP�ɏq�ׂ܂��B 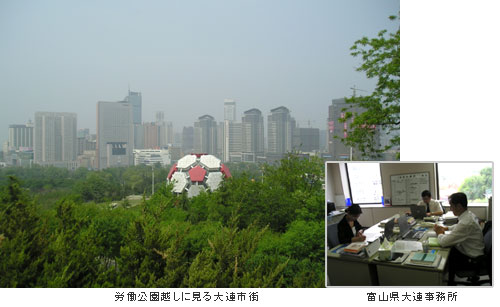 |
�P�@�x�R����A�������̊����Љ�(�P) �x�R���ƒ����Ƃ̊e��𗬑��i
�x�R���֘A��Ƃ������ɐ������i�o���Ă����܂��B��A�s�����ł���\���Ђ𐔂��܂����A�����i�o�ς݂̊�Ƃ͖ܘ_�A���㒆���ŋƖ��W�J���������̕��ւ̎x������ʂ��ė����̌o�ό𗬑��i��}���Ă��܂��B��̓I�ɂ͔N�S��A��A�x�R��Ɖ���J�Â��A�e��Z�~�i�[��e�ЍH�ꌩ�w�������{���Ă���܂��B������Ɠ��m�Ƃ�����������A���ł͓��ɂ������̌����⑊�k�̏�Ƃ��Ă��D�]�Ă��܂��B���ɂ͌ږ�_���������Ă���@���������Ɖ�v�������ɂ�閳�����k�T�[�r�X��������܂��̂Ō�����Ƃ�l�̊F�l�ɂ������p���ĉ������B ��Ɛi�o�݂̂Ȃ炸�A�f�Ց���T����ϑ����H��̏Љ�Ȃǂ��s���Ă���܂��B�ŏ�����Ǝ��ōH������݂���ƂȂ�ƃ��X�N���傫���Ȃ�܂��̂ŁA�����͈ϑ����H����Ƃ����I���������邩�Ǝv���܂��B�i*2�j �܂��A�o�ϖʈȊO�ł͊w�p�E�����������ʂ̌𗬂̂���`��������Ă���܂��B��w�Ԃ̌𗬓��������𗬂ւ̎x����������܂��B�����Ē����I�ȉۑ�Ƃ��Ē����嗤����̊ό��q�U�v�ɂ���g���ł����A�����̂Ƃ���x�R�̒m���x�͓������ʓ��ɔ�ׁA�܂������Ȃ��ł��B����͓��Y�i���܂ߕx�R�u�����h�������Ŏ��m�����悤�w�͂����Ă����\��ł��B |
(�Q) �x�R�t�@����y���ɂ��������ɂȂ���g�݂Ƃ��āu�x�R�t�@����y���v������A���������Ɏ����ǂ�u���Ă��܂��B����͗��w�⌤�C�ŕx�R���ɑ؍o���̂��钆���l�ɂ��\������g�D�ŁA�x�R���ƒ����e���ʂƂ̌𗬑��i�̋��n�����ƂȂ��Ă�����Ă��܂��B����y���ɂ͒����A����Ɋ��E�E���ƊE�Ŋ��������ÁE�Ȋw�E���ی�E�`�p�E�_���Ɠ��̐�啪��ɑ����̈�ނ������A�x�R���ɂƂ��Č𗬎��Ƃ��l����ꍇ�A���ɈӋ`�̂���g�D�ƂȂ��Ă��܂��B�i���݉�����͖�Q�S���j�i*3�j (�R) ���������̍���̉ۑ��ɔJ�Ȃ𒆐S�Ɋe�n�̎s���{��J����Ƃ̘A���𖧂ɂ��Ă���܂��̂ŁA�ɔJ�ȓ��ւ̊�Ɛi�o�ɓ������Ă̏���{�@�֓��̏Љ�̂ł���̐��͐����Ă��܂������A�t�ɒ�������x�R���ւ̊�ƗU�v�ƂȂ�ƁA�������̂����������Ƃ������Ƃ����荢��ȏɂ���܂��B���N��A�ŊJ�Â��ꂽ�u�k�����ۓ����𗬑��i��c�v�ɂ����āA��A��Ƃɑ���k���n��ւ̊�ƗU�v�Z�~�i�[�̂���`�������܂������A���������Ƃ̗U�v�͓��ʂ͑�������Ǝ������܂����B�ނ����R���Y�ƕ���ł̒�����Ƃ̕x�R���i�o���l�����܂����A������Ƃ̐�����O��ɂ��܂̂��������s�����I�ɕx�R���̂o�q�ɓw�߂����ł��B |
(�P) ��������o�ϐ����Ə������̓�ɉ��̖��
�����o�ς́u�K���v�Ƃ����f�c�o�������͂X���O��ƌ����Ă���A��N���ыy�э��N�̗\�z�Ƃ��قړ������ł����A���g���ᖡ����ƕ���ɂ���Ă͉ߔM�ƌ��킴��܂���B�ȉ��A�ߔM���ۂ̓��e�ɂ��ė��܂��B �@�o�ς̉ߔM����
�A��ɉ��̖�� ����A�����⎑�Y���̍��ڂł̓�ɉ����i�s���Ă���A����͓s�s�ƒn���A�s�s�����̓�ɉ��ɉ����A�n���i�_���j�ł̓�ɉ��Ƃ��Ȃ��Ă��܂��B�S�̓I�ɕn���������n��ł��A�W�j�W���i*6�j�͂O�D�S���Ă���A�����z�œ��n��_���ƒ���T�K�w�ɕ��ނ����ꍇ�A�ō��ʂ̂Q���̉ƒ�̔N���͍Œ�ʂ̂Q���̕��ωƒ�̖�P�Q�{�ȏ�ƂȂ��Ă��܂��B�������ɐ��{�������i�������Ɏ�g�ݎn�߂Ă��܂��B���w�엿��R�����i�㏸�ɂ��_���ւ̃}�C�i�X�ʂ��o�Ă���Ȃ��A�_���̗]��J���͑���i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B �J���W��^��Ƃ�荂�t�����l�̋Z�p�W��^�E�ݔ��W��^��Ƃ֊S���ڂ�n�������܂����A�����S�̂ł͈ˑR�J���W��^�Y�Ƃɂ��ٗp�m�ۂ��d�v�Ƃ̈ӌ�������܂��B |
���_���猾���ƁA�����̈ꕔ�o�ϊw�҂����͊����ƔF�߂Ă��܂����A������J���Ҍٗp�m���i*7�j�E�����㏸�Ɛl�����̋}�Ȑ�グ�͗����ł��Ȃ��W�ɂ���A�������ǂ͎Љ�̈���̂��߂ɂ��l�����̋}���ȏ㏸�͂��������Ȃ��ƌ���ׂ��ł��傤���B �ŋ߂ł͍���������w�Ґ����P�O�N�O�̂T�{�̂T�O�O���l�ɂȂ��Ă���A���w��J���͋z�����ۑ�ɂȂ�Ȃ��A�\�t�g�J���������ڂ���Ă��܂��B���̕���ł̓C���h�Ƌ�������̂ł����A�����̓\�t�g�J���̑g�D�͂�l�ވ琬�̖ʂ��܂߁A�\�t�g�Z�p���x���ł̓C���h�ɂ���邽�߁A�C���h�������P���łȂ��Ə��ĂȂ��̂�����ł��B�C���h�̓��m�̖f�Վ��x���P��I�ɐԎ��ł���A�ʉ݂̐�グ���͂͏��Ȃ����߁A�C���h�̑��݂��l����Ɛl������グ�͔��Ɋɖ��ȃX�s�[�h�ł����ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �܂����z�̊O�݂̒~�ς�����A�č������ʂɕۗL���钆���Ƃ��Ă͕č����������̂T���O��ł��邱�Ƃ��炷��A�N�Ԃ̈בւ́u�ڌ���v������ȉ��łȂ��Ɛ����ɂ����Ƃ������ł���A�Q�O�O�T�N�V���̐l�������v���̐�グ���Ƃ���ȍ~�̏㏸���͂��̐������Ɏ��܂�������ɂƂǂ܂��Ă��܂��B�i�ŋ߁A�u�ԓI�ɂP�ăh���W�l����������j�i*8�j �A���A�Ē��f�Ֆ��C�͌������邱�Ƃ͕K���ł���A�q��@��\�t�g�E�F�A���̑�K�͂Ȓ��B�⋍���A���ĊJ�Ƃ��������@�Ŗ��C������������A���{�ƈႤ�̂͐����E�R���̖ʂł̑卑�Ƃ��Ẵp���[��w�i�ɒʉݐ�����^�c�ł���_������܂��B���{�~�̑�ϓ��̗��j�ʋ��t�ɂ��đQ�i�I�Ȓʉ݉��v�i��グ�j�͌p������\�����傫���Ǝv���܂��B�i�ߋ��̓��Ėf�Ֆ��C�ƃA�����J����̓��{�~�̐�グ���͂̓����ɂ��ގ�����Ƃ��������A���݂̒����͂��Ă̓��{�̒ʉ݁E���Z�������d�����Ă��锤�ł��j �ΕĖf�Ս����͂Q�N�A���ň�牭�h���ɒB���錩���݂ł���A�l�����̏㏸���͂����������邽�߂̉���ɂ��l�����̗����������傷�錋�ʂ��z�肳��܂��B����͂��Ă̓��{�̉ߏ藬�����ɂ��o�u�������̉ߒ��Ɨގ����Ă��܂��B�܂��C�O�̓����E���@�����ɂƂ�A���킶��ł����m���ɒl�オ�肷��ʉ݂ł���l�������Ă̎��Y�͓����ΏۂƂ��ė��z�I�ł���A���������͌p����������ɂ���A������s���Y���̃o�u���v���ƂȂ��Ă��܂��B ���Ȃ����ܗւ܂ł̊��Ԃ͍����̓�ɉ��Ɛl�������ɂȂ�Ƃ��Ή����u��D���v�Ȍo�Ϗƕ\�ʏ㌩����Ǝv���܂����A�ܗւ܂��͖�����Ɍo�ϖʂł̒����ǖʈ����͔���������\���͂���A�����I�ɂ͐T�d�ȓ����X�^���X���K�v��������܂���B�i�����I�ɂ͂Q�O�Q�O�N�܂ŘV��l���Ƃ��ǂ��̊��������Ȃ��Ƃ����l����̃����b�g������ł����A���琅���̌���E�ΕׂȖ����������Ă���ƌo�ϔ��W�͌p������Ǝv���܂����E�E�E�j |
�R�@������
��A�͓s�s�����玊�ߋ����̂Ƃ���ɐ؎�̐}���ɂ��Ȃ����������C�ݐ�������A�Ă���H�ɂ����Ē��������̑��A���V�A��������������̃��]�[�g�q�E�ό��q���K��܂��B�T�S�ւ̕x�R�E��A�ւ�����܂��̂Ő���A�x�R���̊F�l���̋G�߂ɂ�������艺�����B �Ȃ��A�x�R����A�������̃��[���A�h���X�͈ȉ��̂Ƃ���ł��̂ŁA�����k���������܂�����A���A���̒����҂����Ă���܂��B E-mail : office01@toyama.com.cn �d�b�F86�i���ԍ��j-411-8368-7879 |
| �i*1�j | ����������̗����Ȃ̖��ڂȌ𗬂̌��ʁA�P�X�W�S�N�T���ɗɔJ�Ȃ̑�\�c��x�R���Ɍ}���ėF�D���Ȃ̒������s���Ă���B���ꂩ�炩��Q�O�N�ڂ̂Q�O�O�S�N�ɑ�A���������J�݁B |
| �i*2�j | �Ǝ��Ƃ͓��{���O����Ƃ������Ɍ��n�q��Ђ�ݗ�����ۂɁA�������Ƒg�ނ��ƂȂ��A�P�O�O�����炪�o�����s���`�Ői�o����`�ԁB�������̃p�[�g�i�[���o������ꍇ�A�u�����v�`�Ԃƌ����܂��B�Ȃ��A�ϑ����H�͑S���o���W�킸�A�����̊�Ƃɐ��Y�̍H���̈ꕔ������`�Ԃł��B |
| �i*3�j | �x�R���̗l�X�ȖK��c���ɔJ�Ȃɗ��K�̍ہA�x�R�t�@����y������̂Ȃ�����A�֘A���镪��̕����s�b�N�A�b�v�̏�A�K��c�ƈ������킹���邱�ƂŁA�𗬂�V���ɐ���ł��܂��B |
| �i*4�j | �Q�O�O�O�N�O�ォ��O����Ƃ̏�C�i�o�u�[���������A��C�̕s���Y���i���㏸�𑱂������̂ł����A�Q�O�O�S�N�̒������{�̌o�ω^�c���j�̂Ȃ��ʼnߔM�����Ƃ���A�s���Y�����}���̃X�^���X���ł��o����܂����B�Q�O�O�T�N�ȍ~�A���̌��ʂɉ����A���������}���ȏ㏸�̔���������A��C�̕s���Y���i�͉����B�������A��s�s�ƒn���̓�ɉ��������瓌�k�n���⒆���̒������̊J���͏��コ�ꂽ���߁A�n���̕s���Y���i�͏㏸�A�n���̃C���t���������}���ɐi��ł���B |
| �i*5�j | �����ł̓}�C�z�[���Ƃ͕ʂɕx�T�w�����Ȏ����Ȃ����͋�s�ؓ����s���A�����̃}���V�����ɓ���������Ԃ�����܂��B���ۂɎ������g���킯�ł��Ȃ��A���l�ɑ݂��킯�ł��Ȃ��A���l�œ]�����邱�Ƃ��ő�̖ړI�ŁA�܂��Ɂu�����v�ł����A�Ȃ��ɂ͎ؓ������̕��S�������ł��a�炰�邽�߁A���l�ɕ�����݂��o�����Ƃ�����܂��B�������ƒ��͎v�����قǍ����Ȃ��A�s���Y����肪��s������茩��肷��P�[�X�����X����܂��B |
| �i*6�j | �W�j�W���Ƃ͕��z�̏W���x���邢�͕s�����x��\���W���ŁA�����ł���قǂO�ɋ߂Â��A�s�����ł���قǂP�ɋ߂Â��B�W�j�W�����傫���قǐ��ё��݂̊i�����傫���s�����Љ�Ƃ������ƂɂȂ�B |
| �i*7�j | ������J���҂̌ٗp�m�ۂ̉ۑ�Ɋւ��ẮA�����P�V�N�R�����́u�Ƃ�܌o�ό���v�f�ڂ̕x�R��w�����O�q�����̘_���u�����̎��Ɩ��v�����ɎQ�l�ɂȂ�܂��B |
| �i*8�j | �l������グ��̓��� �Q�O�O�T�N�V���Q�P���ȑO�@�P�ăh�����W�D�Q�W�����x �Q�O�O�T�N�V���Q�P���@�@�@�P�ăh�����W�D�P�P���i��Q���㏸�j �Q�O�O�U�N�T���P�T���@�@�@�P�ăh�����V�D�X�X�W�Q���i�v�R�D�S���㏸�j ���̌�A�W����ɖ߂��Ă��܂��B |