![]()
構造改革特区と地域再生推進プログラム
富山大学経済学部教授 中村和之
はじめに
今回から3回にわたって、『経済指標のかんどころ 改訂22版』(以下「かんどころ」と略します)の第2章と第5章に掲載された項目の中からいくつかを取り上げて解説します。特に、「かんどころ」刊行以降の新たな動向を中心にお話ししたいと思います。
今回は、第2章「経済政策」の中から経済構造改革を取り上げます。小泉内閣の構造改革路線も3年目に突入しました。当初は不良債権処理や金融再生などバブルの後始末が中心でしたが、昨年度以来、規制改革や地方分権といった改革プログラムに沿った具体的な政策が打ち出されつつあります。 以下では、小泉内閣の経済構造改革の目玉である構造改革特区と地域再生推進プログラムについて、その仕組みや背景、意義を考えます。なお、経済構造改革の全体像については「かんどころ」を御参照下さい。
構造改革特区
昨年、「どぶろく特区」が新聞やテレビで話題になりましたね。特区に認定された地域では、酒税法に基づく酒類の製造免許を受ける際に最低製造数量基準の要件を適用しないことで、農家が自家製の酒を併営の民宿などで提供できるようになりました。岩手県遠野市(日本のふるさと再生特区)や長野県飯田市(南信州グリーン・ツーリズム特区)などがこの認定を受けています。
今年の2月には、東京都千代田区(キャリア推進特区)と大阪市(ビジネス人材育成特区)で株式会社立の大学、大学院の設置が認可されました。教育関連では、小学校と中学校の垣根を取り払う小中一貫特区(東京都品川区や奈良県御所市など)や、小学校から英語科を導入する特区(福島県会津若松市や千葉県成田市など)もあります。
これらはいずれも構造改革特別区域法に基づいて認定された構造改革特区だけで実施される試みです。特区では従来できなかった事業やサービスの提供が公的規制の緩和によって可能となります。
構造改革特区制度の仕組みと現状をまとめておきましょう。構造改革特区制度では、まず地方自治体、企業、NPOなどが規制緩和の要望を政府に提案します。関係する省庁は、これらの提案を検討し、実行可能と判断されたものについて法改正、省令、容認などの形で対応します。これを受けて、地方自治体が構造改革特区計画認定の申請を行います。これまでに4回にわたって認定作業が行われ、324件の特区が誕生しました。
図1は第1回から第4回までに認定された特区を分野別にまとめています。従来の規制緩和は通信、運輸、エネルギーなど産業関連が中心でしたが、特区制度では教育や生活福祉など幅広い分野で規制緩和が行われていることがわかります。
図2は都道府県別にみた第1回から第4回までの認定件数を表しています。すべての都道府県で複数の特区が認定されていることがわかります。富山県内では、富山県と県内のいくつかの市町村による「富山型デイサービス推進特区」、八尾町の「越中八尾スロータウン特区」、上平村の「上平村農地保全継続創造特区」の三件が認定されました。
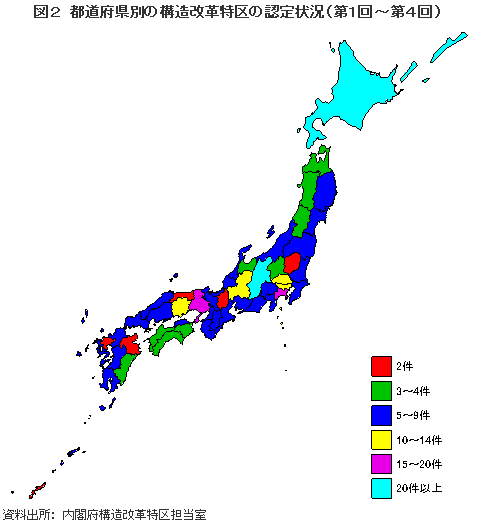
本年4月からは特区の評価作業が本格化します。構造改革特区推進本部に設置された評価委員会が各特区における規制緩和の効果を評価して、i)地域を限定することなく全国で実施、ii)引き続き地域特性を有する地域に限定して適用、iii)廃止もしくは是正、のいずれかの判断を下すこととなります
。
注)
1) 詳細は、経済財政諮問会議「構造改革と経済財政の中期展望-2003改訂」
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2004/040119kaikaku.htmlをご覧下さい。2) 構造改革特区制度の詳細は、構造改革特別区域推進本部「構造改革特別区域基本方針」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kettei/040224kihon.htmlを御参照下さい。3) 全国で認定された特区の詳細は、構造改革特別区域推進本部の資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/index.htmlをご覧下さい。4) 評価委員会での議論は、
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/hyouka.htmlを御参照下さい。5) 詳細は、地域再生本部
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiikisaisei/index.htmlを御参照下さい。6) 第二次行革審(1988)「公的規制の緩和等に関する答申」より。 7) 総務庁(2000)『2000年版 規制改革白書』第3章。 8) 1990年代に行われた規制緩和の効果については『経済指標のかんどころ 第21版』の第2章「経済構造改革」
http://www.cap.or.jp/~toukei/kandokoro/top/top1.htmlの表2でまとめられています。