| 統計図表の見方と地域の実像(3) 富山大学経済学部教授 柳井雅也 |
| 今回は世界や日本を対象に、地域の比較や地域スケールの変化によって地域の見え方や読み方が変わる事例を見ていきます。そして統計分析における「コツ」を考えてみたいと思います。 1.都道府県VS世界経済−GDPで比較すると− 日本のGDP規模の大きさを知るには、日本と外国を比較するのが普通です。しかし、もっと日本のGDP規模の大きさを「実感」したいなら、日本の都道府県と世界の国々との比較のほうが「実感」できると思います。図表1は、それを示したものです。 最近の日本経済は不況が続いていますが、まだまだ日本の経済規模が大きいことがわかります。例えば、近年IT化の急速な進歩で注目されている韓国でも、まだ東京のGDPより低いことがわかります。この他、北陸3県(富山、石川、福井)の合計が、ポルトガルと同じだったり、富山県がルーマニアをわずかに上回ったりしていることなどがわかります。 こういう比較から「日本経済の不況が続くことは世界経済にとって不安定要因の一つになる」と考えるほうがわかりやすいと思いますが、いかがでしょうか。 |
| 図表1 県内総資産 諸外国との比較
(単位:億米ドル)
|
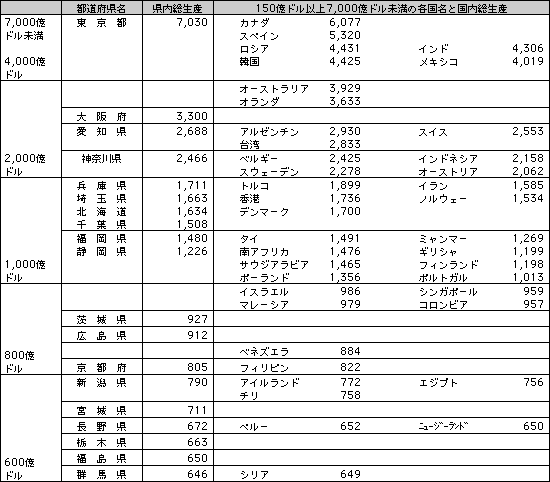 |
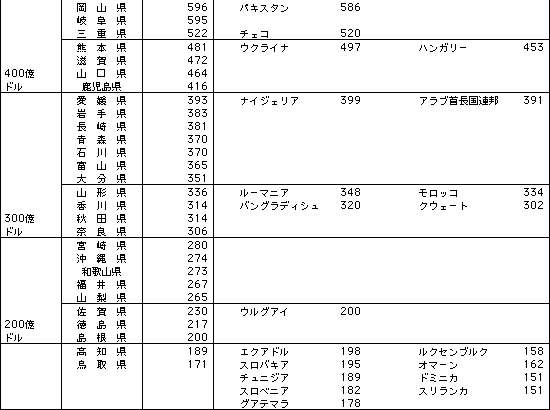 |
| (注) | ・各都道府県は「平成9年度(1997)県民経済計算(統計表)」(経済企画庁経済研究所)による。 ・県内総生産額は1ドル=122.71円(1997年度値)として換算(東京市場インターバンク直物中心相場の各月中平均値) ・各国について、OECD加盟国は「MAIN ECONOMIC INDICATORS」、他は国際通貨基金「国際金融統計月報」による。 (「海外経済データ(平12.1)−経済企画庁海外調査課−」よりいずれも1997年値) |
出所:全国知事会HPより (http://www.nga.gr.jp/kisodata/new_kiso_data_2002/3-3_data.pdf) |
| 2.港から経済の盛衰をはかる 図表2-1は、国内港湾のコンテナ取扱量の変化を示したものです。これによると東京の成長が確認できます。でもこの結論は本当に正しいのでしょうか? 続いて図表2-2をご覧ください。世界のランキングでは、日本全体の地盤沈下が明らかです。とくに神戸は阪神大震災の後遺症が残っているのも事実ですが、かなり落ち込んでいることがわかりますし、東京ですら世界的には「横ばい」傾向です。 図表2-1、2をみた場合、世界比較か国内比較かによって、図表の取り上げ方や解釈が異なってきます。もし、適切な図表の取り上げ方を誤りますと、針小棒大にことを取り上げ、拡大して、大げさな結論や誤った結論を導き出してしまうことになります。この、統計の作り手の術中にはまらないためにも、統計の読み手側は注意する必要がありますね。 ちなみに、日本の港湾におけるコンテナ取扱量の伸びが鈍っている理由は、香港やシンガポールそれにプサンなどのアジア地域において、(1) 大水深(-15m以上)コンテナターミナルが整備されつつあること、(2) 港湾の24時間フルオープン化、(3) 欧州航路が増加しているため、といわれています。その一方で、日本の主要港湾では、(1) 幹線道路網とのアクセスの悪さ、(2) 港湾での諸料金の高さ、(3) 手続きの煩雑さ、(4) その結果として東京湾などでは航路数は増加していないこと、が指摘されています※1。これに経済不況が追い討ちをかけているわけですね。 |
| 図表2-1 外貨コンテナ貨物量(万トン) |
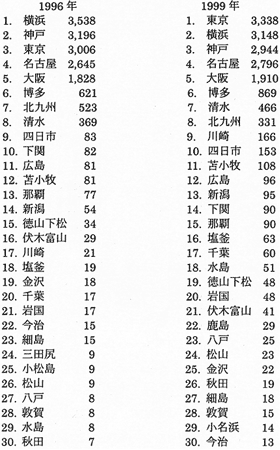 |
| (出所):運輸省港湾局監修『数字でみる港湾'98』『数字でみる港湾 2001』日本港湾協会をもとに作成。 |
| 出所:山崎朗「日本海沿岸地域の物流と日本海国土軸」『環日本海(東海)経済交流と日本海国土軸』経済地理学会北陸地域大会シンポジウム、2001年 |
| 図表2-2 コンテナ取扱ランキング |
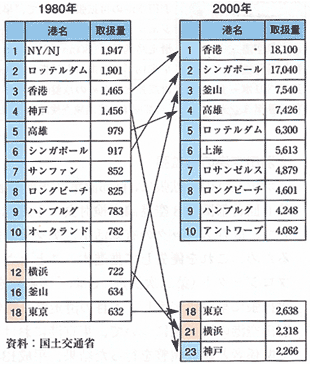 |
| 出所:『首都圏白書』平成14年版より。 |
| 3.成田空港の貨物取扱い地域は首都圏だけ? 図表3-1は国際線の貨物量の推移を示したものです。これによると、新東京(成田空港+羽田空港)が取扱量は圧倒的です。これは東京周辺地域の輸出入が多いためとも読み取れます。 ところが図表3-2をご覧ください。これは各都道府県の輸出入航空貨物に占める成田空港のシェアを示したものです。輸出では、長野を含む関東・東北が成田空港から輸出するのが75%以上を示し、次のランク(50−74%)では新潟、岐阜、静岡、それに九州の一部地域がはいっています。輸入においても、成田空港の大きさがわかります。成田の貨物取扱地域は全国レベルにあることがわかります。このケースは単なる例示に過ぎませんが、このような地域統計を読むときには、「常識」「推理」「カン」などを働かせて、場合によっては追加的にデータなどを調べる必要があります。 |
| 図表3-1 国際線空港別貨物取扱量の推移(一部改変)
(単位:t) |
|
| (注) | 新東京国際空港(成田空港)及び関西国際空港の数値は、東京国際空港(羽田空港)及び大阪国際空港(伊丹空港)の貨物取扱量との合算値である。 |
出所:北海道庁HP(http://www.pref.hokkaido.jp/skikaku/sk-kkkkk/sora/2-11.htm)より。 |
| 図表3-2 新東京国際空港の輸出入貨物の背後圏(金額ベース) |
各都道府県の輸出入航空貨物に占める成田空港のシェア(%)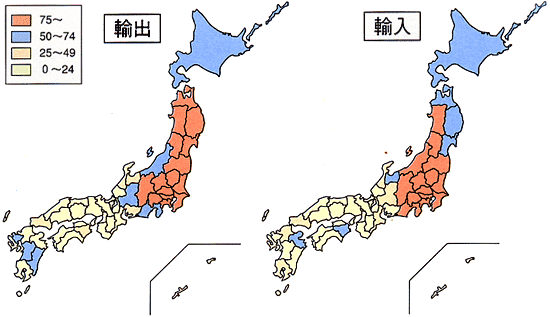 資料:「輸出入貨物に係わる物流動向調査(平成13年)」(財務省関税局)により国土交通省国土計画局作成 |
| 出所:『首都圏白書』平成14年版より。 |
| 4.統計分析法の「わな」 1から3の事例は、統計の地理的範囲の取り方によって、見え方や読み方が変わる統計について紹介をしてきました。実は、統計分析のテクニックについても注意することがあります。 例えば地域統計の分析法には、因子分析法や、ランクサイズルール、クラスター分析など統計的テクニックを駆使する分析法があります。「これを使えば、絶対に間違いはない!」と思えます。しかし、その答えは「No!」です。それぞれの統計テクニックにはデータの選び方や、結果の評価の仕方によって解釈が分かれる場合があるからです。 例えば、図表4の右のグラフは、ランクサイズルールという手法で、日本の都市システムを示したグラフです。簡単に言えば、都市を規模の大きいほうから順に並べて、縦軸に規模(size)、横軸に順位(rank)をとって対数表で示したものです。この統計手法は、左のグラフのように、第1位の都市が卓越するタイプ(primate pattern)、規模の近い上位都市が並存するタイプ(polynary pattern)、均衡が取れた都市システム(rank-size pattern)の3つに分かれます。これでいくと右のグラフは、6大都市や大阪の相対的な地位の高さに特徴がある近代から、東京を中心としたrank-size patternへ移行している様子がわかります※2。 この図の解釈はこれで正しいと思いますが、この統計手法には対象地域の範囲や都市の単位をどう取るか※3、中心地の階層区分をどうするかなど、分類の結果次第では異なった統計結果や解釈を引き出すことが可能になり、地理学などの分野では議論が続いています。 このほか、同じ都市の時間の推移(時系列)の分析を行うときは、過去の合併などによる都市域の変化などにも配慮する必要があります。 |
| 図表4 |
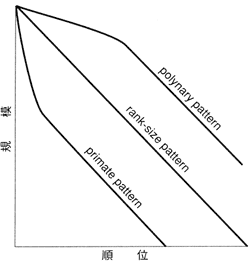 |
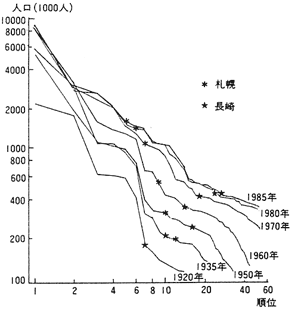 |
| ランクサイズグラフの3形態 (対数グラフ) |
日本の都市システムの変化 〔林上『都市の空間システムと立地』大明堂、1991〕 |
| 出所:『ジオグラフィックパル』(海青者)1998年。 |
| 5.適切な統計地図の選択 図表5-1、2は日本の平成12年(2000)の都道府県別人口を図にしたものです。みなさんはどちらの統計地図の描き方が適切だと思いますか?あるいはどちらも「OK」ですか? 答えは図表5-2が正しいです。図表5-1のような階級区分図(コロプレスマップ)を描く場合は統計の絶対値ではなく、割合を使うほうが適切だからです※4。当然のことを書いているようですが、実はコンピュータで描くとき、ボタンひとつで描画ができるために、「うっかり」して不適切な地図を描いてプレゼンテーションする場合があるため注意が必要です。 |
| 図表5-1 | 図表5-2 | |
(単位:万人)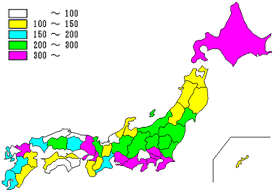 |
(単位:万人)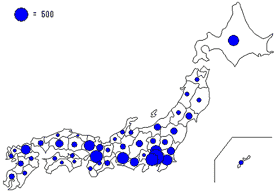 |
| いかがでしたか?地域範囲の設定の仕方に関する検討や、統計テクニックを利用する際の心得、それに地図の適切な表現が、正しい統計の理解にとって大切なことがわかっていただけたでしょうか? (注) ※1 国土交通省編『首都圏白書』平成14年版。 ※2 浮田典良編『ジオグラフィックパル』(海青社)1998年。 ※3 都市の定義についても世界では「基準」が異なります。たとえば米国の「標準大都市圏統計地域」では、都市の領域を 1.中心となるべき都市は人口 5 万人以上であること、2.郡別統計による労働力人口の 75 %以上が非農業従事者であること、 3.(i)人口の 50 %以上が人口密度 1 平方マイル当たり 150 人以上の市町村に住むか、(ii)非農業従事者の 10 %以上が中心市で働くか、あるいは(iii)郡の非農業従事者が 1 万人以上に達するかのいずれかに該当することなどと規定しています。 (http://www.crinet.co.jp/contents/president/essay/19990500.html#★) ※4 秋本弘章「パソコンにおける統計活用術」『統計から地域の変化を読む 地理11月増刊』相澤善雄・杉本茂編(古今書院)2001年。 |