![]()
「環日本海」は対岸だけか?
−富山県と「環日本海地域」−(その2)
富山商船高等専門学校国際流通学科 助手 岡本勝規はじめに
前回は「日本の日本海側地域がどの程度『地域』としてのまとまりをもっているか?」ということについて、北陸地域を中心とした公共交通の利便性を手がかりに論じてみました。
今回は、もう一つの疑問−−「日本の日本海側地域が、対岸諸国にとってどの程度比重を持っているのか?」ということについて、対岸諸国との貿易規模を手がかりに探ってみましょう。
なお、この稿においても、日本の日本海側地域とは、青森県から島根県にかけての日本海に面した地域とします。また、対岸諸国とは、ロシア連邦共和国(以下、ロシア)、中華人民共和国(以下、中国)、大韓民国(以下、韓国)、朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)、ソビエト社会主義共和国連邦(旧ソ連)を指すものとします。1992年のソビエト体制崩壊から6年後の1998年と、6年前の1986年を比較しました。
なお、データはすべて国土交通省「港湾統計(年報)」によるものです。1.日本海側地域における対岸諸国との貿易規模
まず、日本海側地域で行われている対岸諸国との貿易規模について、その変化と特徴を見ていきます。具体的には、日本海側の港湾で取り扱われている貿易量(輸出量・輸入量)に着目しました。日本海の沿岸には数多くの港湾が存在していますが、それらの中から、港湾法に基づいて重要特定港湾及び重要港湾に指定されているものをピックアップし、貿易量を対岸諸国別に比較してみます。
なお、日本海側地域の特定重要港湾及び重要港湾は、以下の19港です。
青森、能代、船川、秋田、酒田、新潟、両津、小木、直江津、伏木富山、七尾、金沢、福井、敦賀、舞鶴、鳥取、境、浜田、三隅(但し、福井港は2001年3月に地方港湾へ格下げ)。
[1]ロシア(旧ソ連)との貿易量 (表1)
輸出についてまず目に付くのが、伏木富山港における大幅な規模縮小です。1986年の時点では、他の取扱港から抜きんでた規模を誇っていたのですが、1998年には新潟港や浜田港などを下回るようになっています。一方、輸出の全体的な傾向を見てみると、日本海側全体の取扱量は実に半減するとともに、酒田港などの新たな取扱港が出現しており、「規模縮小+取扱港拡散」の傾向が見て取れます。
輸入については、1986年と1998年の両時点とも、伏木富山港が抜きんでた取扱量を示しています。輸出で首位の地位を失ったとはいえ、この輸入取扱量の圧倒的な多さは、伏木富山港が日本とロシアとの貿易において、非常に重要な役割を果たしていることを示していると言えるでしょう。
しかしながら、日本海側地域全体の取扱量は3分の2にまで減少しており、ほとんどの港が取扱量を減らしています。伏木富山港においても、取扱量の首位は維持しつつも、取扱量を半分近くまで減らしており、相当な不振が目立っています。
このことから、「環日本海」のかけ声の下、日本海沿岸の各港がロシアへの貿易に目を向ける一方、貿易の総量が減少した結果、少ないパイの奪い合いの状態となっていることが分かります。表1 日本海側地域の主要港における対ロシア(旧ソ連)輸出・輸入量(t)
港名 輸出 輸入 1986 1998 1986 1998 青森 − 22,823 34,876 27,802 能代 − 17,970 17,970 1,120 船川 − − 5,480 83,226 秋田 − − 64,625 88,549 酒田 − 42 554,693 391,871 新潟 75,705 97,480 599,114 417,926 両津 − − − − 小木 − − − − 直江津 − − 261,869 103,801 伏木富山 189,844 8,980 2,159,676 1,234,631 七尾 − 523 300,937 264,276 金沢 − 366 171,995 59,673 福井 6,590 − − 50,486 敦賀 37,739 438 264,160 222,340 舞鶴 22,137 176 628,197 251,830 鳥取 − − − − 境 − 1,644 125,234 108,992 浜田 − 11,614 − 102,319 三隅 − − − − 計 332,015 162,056 5,188,826 3,408,842
[2]韓国との貿易量 (表2)
韓国との取扱量は、ロシアとは逆に、日本海側全体では、輸出で25倍、輸入で5倍と大幅な増加を示しています。これに伴って各港とも規模増加あるいは新規取扱の動きを見せており、まさに「環日本海」のかけ声にふさわしい状態と言えるでしょう。大幅に増加した原因としては、1.各港が釜山からのフィーダー航路の誘致に積極的に取り組んだことと、2.阪神大震災で神戸港が被害を受けた事により、日本海側向け貨物の集散地として釜山の比重が高まったことによることが考えられます。
ただ、全体の取扱量が増加したとはいえ、ロシアとの取扱量と比較するとその規模はまだまだ小さく、より一層の増加が期待されます。また、現在同規模の取扱港がかなり分散していることから、取扱量増加の動きが鈍った場合、恐らく食い合いになるものと思われ、いかに他港から抜きんでるかが、今後の生き残り策として重要になってくるでしょう。表2 日本海側地域の主要港における対韓国輸出・輸入量(t)
港名 輸出 輸入 1986 1998 1986 1998 青森 − 20,601 8,171 160 能代 − − 4,643 − 船川 1,800 − 300 − 秋田 − 63,701 5,614 65,453 酒田 − 72,902 11,527 55,321 新潟 15,692 149,564 52,404 362,895 両津 − − − − 小木 − − − − 直江津 3,000 41,809 2,300 45,054 伏木富山 − 81,902 10,880 113,290 七尾 − − − 5,920 金沢 310 42,151 15,108 150,178 福井 − 192 − 2,669 敦賀 − 40,718 38,176 55,968 舞鶴 − 13,374 10,630 64,053 鳥取 − − − − 境 1,829 3,644 34,627 108,604 浜田 − − 1,226 5 三隅 − − − − 計 22,631 530,558 195,606 1,029,570
[3]中国との貿易量 (表3)
中国との取扱量は、輸出で若干の伸びを示すとともに、輸入で2.5倍という大きな伸びを示しており、これも「環日本海」のかけ声にかなったものとなっています。取扱港の増加は輸出入ともに見られますが、ほとんどの港で輸入取扱量が増加しており、各港で中国との貿易開拓が積極的に行われたことがうかがえます。その一方で、伏木富山港は、1986年には他港に比べて卓越した規模を誇っていたにもかかわらず、98年にはその規模を縮小させており、取扱港増加による食い合いのあおりを受けた格好となっています。この傾向が続きますと、韓国との貿易同様、食い合いにうち勝つ方策が、各港で求められることになるでしょう。表3 日本海側地域の主要港における対中国輸出・輸入量(t)
港名 輸出 輸入 1986 1998 1986 1998 青森 − 467 23,057 14,835 能代 − − − 219,053 船川 − 21,555 − − 秋田 48,914 23,306 115,511 140,203 酒田 − 807 10,180 21,884 新潟 30,278 83,245 143,981 405,456 両津 − − − 34,166 小木 − − − − 直江津 − 9,400 36,900 118,661 伏木富山 745 19,006 501,052 491,934 七尾 − − − 198,835 金沢 − 1,514 − 19,515 福井 − 1,003 − 38,281 敦賀 12,796 6,832 65,101 184,059 舞鶴 − 23 3,666 30,916 鳥取 17,753 − − 39,680 境 − 916 − 99,686 浜田 − − − − 三隅 − − − − 計 110,486 168,074 899,448 2,057,164
[4]北朝鮮との貿易量 (表4)
北朝鮮との取扱量は、数字ベースで見れば、輸出入とも3倍の伸びを示している。しかしながら、全体的な規模の点から見れば、他の3カ国と比べてまだまだ寡少であり、取扱港も増えはしているもののいずれの港も取扱規模はわずかです。おそらく現時点ではまだ貿易に先鞭を付けた段階であると思われ、今後の伸びが期待されます。表4 日本海側地域の主要港における対北朝鮮輸出・輸入量(t)
港名 輸出 輸入 1986 1998 1986 1998 青森 − − 7,774 118 能代 − − − − 船川 − − − − 秋田 − − 1,606 1,375 酒田 − − − − 新潟 4,218 8,010 14,982 9,453 両津 − − − − 小木 − − − − 直江津 − − 5,766 1,100 伏木富山 567 1,200 − 732 七尾 − − − − 金沢 − − − − 福井 − − − − 敦賀 − 1,264 − 6 舞鶴 − 2,423 3,845 88,319 鳥取 − − − − 境 − 180 1,318 5,970 浜田 − 198 − − 三隅 − − − − 計 4,785 13,275 35,291 107,073
2.対岸諸国との貿易規模における日本海側地域と太平洋側地域の比較
ここでは、日本海側の港が扱う全体量と太平洋側の主要港が扱う量を比較し、環日本海諸国にとっての日本海側地域の比重を推察したいと思います。太平洋側の港湾としては代表的なものとして横浜港と神戸港を選びました。[1]ロシア(旧ソ連)との貿易量 (図1,2)
まずロシア(旧ソ連)との貿易量を見てみましょう。先の節でロシアとの貿易を見た際、特に輸入における規模の大きさが目立っていましたが、この太平洋側との比較においても、輸入の取扱量で日本海側は太平洋側に大きく卓越しています。輸出についても1986年の時点では横浜、神戸のいずれに対しても下回っていたものが、1998年には上回るようになっており、日本海側地域が、ロシアにとって重要な地域であることを示していると言えるでしょう。貿易総量自体は1986年に比べて1998年は減少していますが、このロシアに対する日本海側地域の卓越した地位は維持されており、ロシアに対しては「環日本海」というフレーズが有効に働く可能性を示唆しています。
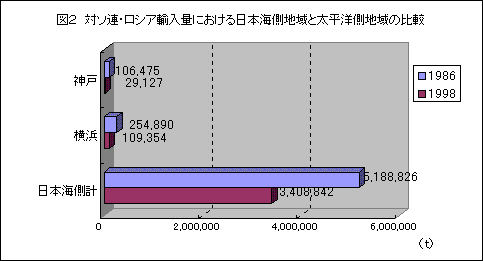
[3]韓国との貿易量 (図3,4)
次に、韓国との貿易量を見てみましょう。太平洋側の港の取扱量は、輸出入共に1986年に比べて1998年にはいずれも減少しているのに対し、日本海側地域では逆に大幅に増加しています。この結果、1998年の日本海側地域全体の取扱量は、輸出でかなりその差を縮め、輸入では神戸港や横浜港を上回るようになったのです。以上の動きから、韓国における日本海側地域の比重は、太平洋側のそれに比べて相対的に上昇したと言えるでしょう。このような韓国との取引の動きは、「環日本海」という言葉に実態を与える期待を持たせてくれます。ただ、現時点では日本海側地域全体でやっと太平洋側の1港に太刀打ちしている状態です。ロシアとの取引に見られるような卓越した地位を築くことを目指して、日本海側地域における対韓国拠点港を作る必要があるでしょう。
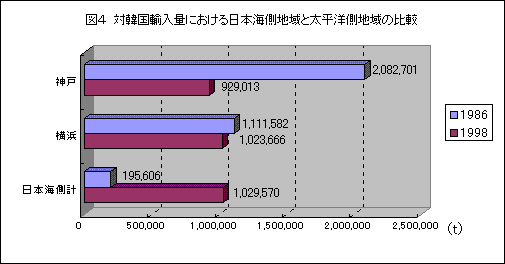
[3]中国との貿易量 (図5,6)
一方、韓国同様に貿易規模で伸びを示した中国の貿易量についてはどうでしょうか?。残念ながら、日本海側地域の取扱量は神戸港や横浜港に遠く及びません。特に輸入では、日本海側地域全体の取扱量は大幅に伸びているものの、神戸港や横浜港などでの伸びはそれを大きく上回っており、1986年のデータと比較すれば、日本海側地域の地位は取扱量の伸びとは裏腹に低下しているとさえ言えます。つまり、一見「環日本海」のかけ声のもと強化されたように見える中国と日本海側地域の関係は、太平洋側と比べてみれば相対的に脆弱になりつつあるわけです。このことから、中国にとって、日本海側地域は今も昔もさほど重要ではないことがうかがえるのです。
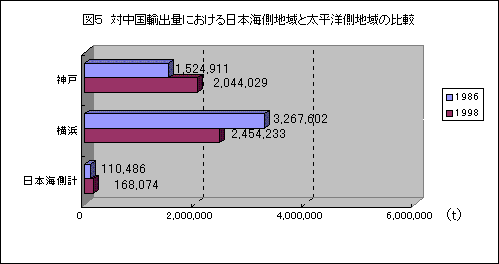
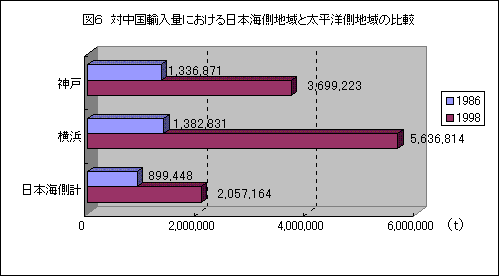
[4]北朝鮮との貿易量 (図7,8)
最後に、北朝鮮との貿易量を見てみましょう。北朝鮮との貿易規模は日本海側地域のみならず太平洋側といえどもやはり小さい状態であり、わずかな取扱量の増加でもその地位は大きく変動します。そのことを留意した上でデータを検討すると、1996年の時点で日本海側全体の取扱量が伸びた結果、特に輸入において横浜や神戸を上回っています。このことは日本海側地域が北朝鮮にとって重要な地域になる可能性を示唆しており、「環日本海」という点で明るい傾向であるといえるでしょう。
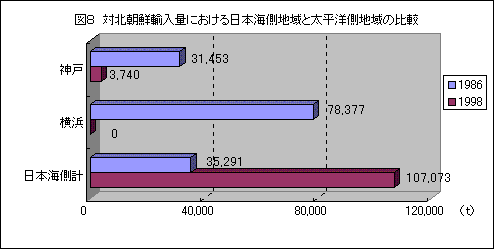
おわりに以上のことから、一口に「環日本海」とか「対岸諸国」といっても、各国にとって日本の日本海側をみる認識には温度差があることが見て取れます。とりわけ面白いのは、韓国や中国においては、日本海側地域全体の貿易規模の伸びが上向きであるとはいえ、太平洋側と比べると比重は大きくない、一方、貿易規模が縮小しているロシアやまだ寡少である北朝鮮においては、日本海側の比重は比較的大きいという、皮肉な結果です。このことは、今後「環日本海」という概念を実態あるものにするためには、どこをより重点的に対象とすべきかを考える大きな手かがりとなるように思います。