![]()
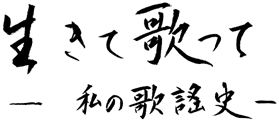 (50)
(50)
八 尾 正 治
汐 新湊市の巻(その2)
| 新しい歌に入って、まず「富山新港音頭」がある。これは昭和43年4月、待望の富山新港が開港した。これの祝い歌として作られたもので、旋律は箏曲旋法で純日本式だが、明るく典雅な歌曲である。地元の詩人松本福督が作り、福井溪水が作曲している。 |
富山新港 音頭
|
|
|
新 湊 慕 情
|
|
|
| 海の貴婦人といわれる帆船「海王丸」は、新湊にとって観光の目玉商品である。新湊市中央町でコンビニエンス・ストアーを経営する高島忠夫は、海王丸の優雅な姿に魅せられて歌を作った。平成3年3月、新湊出身の作曲家聖川湧がこれに作曲して、できたのが、「海王丸さん・ありがとう」である。行進曲風で歯切れのいいメロディ。小中学校へ配布し、子供たちにもおおいに歌ってほしいと、作詞者・作曲者ともども切望している。
|
海王丸さん ありがとう
|
|
|
新湊内川 橋めぐり
|
さて、ここもと聖川湧の活躍は目覚しい。彼の出身地新湊にかかわる歌の作曲が多いのは当然のこととして、全国的にヒットした名曲の数数をものして、今や歌謡曲界に揺るがぬ地位を得ている。彼は、昭和19年2月11日、新湊市堀岡古明神生まれ。本名は岩井実。金沢へ出て、新川二郎らと楽団を組織し、アルトサックスを吹いていた。38年に上京して、歌謡の世界を転転とし、辛酸をなめた。45年頃から作曲家として認められ、デビュー。55年に、三笠優子の「夫婦舟(みようとぶね)」がヒット。以来、香西かおりの「雨酒場」や「流恋草(はぐれそう)」などのヒット曲が続き、歌謡界での長い遍歴と鋭い感性で油の乗り切った活躍振りを展開している。 作詞者高島忠夫には、もうひとつ「新湊内川めぐり」という歌がある。かつては水質汚濁と破船の繋留で、顔をそむけたくなるような内川だったが、今ではきれいな水に蘇生し、架けられた橋も文化性豊かなものばかり。彼はこれを歌にしたもので、橋めぐりを楽しみたくなる。 |
汐 氷見市の巻(その1)
| 氷見市は旧氷見郡の各町村が大同合併して市を形成した、珍らしい例である。先史古代の遺跡、大境洞窟、朝日貝塚をはじめ、ここもと柳田布尾山古墳の発掘調査が、注目を浴びている。中世の戦乱を物語る、阿尾城址などの歴史遺産が極めて豊富である。海岸美に恵まれ、朝日山公園、海の幸山の幸、ホテル・民宿群など、観光都市としての特色を持っている。能登と隣接しているため、能都とよく似た風土性を持っている。そのひとつは、多様多彩な祭事習俗を今に伝承していること。従って歌謡にも恵まれているといえよう。 民謡も、カーカ節、青田節など、特色のあるものを伝承している。まず「氷見市制を祝う歌」から紹介しよう。これは昭和29年4月1日、氷見が1郡1市という大目標を実現した祝いを込めて作られたものである。4月27日、市政拡大祝賀会で発表された。 |
氷見市制を祝う歌
|
作詞者は、地元氷見市の辻本俊夫。昭和33年の「富山県民の歌」の作詞者でもある。作曲者の名は、明記していない。 −つづく− (富山県郷土史会長)